翌日、朝食を摂りに階下に降りると、宿のおかみが切り出した。
「実は、ついさっきお触れが回ってきてね、嵐の季節が到来したから、大型船は航路を変えるって。
今年はいつになく早くて……ほら、あんたらが巻き込まれた嵐が、最初のもんでさ。
こうなると、一月くらいは、メリーディアスにゃ寄港しなくなっちまうんだよ。
その間、あんたらどうするね? ずっと、うちに泊まってるのかい?」
「一月もか、困ったな。昨日言った通り、もう帰郷するつもりでいたのだが。
それでも、ファイディーに向かう船はあるのだろう?」
サマエルは尋ねた。
「あー、どうだろう、ここらの船は小さくてあまり遠くまで行かないし、直行便はないかもねぇ。
多分、乗合船を乗り継いで帰るしか、ないんじゃないかな」
「え、そうなの? レシィ、どうしよう……」
途方に暮れた顔をしたジルに、サマエルは微笑みかけた。
「大丈夫だよ。食べたら港に行ってみよう、船乗りに詳しい話が聞けるかも知れない」
「うん」
外に出ると、少し風が出ていたが、まだ嵐というほどではなかった。
ヤシの木が揺れる中を、二人は港に向かった。
「抱っこされて、飛んで帰るのもアリだけど、二人きりで乗れるお船があったらいいのにね。
……ほら、あれくらいの」
ジルが指差す先には、年季の入った小ぶりの帆船が停泊していた。
「それはいい!」
サマエルは、思わず声を上げた。
「よし、善は急げだ、あの船の持ち主に聞いてみよう」
「うん!」
ジルも顔を輝かせた。
探し当てた船主の老人は、幸い、古くなった船を手放すことを望んでいた。
すぐに交渉は成立し、サマエルが代金を支払おうとしたとき、若い女性が奥から出て来て言った。
「ジイちゃん、吹っかけ過ぎだよ、それじゃ、新しい船買えちまうじゃないか。
あんたもお人好しだね、少しは値切りなよ」
「こら、取引に首を突っ込むんじゃない。
装備も全部、つけた上での値段だ、高過ぎやしないわい」
「へーん、そうですかぁ」
老人は、渋い顔で舌打ちした。
「……ったく。すまんね、うちの孫は生意気で。
船員のあてはあるのかな」
「ああ、私達だけで何とかなりますよ」
サマエルは答え、荷物を取りに二人で宿へ戻った。
宿賃を精算し、名残惜しげなおかみに別れを告げて港に戻ると、帆船のそばには荷物を背負った船主の孫娘がいた。
「あんたら、素人だろ?
あたいが乗ってあげるよ、今は嵐の季節だし、ここらの海は、あたいの庭みたいなもんだしさ」
自信満々に、女性は言った。
「気持ちはありがたいが、大丈夫、嵐には気をつけるよ」
「でも、妹さんには、力仕事は無理だと思うけど?」
女性は口を尖らす。
「……妹?」
ジルは眼を見開く。
「彼女は私の妻だ。悪いが、この船はもう私達の物だし、他の女性を乗せる気はない」
サマエルはジルの肩を抱き寄せ、きっぱりと言ってのけた。
「えっ、奥さん!?」
女性は、ぽかんと口を開けた。
「お前、そんなとこで何やってんだ」
そのとき、元船主の老人がやって来た。
「あ、ジイちゃん……」
「こいつがまた、何か余計なことをしたんかね?
勘弁してやってくれ、悪気はないんじゃが、栄養が胸ばかりに行っちまってな」
「何さ、ふん!」
孫娘は、ぷいと横を向いた。
「この子が生まれた記念に作った船なんでな、愛着があるんじゃろうよ。
さ、受け取ってくれ、秘蔵のワインじゃ。
船の、新たな旅立ちにな」
老人は、丸みを帯びたワインの瓶を差し出す。
「ありがとう!」
「頂いていきます」
礼を言って二人は船に乗り込み、サマエルは船主や孫娘の心から読み取ったやり方で、てきぱきと帆を広げ、ジルはそれを手伝う。
そうして、船は、元の船主達に見送られて出港した。
手を振る二人の姿が見えなくなると、サマエルは、船べりにもたれて大きく息を吐いた。
「大丈夫?」
「……ああ。一時はどうなることかと思ったけれど、ね」
サマエルは、どうにか笑みを浮かべた。
「うん。これで二人きりね」
「……実は、旅行に出る前の占いで、『女難の相』が出てね。
嫌になるほど、よく当たってしまったよ。
でも、これでもう……」
サマエルは天を仰いだ。
ジルは眼を見開いた。
「えっ、言ってくれればよかったのに」
「いや、まさか、ここまでとは……」
嫌な記憶を振り払うように、サマエルは頭を振った。
「それで、ね……一つ、お願いが、あるのだけれど、いいかな……?」
彼の方から要求を出すのは珍しく、ジルは身を乗り出した。
「何? 何でも言って」
「食べ物や水は、魔法で出せる……だから、港、というか……どこにも寄らないで、ファイディーに行ける……と思うのだけれど……どうだろう?」
おずおずと、サマエルは提案した。
「それ、あたしも言おうと思ってたの。
サマエルは、にぎやかなところが苦手でしょ、だから」
「そうか、ありがとう」
サマエルは妻を抱き寄せた。
夜になると風が強くなって来て、波も高くなり始めた。
島影で錨を下ろし、嵐が過ぎ去るのを待つ間、二人は改めて船を見て回った。
設備は古くとも航海にはまったく支障なく、船室は数人がゆったり寝られる広さがあった。
「でも、縁起がいいわよね、このお船」
サマエルが出した大きなベッドに腰掛けて、ジルは言った。
「孫の誕生記念に作った船、だからかい?」
「うん。おじいさん、さっきのお金で、また船を作ってあげる気なんでしょ」
「そうだね……ああ、どうせなら、この船も新品に戻そうか。
私達にとっても、新しい門出だし」
「うん! このお船にも、ファイディーまで頑張ってもらわなきゃいけないもんね!」
ジルの声も弾む。
そこで、サマエルは魔法を使い、船を復元した。
「わー、綺麗! 木の香りがするわ……素敵!」
ジルは深呼吸し、真新しくなった船室を見回す。
結界を張って新しい船を守ると、二人は眠りについた。
のんびり釣りをし、海鳥に話しかけ、ときにはイルカの群れと泳ぎ、星や太陽の位置で航路を知る……穏やかな日々が続く。
風任せ、波まかせの船旅は気分を和ませ、ささくれだったサマエルの神経を静め、癒してくれた。

そうして二月が経ち、そろそろカミーニ港に着くという頃、またも嵐に遭い、彼らは近くの無人島へ避難した。
そこには、乗合船らしき先客が停泊していた。
近づいて行くと、一人の男が甲板に出て来てカンテラを振り、叫んだ。
「おおい、そっちに医者はいないか!
お客のご婦人が、産気づいてしまったんだ!
「私は薬師だ、医術の心得がある!」
サマエルは、嵐に負けじと叫び返した。
「ありがたい、頼む!」
「あたしも行くわ!」
三人が乗合船の船室に入って行くと、大きなお腹の赤毛の女性が、ベッドで苦しげな声を上げていた。
「ベッツィー、しっかりしろ!」
若い男が、女性の手を握って励ましている。
「薬師の人を連れて来たぞ」
船の乗務員が声をかけると、男はホッとした顔で頭を下げた。
「お願いします」
「よし、では、まず、お湯を沸かして。それからタオルを。出来るだけたくさん欲しい」
「分かった!」
サマエルの言葉に、乗務員は駆け出した。
「俺も手伝います! ベッツィー、頑張れよ」
若い男は、妻の手をそっと放して、後を追った。
代わりにジルが優しく、妊婦の手を取る。
「あたしジル。サマエ……ううん、レシィは、お医者さん顔負けに色んなこと知ってるの、だから、安心してね」
「ありがと、……うっ」
ベッツィーは、陣痛に身をよじる。
「ちょっと失礼」
サマエルは毛布をまくり、妊婦の診察を始めた。
「もう破水しているね、
……奥さん、あなたは初めてのお産かな?」
「え、ええ」
「大丈夫、順調だよ。
少し時間はかかるかも知れないが、
「はい……」
額に汗を浮かべた妊婦は、うなずく。
“ホントに詳しいのね。赤ちゃん、取り上げたことあるの?”
ジルが念話で尋ねると、サマエルは、かすかに頭を振った。
“いや。でも、お産に関する本は、たくさん読んだから”
“え? じゃ、難しい顔して読んでたのって……”
“そう。お産……女性の体の変化について何も知らないから、不安なのかも知れないと思ってね。
それが、こんなところで役立つとは”
その夜遅く、赤ん坊は無事生まれた。
大役を果たしたサマエルは、若夫婦だけでなく、船の乗務員や乗客にも感謝された。
嵐も収まった夜明け前、二人は船に戻った。
「お疲れ様」
差し出されたカップを受け取り、サマエルは微笑んだ。
「ありがとう」
「頼もしかったわ、サマエル」
「……そうかな」
照れたように、彼はお茶をすする。
「何だか、少し自信がついたような気がするよ……色々と。
キミのお陰だ、ありがとう」
「ううん、サマエルが頑張ったからよ。
でも、もう着いちゃうのね……もっと、乗ってたかったな」
「……だったら、この船で、屋敷まで帰るのはどうかな?」
「あ、魔法使って? 素敵!」
翌日の深夜、船はカミーニに着いた。
サマエルは、港には寄らずに川を
帆は熱い風をはらみ、船は滑るように砂漠を渡る。
もし、その様子を見ることができた者がいたとしても、自分の眼を疑ったことだろう。
幻覚だと思ったかも知れない。
「わあ、すごい、すごい!」
ジルははしゃぎ、サマエルもいつになく、気分が高揚していた。
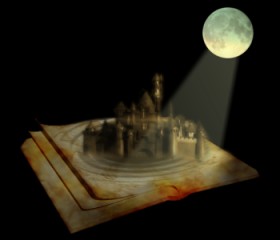
風任せで一週間が経ち、単調な景色に飽き始めた頃。
「何かしら、あれ?」
ジルが指差す先には、折れた石柱や建物の土台と思われるものが、紅い砂から顔を出していた。
「昔滅んだ、アグラーヴォ王国の遺跡さ。
……私が破壊したのだよ」
サマエルは、
「ええっ!?」
妻が驚くと、彼は眼を伏せた。
「……私が怖いかい、ジル」
彼女は首を横に振った。
「いいえ。でも、なぜ?」
「……壊したといっても、城だけで、人の命は奪っていない。
私を慕ってついて来た人々は村を築いた……ワルプルギスの
……ああ、数日でそちらに着くと、タィフィンに知らせておこう」
サマエルはそう言って、話を打ち切った。
それを聞いてから、ジルは少し元気をなくしたようだった。
彼は、黙っていればよかったと後悔した。
二日後、山に着き、彼はふもとに帆船を隠した。
村人達は総出で、彼らの帰還を祝ってくれた。
サマエルは他の街では見せたことがない、くつろいだ表情をし、ジルも顔なじみの村人と話すうち、帰って来たという実感が湧き始めた。
そうして、ようやく二人は屋敷に戻って来た。
懐かしい門をくぐる。透明な使い魔が彼らを出迎えてくれた。
ひとまず居間でくつろいでいると、荷物を運び終えたタィフィンが、魔法学院から村宛に届いたという手紙を持って来た。
ファイディーの建国直後、魔法を教える学校が必要だと彼が王に進言したことで学院は設立され、その後も彼は少々、運営に関わっていたのだ。
「別れ際、リュイに学院行きを勧めておいたのだよ、魔力の制御と絵の勉強が一緒に出来るとね。
これは多分、彼が着いたという知らせだろう」
だが、手紙を読み進めるうち、サマエルは難しい顔つきになり、内容を読み上げ始めた。
「……『つきましては、リュイ・ネスター殿を婿養子として迎えたいと存じます。渋る彼を、ぜひともご説得頂きたく』……」
ジルは眼を丸くした。
「何それ!? 彼にはシエンヌがいるのに!」
「──はあ。まったく、学院長も何を考えているのだか。
どうせ、娘が一方的に熱を上げているのだろうが、それを
サマエルは首を横に振る。
「本当、勝手よね。リュイの気持ちも考えないで」
ジルもぷりぷりしていた。
「まったくだね、きつく釘を差しておかないと。
権力を笠に着て、嫌がる生徒に強要するなど、教育者失格だ。
リュイに娘を近づけるな、さもなくば学院を辞めさせ、私が直接彼を指導するとね」
彼は手早く返事をしたため、魔法で送った。
翌朝、ジルは体調を崩した。
熱はないが、数日前から時々、吐き気があったという。
長旅の疲れが出たのだろうと、サマエルは精気を送り込んでみたが、効果はない。
そこで、彼は、地下室から薬酒を持って来るよう言ったが、それに対するタィフィンの答えは、意外なものだった。
「あの、お館様……奥方様は、もしや、ご
「えっ!?」
「何だって!?」
サマエルは急いで、妻の腹部を凝視する。
「……たしかに胎児がいる。よく分かったね」
「おめでとうございます、お館様、奥方様」
使い魔の声は弾んでいた。
「ありがと、タィフィン。あたし、お母さんになるのね」
ジルの瞳は輝いたが、腹に触れ、おずおずと尋ねた。
「うれしい? サマエル……」
「もちろんだとも!」
力強く答える彼の顔も、自然とほころんでいた。
THE END.