「痛いわ、痛い!」
「済みません、済みません……!」
今度の場合、抱きついた相手が悪かったらしい。
地面に倒れて悲鳴を上げているシエンヌと、彼女をかばいながら謝っている青年は二人揃って、怒り狂った男に
「ひどい、やめて!」
飛び出そうとするジルを、サマエルは押さえた。
「キミはここにいて。私が行こう」
「ええ、お願い」
すがるような視線を向けてくる妻を安心させようと、サマエルはうなずいた。
「すぐにやめさせるよ。だが、ずいぶん荒っぽい男を捕まえてしまったようだね、シエンヌは」
それから彼は、荒れ狂う男に近づいて行き、肩をたたいた。
「もうその辺でいいのでは? いくら腹に据えかねても、女性に乱暴を働くのはどうかと思いますが」
すると男は険しい顔で振り向き、サマエルを睨みつけた。
「なんだ、お前は」
「私もあなた同様、いきなり抱きつかれて驚いた者ですよ。
その女性は、お気の毒に、
ですから奥様、ご心配はいりません、旦那様は潔白ですよ。
あなたからも、おやめになるよう、口添えをして頂けませんか」
サマエルは、男の隣に立つ女性にだけ自分の顔が見えるようにフードをずらし、微笑みかけた。
夢魔である魔族の王子、その微笑の効果は、絶大である。
女性は、ぽっと頬を赤らめ、夫に向かって言った。
「ねぇ、もういいわ、あなた。この人、頭がおかしいんですってよ、可哀想じゃない。
それにわたし、あなたが浮気したなんて、思ってないわよ」
「う、……そ、そうか?」
妻に言われて頭が冷えた男は表情を緩め、うなずく。
「ええ、もう行きましょうよ、人目もあるし」
「そ、そうだな。……ったく、縄で縛っとけ、気違い女!」
男は捨て台詞を吐き、妻と一緒に去って行った。
「大丈夫?」
「うるさいわね、放っておいてよ、お節介!」
ジルが差し出す手を、邪険に払いのけてシエンヌは立ち上がり、走り去った。
サマエルは肩をすくめた。
「どうやら今の
キミがリュイだね、大丈夫かい? 私達はさっき、テスさんに助けられたんだが」
「そうでしたか。大丈夫です、済みません……シエンヌは、あなた方にもご迷惑を……」
ふらつきながらも自力で立ち上がった青年の唇は切れて血がにじみ、頬や目の周りには、殴られて出来た
一般的なメリーディエス人よりもかなり色白で、悲しげな瞳も淡いグリーンをしている。
短い髪の色は黒かったが、島の住人とは違い、ウエーブはかかっていない。
「はい、これでお顔をふいて。血が出てるわ」
「いえ、平気ですから」
ジルが差し出すハンカチを、青年は受け取らなかった。
「ねぇ、どうしてシエンヌは、あんな風になっちゃったの?
あたしのお父さんも昔、病気で死んじゃったわ。
だから、すごく悲しいのは分かるんだけど、でも、それでどうして……?」
「お父さんが亡くなった直後は、彼女もあんな風ではなくて、それどころか
もちろんショックは受けてましたけどね。
でも、今度はお母さんも倒れてしまって。そしたら彼女は、掌を返したように僕を避け始めて……。
そして、王子様探しに夢中になっていったんです……」
「だが、どうしてキミでは駄目なのだろうね? 恋人同士だったのだろう?」
今度はサマエルが尋ねる。
「だって、今のシエンヌが欲しいのは、売れもしない絵ばっかり描いてる“貧乏な絵描き”じゃなくて、お父さんが生きてた頃と同じような生活を保障してくれる、“裕福な誰か”なんですよ。
貧しくても、僕は僕なりに、シエンヌはもちろんお母さんのことだって、ちゃんと面倒を見るつもりでいたんですけどね……。
あ、僕、彼女を追いかけなきゃ。また、誰かに迷惑かけるといけないから。失礼します……」
リュイは、拳で
「……可哀想ね。リュイも、シエンヌも、お母さんも。
何かできることないかな……そうだわ、ねぇレシィ、リュイの絵を買ってあげたらどうかしら。
お金が手に入ったら、シエンヌも、彼のこと見直すんじゃない?」
ジルは、サマエルを見上げた。
「それはいい考えだね。どうせなら、旅の記念に私達を描いてもらおうか」
「わあ、素敵!」
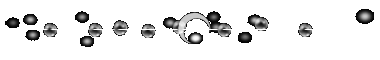
「やあ、お二人さん、来てくれたのかい!」
リュイの家を訊くため訪ねたテスの喫茶店は、たくさんの客でにぎわっていた。
「テスさん、先ほどはどうも。いいお店ですね」
サマエルの言葉に、テスは頬を緩めた。
「おかげさんで繁盛してるよ。さ、そこがちょうど空いた、座って。
メリーディエス名物の、フルーツジュースでもどうだい、よく冷えてるよ」
「はい、お願いします」
二人はカウンター席に並んで座り、リュイに絵を頼もうと思っていることを話した。
テスは、親指を一本突き出し、賛意を示した。
「そいつはいい、リュイの腕は確かだよ!
町長一家の肖像画を描いて町長に見込まれて、ぜひ娘の婿にって言われてるらしいぜ。
娘は美人だし、何より、生活を気にしないで絵を描いていられる。似合いの夫婦になると思うよ。
今の……少しおかしくなっちまったシエンヌと一緒になるよりか、幸せになれるだろうな」
テスの話を聞いた二人は、顔を見合わせた。
ともかく彼らは、リュイの家へ行ってみた。
小ぢんまりした家からは、さほど貧しさは感じられなかった。
庭はきちんと手入れされ、南国特有の花々が咲き誇っている。
だがテスは、リュイ一人が、三人分の生活費とシエンヌの母親の薬代を働いてまかなっているので、金は常に足りないはずだと言っていた。
家で傷の手当てをしていたリュイに、絵を頼みたいと言うと、彼はやつれた顔を輝かせたが、すぐに眼を伏せてしまった。
「……済みません、この頃は絵の注文をお受けしてないんです……。
お恥ずかしい話ですが、絵の具も買えなくて……日雇いの仕事をして、何とか暮らしてる感じなので……」
「では、料金を前払いしよう。それで絵の具やカンバスを揃えればいい」
「ええっ、こ、こんなに!? ……いけません、こんなには頂けませんよ」
サマエルは四枚の銀貨を出して見せたが、リュイは勢いよく首を振り、受け取りを拒んだ。
「じゃ、こうしましょ。
まず、このお金を半分、あなたにあげる。そして、できた絵が気に入ったら、残りを払うわ。
これでどうかしら?」
ジルが言い、リュイの顔を覗き込んだ。
「え、ええ……では」
そこでようやく絵描きの青年は、伏し拝むようにして、銀貨を手にした。
「私達は、『おてんば人魚亭』に泊まっている。明日、道具を揃えて、昼過ぎに来てくれ」
「楽しみにしてるわ、よろしくお願いね」
ジルはにっこりした。
「はい。ご期待に添えるよう、頑張ります」
青年は深々と頭を下げた。
翌日、リュイは約束通り、昼過ぎに宿屋にやってきた。
テスが言っていた通り、彼の腕は確かで、カンバスにすらすらと下書きをしていくデッサンは狂いもなく、サマエルの高貴な美貌とジルの純粋無垢さを、正確に写し取っていった。
「さすがだね。町長一家の肖像画を書いて、喜ばれたと聞いたよ。
ぜひ婿に、とも請われているそうだね」
一休みしてお茶を飲んでいるとき、サマエルは何気なく水を向けてみた。
「ああ、テスさんに聞いたんですね。
たしかに、町長さんの娘さんと結婚すれば、絵の学校にも通わせてくれるって言われてますよ。
……ずっと断ってたんですけど、最近じゃそれもいいかなって、思い始めてるんです……。
結婚後も、シエンヌのお母さんの面倒を見てくれるっていうし、それよりも……シエンヌはもう、僕と話もしてくれないし、眼も合わせてくれないから……」
リュイの淡い緑の瞳は、悲しげに揺れていた。
「しかし、裕福な暮らしを望むのなら、シエンヌ自身が金持ちと結婚すればいい。
どうしてそうはせずに、
サマエルは首をかしげる。
「ああ、それは……昔、実際に会ったことがあるからですよ」
「え?」
予想外の答えに、サマエルは眼を見開いた。
「十年ほど前に、彼女と仲のいい叔母さんがお嫁に行くことになって、彼女も式に参列するために一緒に行ったんだそうです。
そのとき泊まったオアシスで、その人を見かけたんだと言ってました」
「オアシス……では、叔母さんはファイディーに嫁いだのか」
「ええ、そうです。
皆が寝静まった夜中、その人は彼女が見ていることに気づかず、着物を脱ぎ捨てて水浴を始め……。
満月が照らし出したその顔は、この世の者とは思えないほど美しく……彼女はただ、ぼうっと見とれていたそうです。
月が雲に隠れ、再び出てきたとき、もうその人はいなくなってた……長いさらさらの銀髪に紅い眼をして、年は二十七、八くらい……でも、人間にはそんな外見の人は珍しいし、ひょっとしたら、オアシスに住む水の精だったのかも知れないと……。
その話自体は僕も何度か聞かされてて、でも、とても綺麗なおとぎ話みたいに思ってました。
彼女も、以前はそう言ってたんです。なのに今頃になって……」
サマエルはジルと顔を見合わせ、つぶやいた。
「……長い銀髪に紅い眼、年は二十七、八……か」
「ええ。そういえば、失礼ですが、あなたはお幾つですか?」
「私? ……二十七になったところだよ」
リュイの問いに、サマエルはよどみなく答えた。
旅行の間は、年齢はジルの三歳年上ということにしておこうと決めてあったのだ。
「じゃ、やっぱりあなたじゃありませんね。
髪や眼の色が違うのはもちろん、十年前には、あなたはまだ少年だったでしょうし。
でも、変だな。今までシエンヌが抱きついた人は、あなた以外は皆、銀髪だったんですが」
「……ふうむ、なぜだろうね」
動揺を
「まあ、彼女の気持ちも分かりますけど。
あなたは……その、男にしておくにしては惜しいくらい、美しい方ですから……」
言ってしまってから、リュイは顔を赤らめた。
「私は男だ、男性に美しいと褒めてもらっても、あまりうれしくないね」
「あ、そ、そうですよね、すみません」
青年は慌てて詫びた。
“サマエル、やっぱりあなたのことみたいね”
ジルの念話を、サマエルは肯定する外なかった。
“……そうだね、見られていたとはうかつだった。だが、私は誓って彼女には何も……”
“分かってるわ。シエンヌだって、ただ見かけただけって言ってたんでしょ”
“ともかく、白を切り通すしかないだろうねぇ、この状況では……”
ため息混じりに、彼は答えた。
二人が視線を交わしているところを見たリュイは、言った。
「すみません、無駄話をしてしまって。続きを描きますね」
「ああ、お願いしようか。
ところで、どれくらいで出来るものなのかな?」
気を取り直し、サマエルは尋ねた。
「ええと……何日くらい滞在なさる予定なんでしょうか。
絵そのものは、お急ぎなら三日ほどで完成しますが、絵の具が乾くのに、やっぱり同じくらいかかってしまうので。それでも、ここは暑いので、寒い地方の半分の期間で済みますけど」
「いや、さほど急いではいない。キミが気の済むまで、時間をかけてくれて構わないよ。
それまで私達は、南の島を満喫するから」
サマエルは微笑んだ。

そうして一週間が過ぎ、絵は完成した。
「素晴らしい出来だね」
「ホント、すごく上手! レシィがとっても美人に描けてるわ!」
「ジル……」
サマエルが困った顔をすると、ジルはにっこりした。
「冗談よ。とってもカッコいいわ」
「そう。では、約束のお金を」
残りの銀貨を支払うと、リュイもうれしそうに受け取った。
「ありがとうございます」
「そうだ、メリーディエスには他にも島があります、絵の具が乾くまで回ってらしたらいかがですか?
その間、僕が絵を預かりますよ」
「素敵! 行ってみましょうよ!」
ジルが眼を輝かせたとき。
「ここね、とうとう見つけたわ!」
声と同時にドアがばたんと開き、シエンヌが足音も高く、部屋に入って来た。
その手には、鋭いナイフが握られている。
「なによ、こんな絵!」
それから、くるりと向きを変え、ぎらぎらした眼でジルを睨みつけた。
「あたしの王子様を返して!」
「やめろ、シエンヌ!」
はっとして止めようとするリュイの手をかいくぐり、シエンヌはナイフを振りかざす。
「うっ!」
「きゃあ、レシィ!」
しかし、その光る刃は、妻をかばったサマエルの胸に突き刺さったのだった。