異国情緒あふれる食事を終えると、サマエルは言った。
「ごちそうさま。
さて、私達は一寝入りするよ。今朝は、船がとても早く着いたのでね」
彼自身は大して眠気を覚えてはいなかったが、妻の方は空腹が満たされると共に、何度もあくびを繰り返していたのだ。
「ええ、ええ、新婚の方々は、皆さん必ずそう仰いますとも」
おかみは、訳知り顔にうなずき、にっこりした。
「昨夜も遅かったんでしょう、どうぞごゆっくり。
ああ、ウチのベッドは丈夫な作りですから、音は静かですよ」
「……え? あたし、そんなに寝相悪くないわよ」
「──さ、行こう、ジル」
きょとんとした顔の妻を促し、くすぐったい思いをこらえながら、サマエルは階段を登る。
部屋に戻った彼らは、用心に越したことはないと考え、結界を張ることにした。
天使にしろ人間の賊にしろ、寝込みを襲われるのはごめんだった。
船の時には、魔法使いの航海士が乗り組んでいたお陰で、その心配だけはなかったのだが。
そうしておいてベッドに入ると、思いの外、疲れていたのだろう、ジルの寝息を聞くまでもなく、サマエルもすぐに寝入ってしまった。
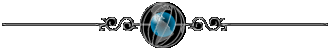
先に眼が覚めたのは、サマエルの方だった。
隣のベッドを見ると、妻はまだ夢の中にいた。
その寝顔をしばし眺めて幸せな気分に浸った後、彼は出かける旨のメモを残し、音も立てずに部屋を出た。
結界を確かめてから、階下へと降りていく。
「おや、だんなさん、お目覚めで。奥さんは?」
おかみが声をかけて来た。
「まだ寝かせておくよ、疲れているようだから。
私は、ちょっと裏の砂浜を散策してみたくなってね」
「そうですか、お気をつけて」
「ああ」
風が心地よく吹き抜ける砂浜を、サマエルは麻のローブをまとい、歩く。
すでに午後も遅くなっていて、日は翳り始め、昼間より過ごしやすくなっていた。
表の
時々立ち止まっては、彼は浜風を胸一杯に吸い込み、どうすれば妻を幸せにできるかを考えた。
とっくに答えは出ているのに、未だ踏ん切りのつかない自分を情けなく思いながら、どれくらい歩き続けたのか、サマエルは、前方から話し声が聞こえて来ることに気づいた。
魔族である彼は、かなり遠くの物音や姿を捉えることができる。
眼を凝らすと、一本だけぽつんと離れたヤシの木陰に、一組の男女がいるのが見えた。
恋人同士なのだろう、笑いながら何事かを話していた二人は、彼には気づかないまま、やがて見つめ合い、口づけを交し、そして……。
(……やれやれ、まだ日も沈まないうちに、人目もはばからず)
サマエルは眉をひそめ、フードを深くかぶり直して、
それでも、あんな風に情熱に任せて、ジルを抱くことができたら……とも思う。
彼が普通の男だったなら、とっくにそうしていたはずなのだが。
気晴らしに散歩に出たはずなのに、自分の不甲斐なさを思い知らされてしまったようで、彼は余計に気分が沈んだ。
重い足取りで宿に帰ると、おかみと話し込んでいたジルが、すぐ彼に気づいて飛びついてきた。
「お帰りなさい、レシィ! 行き違いになるかなって思って、待ってたの」
「すまない、遅くなって……」
サマエルは、思いを込めて妻を抱きしめた。
ジルは微笑み、否定の仕草をした。
「ううん、今、起きてきたばっかりよ」
「……そう。ジル、外は涼しくなっているよ。あちこち見てみないか」
「うん!」
「行ってらっしゃいませ!」
元気なおかみの声に送られて、彼らは宿を後にした。
「あ、あれは何? これは?」
どこを見ても、何を見ても珍しく、ジルは指差してサマエルに訊く。
彼が知っている物もあったが、やはり初めての土地、分からない物の方が圧倒的に多かった。
小腹が空いた彼らは、屋台の食べ物を買ってみた。
「これ、美味しいわね!」
「そうだね」
二人は眼を見合わせて微笑み、にぎやかな通りを進んでいく。

そのときだった。
彼らの幸福な時間を、粉々に打ち砕く出来事が起きたのは。
「──見つけたわ! わたしの王子様! もう離さないから!」
道の真ん中にうずくまっていた女性が、突如大声を発し、彼に抱きついて来たのだ。
「きゃっ、何?」
ジルがびっくりしたのは当然だが、妻を除き、人との接触を極端に避けて来たサマエルは、息が止まるほど驚いた。
「──な、何だ、キミは!?」
「まあ、ひどい、王子様、わたしを忘れたの!?」
女性は顔を上げ、ぎらぎらとした黒い眼で、恨めしげに彼を睨んだ。
容姿は特段美人というわけではなく、この島の者特有の浅黒い肌、縮れた濃い茶色の髪をし、それを長く伸ばして後ろに束ね、南国の花を飾っている。
派手な黄色い花柄の袖なしワンピースを着て、足は裸足だった。
サマエルは必死に記憶をたどるも、まったく面識のない相手だった。幾度見直しても。
女性に警戒心を抱く彼は、なるべく再度は係わらないよう、一度会った相手の顔は忘れないようにしてきたのだ。
つまり、やましいところは何もなかったのだが、妻の視線を痛いほど感じた彼は、冷ややかに言ってのけた。
「忘れるも何も、私はキミを知らない。大体、私は王子などではないし、人違いだ」
しかし女性は納得するどころか、さらにぎょっとする言葉を吐いた。
「嘘つき! お妃にしてくれるって約束したじゃない!」
「き、妃だって……!?」
サマエルは、困惑して相手を見つめた。
ジルにさえ、『妃になって欲しい』などと言った覚えはないというのに。
“正直に言って、サマエル。ホントに知らない人なの?”
たまりかねたように、ジルが念話で訊いて来る。
その妻の手を握り、栗色の眼を覗き込んで、サマエルはきっぱりと答えた。
“ああ。知らない。信じてくれ。知り合いだったら、船のときのようにちゃんと話しているよ”
“それもそうね。うん、信じるわ”
ジルはにっこりした。
妻の笑顔に冷静さを取り戻した彼は、今度は声に出して女性に話し掛けた。
「それほど言うなら、私の名前を言ってみてくれ。いつ、どこで会ったのかも」
「何よ、この女! わたしの王子様に馴れ馴れしい!」
だが、彼の声が耳に入った様子はなく、女性は大声を上げ、ものすごい
「やめてくれ!」
女性の手を、サマエルは跳ねのけた。
「それではキミは、名も知らない男と結婚の約束をしたのか?
大体、王子とは、どこの国の王子なのだ?
これ以上言いがかりをつける気なら、女性相手でも容赦はしないぞ!」
「ああ、ひどい! ひどいわ! わたしを捨てて、こんな女に乗り換えるなんて!
──あああー!」
女性は手で顔を覆い、いきなり大声で泣き出した。
目つきといい、言動といい、正気だとはとても思えない。
「……ジル。どうやら、この女性は少し頭がおかしいようだ、気の毒に。
キミ、落ち着いて。私は本当にキミを知らない、人違いだよ」
サマエルは、女性を説得しようと試みた。
「嫌よ、今度こそ逃がさないわ! わたしを、二度も捨てさせたりしないから!」
しかし、女性は気違いじみた力で再び彼にしがみつき、濃茶の髪を振り乱してわめき立てた。
頭に飾られていた花が地面に落ち、紅い花びらを散らす。
「キミ、とにかく、もう一度話を……」
「嫌よ!」
もみ合ううち、女性はサマエルのローブを引っ張り、最後にはフードをむしり取った。
次の瞬間、四方からどよめきが起こり、同時に女性の荒々しい態度が一変した。
「ああ……美しい……やっぱりあなただわ、わたしの王子様……!」
彼女はうっとりと彼を見上げた。
今の騒ぎで、彼らの周りには野次馬が集まり、人垣が出来ている。
その只中で、変装しているとはいえ、顔をさらすことになってしまったサマエルの眼に、黒い炎が燃え上がったその刹那。
「またあんたか、シエンヌ!
毎日毎日、まったく人騒がせだな、いい加減にしてくれ!
どうせこの人だって、あんたの王子様なんかじゃないだろうが!」
辺りに響き渡る大声に、はっとしてサマエルが振り返ると、長身でたくましい体つきの中年男が、人垣をかき分けてやって来るところだった。
浅黒い肌と濃茶の髪、メリーディエス独特の服装をしており、やはり島の住人なのだと思われた。
「うるさいわね、あんたなんかに何が分かるの!
この人こそ、わたしが待っていた王子様なんだから──きゃあ、何すんのよ!」
サマエルにしがみついたまま憎まれ口をたたく女性を、現れた男は、慣れた手つきで引きはがす。
「放してよ、この馬鹿!」
「はいよっと」
そして、手足をばたつかせる彼女を手早く地面に座らせ、男は周りの群衆に向けて声を張り上げた。
「──皆さん、聞いてくれ! この娘はちょっとココが……」
男は、自分の頭を指差す。
「弱いんだ。外国人のイイ男を見ると、いつもこうやって抱きついて、騒ぎを起こすんだよ。
──さ、分かったら、散った、散った!」
「な、なによ、わたしは頭がおかしくなんかないわ!」
シエンヌは叫び、勢いよく立ち上がると、野次馬をかき分けて走り去って行った。
それを見送り、男は、ぱんぱんと手をたたいた。
「さあさあ、もう終わりだ! 行ってくれ、通行の邪魔だよ!」
するとようやく、人々は、ざわつきながら去って行き始めた。
それから男は、あっけに取られて成り行きを見ていたサマエルとジルに、笑い掛けた。
「新婚さんかい? 災難だったな。
特に奥さん、びっくりしたろ? けどご主人は
シエンヌは、誰にでも同じことを言うんだ、『あなたこそ、わたしの王子様』ってね」
「ええ、あたし、レシィを信じてるから」
ジルも笑顔を返した。
「お陰様で助かりました。私はレシフェ、妻はジルと言います」
サマエルが軽く
「俺は、すぐそこで喫茶店を開いてる、テスってもんだがね。
シエンヌがここらでしょっちゅう、ああいう騒ぎを起こすもんで、迷惑してるのさ。
……まあ、彼女も、気の毒な身の上ではあるんだが。
半年前に、親父さんが事業に失敗したあげく死んで、屋敷も土地も人手に渡ってな。
心労からお袋さんも倒れちまって……」
「それで恋人にも捨てられちゃったの? 可哀想……」
ジルが気の毒そうに口を挟むと、テスは否定の身振りをした。
「いや。捨てられたのは、恋人の方さ」
「え?」
ジルが首をかしげたとき、女性が駆けて行った方角から、またも言い争う声が聞こえて来た。
「な、なんだ、この女、あっちへ行け!」
「──ああ、今度こそ見つけた! あなたこそ、あたしの王子様だわ!」
「な、なんなの、この人!?」
「くそっ、放せ、行けったら!」
「──放さないわ!」
それは、つい今し方の、サマエル達の騒ぎとそっくり同じようだった。
テスは、どうしようもないと言いたげに肩をすくめた。
「……あーあ、まただよ。毎日あの調子で、しかも段々酷くなってきてて、参ってるんだ。
医者を連れて来ても、シエンヌはすぐ逃げちまうし」
「ねぇ、また止めに行かなくていいの?」
声の方を気にしながらジルが訊くと、テスは額に手を当て、遠くを見た。
「リュイが来るから大丈夫だと思うんだが……おかしいな、店の子に呼びに行かせたのに」
「その、リュイというのは?」
サマエルは尋ねた。
「ああ、彼はシエンヌの恋人で……いや、元恋人って言った方がいいか。
彼女の親父さんが生きてたら、今頃二人は結婚して、リュイも絵の勉強を続けられるはずだったんだがね……」
「絵描きさんなの、その人。でも、貧乏になったからって別れなくてもいいのに」
「彼女がああならなきゃ、一緒になれたんだろうが……ああ、リュイが来た。
もう俺の出る幕じゃない。すまんが、お二人さん、俺は店に戻らなくちゃならん。
時間があったら俺の店にも来てくれよ、お茶の一杯もご馳走するから。
ここらで『テスの店』って聞きゃ分かる」
そう言うと、テスは二人に背を向け、雑踏に紛れて行ってしまった。
「ねぇ、シエンヌを助けに行きましょ」
ジルはそう言い、サマエルの腕を取った。
だが彼は、いかにも気乗りしないという顔をした。
「ジル……」
“ね、サマエル、お願い! 一生のお願いよ!”
ジルは念話を使って、夫に本名で呼びかけ、顔の前で手を合わせた。
妻にそこまで懇願されては、サマエルも折れるしかなかった。
「……分かったよ、行こう。でも、これは彼らの問題だ。
私達が行っても、どうもできないかもしれないよ」
「でも、放っておけないの」
ジルは真剣な眼差しで、彼を見上げた。
サマエルは、かすかに眉を寄せた。
「……何か引っ掛かるのかい?」
「うん。よく分からないけど、このままにしちゃいけない気がして……」
「キミがそう言うなんて、よほどのことだね。
分かった。行ってみよう」
二人は、声の方へ向かった。