自室のソファに座ったジルのあどけない顔を、タナトスは無言で凝視する。
「……あたしの顔に何かついてる?」
少女は頬をこすった。
「いや、何もついてはおらん。それよりジル、話を聞いてくれ」
「なあに?」
「……その、つまりだな、ジル。やはり俺と……このまま魔界に残って俺の妃に……」
「それは駄目」
間髪を入れずに、ジルは言ってのける。
「──どうして、俺では駄目なのだ!」
タナトスは感情を抑えられず、力任せにテープルをたたいた。
少女は眼を伏せ、指を固く組み合わせた。
「……ご免なさい、タナトス。
聞いて。あたし、本当はもう死んでるの。疫病に
「……何? それはどういう意味だ?」
あっけに取られ、タナトスは訊き返す。
「あのとき……病気で動けなくなっちゃったときね。
苦しくて、気が遠くなって……もう死んじゃうんだなって思った……そしたら、目の前にね、すごくきれいな女の人が現れたのよ。
『あなたは誰? 女神様?』って聞いたら、『いいえ、わたしは死神です。ジル、あなたを迎えに来ました。
でも、生き返る方法が一つだけあります。わたしの息子と結ばれることです』って言うの。
あたしが、『別に生き返らなくていいわ』って答えたら、急に女の人は泣き出して。
『お願いよ。あなたが唯一の希望なの。息子と結婚して。あなたと息子の間に生まれる子供達だけが、わたしの犯した
あたし、可愛そうになっちゃって。『いいわ、いっぱい赤ちゃん産んであげる』って言っちゃった……。
そしたら、女の人は『息子はすぐ分かるわ。わたしにそっくりだから』って、にっこりしたわ。
……けどね、最近まですっかり忘れちゃってたの、そのこと。
でも、この間、夢飛行でアイシスさんに会って思い出したのよ、全部」
「い、一度死んだキミを、母上が
そんなこと……」
でたらめだ、と言おうとして、タナトスは口ごもった。
ジルは、平気で嘘をつけるような娘ではない。
その上、こんな手の込んだ話をでっち上げ、語って聞かせるほどの芝居っ気もなかった。
(サマエルならともかくな)
タナトスは深く息をつき、気分を落ち着かせた。
「……そうだったのか。ふ、母上はやはり、俺のことなど眼中にないと見える。
しかし、歪んだ未来……キミの子供が戻す……? 母上の過ちとは何なのだろう」
「分かんない。でも、アイシスさんは、タナトスのことも忘れてないよ。
だって、『もし私の息子達がそれを知ったら、わたしを許してはくれないわ。
ルキフェルはもちろん、サタナエルも、母とさえ呼んでくれなくなるでしょう』って言ってたもの」
タナトスは、思わず息を呑んだ。
彼には、思い当たる節があったのだ。
(ま、まさか。宮中に
……ずっと、幼い頃のサマエルが魔法を使えなかったせいで流れた風評だと思っていた……。
それゆえ、親父は、ヤツをまったく
──い、いや、違う。母上が浮気などするはずがない!)
タナトスは、心の中で激しく否定した。
両親は仲
母はいつも、少女のように頬を染めて父を見ていたし、不貞を働くなど理由などない。
(……では、なぜ、父親の違う子供など?)
彼は、身ごもるのは合意の上とは限らない、ということに思い至った。
考えてみれば、いくら魔力が強いと言っても母は人間、そして周囲はインキュバスばかりだった。
父の不在の折に力尽くで、あるいは何か母の弱みを握って、強要したということも考えられた。
(……今、俺がしようとしているようにか……)
第一王子は唇を噛み、頭を振った。
となれば、サマエルの本当の父親は誰なのだろう。
何はともあれ、弟が王家の血を引いているのは確実だった。
さもなくば、“焔の眸”が認めるわけがない。
しかし、どういう経緯にせよ、王妃と情交を結ぶ度胸のある男が汎魔殿にいるのだろうか。
プロケルを始め、家臣達の顔を彼は思い浮かべた。
皆、一様に堅物で、そんなことを仕出かしそうにはない。
(……となると、残るのは……ま、まさか、ベルフェゴール……あの人豚が!?
一応、あれでも王兄だ。
“焔の眸”も文句は言えん、ごたごたを避けるために口をつぐんでいるとしたら……)
タナトスが、自分の思考に没頭していた時。
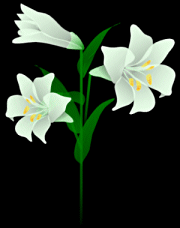
「どうしたの? タナトス。黙っちゃって」
ジルが声をかけた。
「い、いや……」
彼は言葉を濁した。
こんな話を聞かせる気にはなれなかったのだ。
「あ、それからね、アイシスさんはこうも言ってたわ。
『でも、気をつけて。一度死んだあなたは、息子から離れては生きられない。
これからは、息子の“気”をもらって生きることになるのよ』って。
だから、タナトスじゃ駄目なの、ご免なさい」
「……むう……それで、サマエルから引き離すとキミは弱ってしまうと……?」
「うん、そう。でもね、タナトス。一緒にいるのは無理だけど、赤ちゃんならあげられるわよ」
「な……っ、何……」
予想外な言葉に、タナトスは一瞬絶句し、それから尋ねた。
「……き、キミは、どうやったら子供ができるのか、知っているのか!?」
「うん」
少女は、こっくりとうなずく。
「お父さんとお母さんが、一緒のお布団で寝ると子供ができるって、前にお母さんが言ってたわ」
「そ、それはたしかに……だが、それだけでは駄目だ。ベッドの中で、その……男と女が……」
「え? そうなの?」
ジルはきょとんとし、明らかに何も知らない様子だった。
(──ち、親は何をやって……)
舌打ちした彼は、ジルの親が、すでに死亡していることを思い出した。
それでも、他の人間と住んでいれば見聞きする機会もあったかも知れないが、彼女の村だけでなく、近隣の共同体はすべて、流行病のために崩壊してしまっていた。
彼女が知っているのは、十歳以前に教えられたことだけだろう。
「でも、一人だけね。お師匠様には、たっくさん赤ちゃんを産んであげなくちゃいけないから。
その子にはあなたのこと、いい人だって教えてあげる。すごく優しいのよって」
ジルは、屈託のない笑みを彼に向けて来る。
(──くっ、“いい人”がこんなことをするものか!)
タナトスは拳を握り締めた。
「ねえ、これから寝室に行けばいいの?」
さらに意外な言葉が、その唇から発せられ、タナトスはぎょっとして彼女を見た。
「ジル……!?」
「だって、タナトス、さっきからそっち見て、そわそわしてるんだもの」
「……い、今でなくていい。夕食の後でだ」
彼は慌てて言った。
「そう。でも必ず、明日にはお師匠様のところへ帰してね」
「あ、ああ。それは約束する」
「……よかった」
少女は胸をなで下ろした。
「それだけが心配だったの。タナトスが、帰してくれなかったらどうしようって」
魔族の王子の中で、情けない思いが膨らんでいく。
この、新妻と呼ぶにはあまりに何も知らず
しかし、それでも……。心を手に入れられないのなら、せめて……。
彼は少女に手を伸ばすことを、どうしても止められなかった。
「ジル……済まない。俺が憎いだろうな……」
タナトスは、そっと彼女の手を取り、甲に口づける。
ジルは眼を丸くした。
「……どうして? タナトスはあたしのことを好きで、だから一緒にいたいと思ったんでしょう?
そんな人を、どうして憎いと思わなくちゃいけないの?」
小首をかしげる少女の邪気のない瞳を、苛立たしげに王子は睨みつけた。
「くッ……俺はキミを、せっかく結婚した夫から無理矢理引き離して、汚そうとしている男なのだぞ!」
「だって、タナトスは淋しいんでしょう。
お師匠様……たった一人の弟を、あたしが取っちゃうし、もうすぐ人界と魔界は行き来が出来なくなって、一人ぼっちになっちゃう……どうしたらいいか、ずっと考えてたの……」
ジルは申し訳なさそうに言った。
両親を筆頭に、ほぼ全部の親族を幼くして失ってしまった少女には、血を分けた兄弟と引き離されるということが、何より辛いことに思えているのだろう。
「ジル、キミは……そこまで俺のことを……。
だが、俺には、忌々しいが親父もいるし、叔母上もいる。別に、サマエルごときと会えんでも……」
「赤ちゃんてね、とっても可愛いのよ。あたしの弟は、やっと三歳になったばっかりで死んじゃったけど。
あたしもお母さんのお手伝いをして、オムツ替えたりミルクあげたりしたの。
タナトスもきっと気に入るわ。可愛がってあげてね」
「……しかし、サマエルは……」
「お師匠様は喜んでくれるわ。タナトスが一人ぼっちにならないって」
「──くっ!」
「いや、きっとあいつは腹を立てるぞ。そしてキミに離婚を言い渡すかも知れん」
「ええっ!?」
少女は顔色を変えた。
「そうだろう、魔族と違い、人族は一夫一婦制と聞く。
妻が他の男の子を身ごもったりしたら、浮気をしたということだ、離縁されても仕方ない」
ジルは息を呑んだ。栗色の眼に涙がにじむ。
「……あたし、お師匠様に嫌われちゃうの?」
「追い出されたら魔界に来るがいい、俺の“気”でキミを生かしてみせる」
タナトスが言っても、彼女は否定の身振りをした。
「……ううん、行かない。魔法で姿を隠して、お屋敷のそばに見えないお家を作って住むわ。
魔法が使えないお師匠様には、分からないと思うから。
そして、使い魔のタィフィンに頼んで、こっそりキッチンでご飯を作ってあげるの。
……お師匠様があたしに気づかなくてもいい、ずっとそばにいられれば、それだけで……。
──わあん!」
ジルは顔を覆った。
少女の涙に、魔族の王子の心は激しくかき乱された。
「だ、大丈夫だ。お前の赤ん坊も産んでやるとサマエルに言えばいい。
そうすれば、あいつも離婚を言い出しはしないさ、な?」
懸命に慰めてみても、彼女はいやいやと首を振り、泣き止まない。
腹立たしくなった彼は、乱暴に少女の腕をつかんだ。
「もう泣くな、ジル! 泣くなというのに!」
刹那、初めてジルに会った時のことを、彼は思い出した。
弟の悪口を並べ立てて彼女の怒りを買い、びんたを食らったときのことを。
あの時は、怒りに任せて彼女の手をつかみ、弟に止められたのだった。
(……俺はまた、同じ事を……)
彼が唇を噛んだとき、ジルが顔を上げた。
怯えた表情、体も小刻みに震えている。
それを見た瞬間、タナトスの脳裏に、遥か昔の情景が浮かび上がって来た。
生まれて初めて、彼が殺してしまった、少女の顔が。