回廊に出ると、ジルは尋ねた。
「ねえ、これからどこに行くの?」
取り立てて何も予定していなかったタナトスは、一瞬考え、答えた。
「……そうだな、まずは、俺の部屋でお茶でも飲もうか」
「そうね」
その後は無言で歩き、ほどなく二人は、タナトスの部屋に着いた。
以前、帰還パーティの折にも、タナトスはジルをここに連れて来たことがある。
サマエルの部屋の
「そこに座ってくれ」
「うん」
足首まで埋まりそうな毛足の長い
「ミルクティーでいいか?」
「うん」
タナトスは空中からポットを取り出すと、金で縁取られ、優雅に遊ぶ貴族の絵柄がついたティーカップに手ずから熱い紅茶を
「そら」
「ありがと」
カップに角砂糖を三つ入れ、口に運ぶジルの顔を見ながら、彼は話題に
ちらりと寝室の方をうかがうものの、まだ昼にすらなっていない。
もし、ベッドに連れ込むにしても、こんな時間から相手をさせたりしたら、彼女がサキュバスだとしても体が持たないことは明白だった。
それに、一緒に歩いていて気づいたのだが、サマエルはまだ、まったくジルに手をつけていない。
インキュバスは、匂いで女性の状態が分かるのだ。
彼はあきれると同時に腹が立ち、顔をしかめた。
(……くそ、あれから三月は経っているだろうに、どうして仕込んでおかんのだ!
つまり、ベッドで俺が彼女に、一から十まで教えてやらねばならん……ということか?
まったく面倒な……!)
「ね、それで、タナトスは、これからどうしたいの……?」
そのとき、ぽつりとジルが聞いた。
「あ、ああ……ベッドで俺がキミに、いや、その……」
不意を突かれたタナトスは危うく、思っているところをそのまま口にするところだった。
ジルは栗色の眼を見開いた。
「……え? ベッドで何?」
「い、いや、そうではなくて、俺は……その、キミを食べたい……と思う気持ちを抑えられんのだ。
分かるか、ジル。俺は夢魔だ、だから女性の……」
「あたしを食べたいの?」
けげんそうな顔をしたジルは、すぐにうなずいた。
「ああ、お腹が空いてるのね?
この頃、あんまり食べてなかったんでしょ、イシュタルさんもそう言ってたもの」
少女の勘違いに、タナトスは困惑した。
「ち、違う、そうではなく……いや、空腹なことは空腹なのだが」
「そうよね、お腹空いてると元気も出ないもんね。
そうだ、じゃあ、あたしが今からおいしいご飯、作ってあげるから!」
「えっ!? 違う、俺が言いたいのは、……」
「ねえ、キッチンはどこ?
デザートも作ってあげる。何がいい?
あ、タナトスは、チョコレートケーキが好きだったわよね?」
眼をくるくるさせて言う少女の楽しげな様子に、それ以上否定する気力を、タナトスは無くしてしまった。
「……キミの手料理か。そう言えば、しばらく食っていなかったな」
彼は、ジルのケーキを最初に食べたときのことを思い出していた。
見た目はお世辞にも上手だとは言えなかったが、味の方はなかなか美味だった。
「あ、でも、チョコレートがないかしら……」
「心配いらん、常時用意させている。
以前、城のシェフに、キミのレシピ通り作らせてみたのだが、やはり同じようにはならんものだな。
キミに作ってもらった方がうまかったよ」
「ホント? じゃあ、腕によりをかけて、もっと、もぉっとおいしくするからね!」
ジルは大きな瞳を輝かせた。
(……まあいいか。
ベッドで過ごすにしろ、精気を吸うにしろ、おそらく彼女は気を失ってしまうだろうしな。
反応がないのは詰まらん。
せっかくの機会だ、それこそ恋人同士のように、楽しく過ごすのも悪くはない)
そう考えたタナトスは、彼女を
「ここだ」
「あれれ、どっかで見たような……?」
ジルは小首をかしげた。
扉を開けると現れた、こじんまりしたキッチンは、サマエルの屋敷にあるのものと瓜二つだったのだ。
「キミが……俺を選んでくれたら、ここを使ってもらおうと思っていた。
……ホームシックにならんようにな。城の料理番用の大きなキッチンは、隣にある」
「あ、エプロンもあるわ、可愛い!」
タナトスの説明など、ろくに耳に入っていない様子で、少女はエプロンを身につけ始めていた。
「えっと、何作ろうかな。そうだ、ウサギのシチュー……うーん、でもあれって長く煮込まなくちゃいけないのよねぇ。
──あ、そっか、先に作っておいて、晩ご飯にすればいいのよ!
ねえ、タナトス、ウサギさんのお肉ある?」
ジルは振り返った。
「……肉ならそこだ、サマエルの台所と同じところにある。
だが、ジル……」
「何? タナトス。
──あ、そっか、ご免なさい、お腹空いてたのよね。じゃ、まずお昼を先に作らなきゃ。
そうね、オムレツでどうかしら?」
「……あ、ああ、構わんが」
「すぐ作るから、そっちで座って待っててね。
えっと、卵はここかな……あった!
わあ、大きいのねぇ、これ!」
握りこぶしほどもある薄茶色の卵に、ジルは驚きの声を上げる。
「ジル、その……」
「あとは、バターね、ここかしら?」
まったく取り合ってもらえないタナトスは、話の接ぎ穂を失い、
「まあ、パンもあるのね、しかも焼き立てのほっかほか!
これと一緒にオムレツ食べたら、最高だわ!」
「ああ、パンも常備させているが……いい匂いだな」
それでも、フライパンがじゅうじゅう音を立て、同時によだれの出そうな匂いが漂い始めると、徐々にタナトスは気力を取り戻した。
「そうでしょう? すぐできるからね!」
答える間にも、ジルは手を休めない。
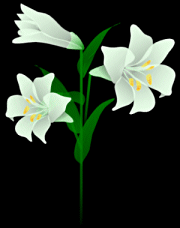
「お待ちどうさま、はい、どうぞ」
やがて目の前に置かれた大きなオムレツからは、盛んに湯気が出ていた。
バターの濃厚な香りが、食欲をそそる。
「おお、これはうまそうだ! 頂くぞ!」
王子は落ち込んでいたことも忘れ、ナイフとフォークを手に、出来立ての料理に挑みかかった。
「うん、たくさん食べてね」
「お代わり!」
あっという間に平らげて、まだシチューを作り続けている少女に向かって、皿を突き出す。
「はいはい」
笑顔でジルはそれを受け取り、また卵を割る。
それを何度か繰り返し、あとは煮込むだけというところまでシチューが出来上がった頃、タナトスはようやく満腹になった。
「うむ、うまかったぞ、ジル」
「そう? タナトスがすごくおいしそうに食べてくれるから、あたしもお腹が減っちゃった!」
ジルはうれしそうに言い、卵を溶いて手早くオムレツを作り、満足げなタナトスの向かいに座った。
「あ、でも、シチューをかき混ぜてなきゃ、焦げちゃうかな」
「それなら、料理専用の使い魔にやらせよう」
タナトスは指を鳴らし、使い魔を呼び出した。
「お呼びですか、ご主人様」
「使い魔さん、お名前は?」
現れた緑色の小人に、ジルは声をかけた。
「ジャーマラです、ご主人様」
「そう、ジャーマラ。このシチューが焦げないように、ずっとかき混ぜててくれる?
晩ご飯のときに、あなたにも分けてあげるから、頑張ってね」
「はい、ちゃんとやります、はい、お任せ下さい、ご主人様」
小人はうれしそうに幾度もお辞儀をし、尻尾を振りながら、少女からお玉を受け取った。
「こんな奴にもくれてやるのか」
タナトスが、コンロの前に陣取る小人に不服そうな視線を送ると、ジルは言った。
「ちゃんと後でもらえると思えば、つまみ食いもしないし、絶対さぼったりしないわよ。
だって、焦げちゃったりしたら、自分もおいしいの、食べられないんだものね」
「……なるほど。失敗した後で仕置きするよりも、何倍も効果的な気がするな」
「そうでしょ? お母さんが教えてくれたの」
少女はにっこりした。
「──さてと、あとは、ケーキね」
「俺も手伝ってやる」
「うん、ありがと」
さっさと料理を終わらせなければ、ジルとまともに話もできないということに、ようやく気づいたタナトスは、遅まきながら助力を申し出たのだった。
「でも、こうしてると、イナンナと再会したばっかりの頃を思い出すわね」
「……そうだな。大人になってから、俺が料理を作ったのはあの時が初めてだったが」
ジルはくすくす笑った。
「いやだぁ、タナトス。あの時は、ただ葉っぱを取ってただけなじゃないの」
「そうだったか? だが、その後でも、幾度か手伝ったろう」
「……えーっ、そうだったぁ?」
決して美人ではないものの、うまい食事を作ってくれる少女と何気ない会話をかわし、笑い合う。
タナトスにはそれが、何ものにもかえがたい宝物のように思え、さらにジルが欲しくなった。
だが、手に入れることはできない。
彼女の心は、決して自分のものとはならない……のだから。
たとえ、憎い弟を殺したとしても。
(……つまらんことを考えるのはやめろ。今は、ジルと楽しく過ごせさえすればそれでいい)
タナトスは頭を振り、暗い気分を追い払った。
「これでよし、と。後は焼くだけね」
そうこうしているうち、ジルがケーキの種をオーブンに入れ、完成を待つだけになった。
「ジル、後は使い魔に任せて、俺の部屋で一休みしないか」
タナトスは、椅子に座って一息ついている少女を誘った。
「そうね。ジャーマラ、ケーキが焼けたら、冷めるまでそのままにしておいて。
晩ご飯のときに、あなたにも一つあげるからね」
「はい、ご主人様、ありがとうございます。お任せ下さいませ」
深々と頭を下げる小人に見送られ、二人は再び、タナトスの自室に向かった。
悄然しょうぜん
元気がなく、うちしおれているさま。しょんぼり。