「“今から明日の朝まで、ジルを借り受ける”、というのはどうだ、我が弟よ?
その間、“俺は彼女に何をしてもいい”と」
冷酷な笑みと共に、タナトスは言い放った。
さすがに今度は、サマエルの顔色も変わる。
「な、何を言うのだ、タナトス! いくら何でも無体だぞっ、そんなことが許されるはずがないだろう!」
「何だ、その言い草は。兄と呼べ、と言ったろうが!
ただでさえ、貴様を、この場でぼろ雑巾のごとく引き裂き、ジルを力ずくで奪い取りたくて、気が狂いそうになっているのだ!
それを、我慢してやっているというのに!」
「あ、兄上、お許し下さい、そんなことはできません、できるわけがないでしょう……!
私はどうされても構いません、ですが、ジルはお渡しできませんよ!」
急ぎ言い直した弟王子の声には、どうにも抑えられない動揺が現れていた。
「ふん、貴様の取り乱した顔を見るのも久しぶりだな、実に気分がいい。
嫌なら嫌で、別に俺は構わんぞ。
その代わり、かつて同様、人界を、ゴミくずのようになるまで破壊し尽くし、二度と復活などできんよう、人間どもを根絶やしにしてくれる!」
鼻息も荒く、タナトスは言ってのける。
それは単なるこけおどしではなく、タナトスは昔、本当に人間を滅ぼしかけたことがあった。
今から一万二千年前……“黯黒の眸”が盗み出された(と当初は思われていた)ために起きた人界と魔界との戦争で、ベルゼブルとタナトスが人界の大陸のうち二つを破壊し、運良く生き残った小数の人間達が、原始時代からやり直したのだった。
最悪の事態に陥ってしまった。
サマエルは、奈落の底に落ちていくような思いを味わっていた。
自分一人ならば、タナトスにどんなことをされてもいい……というよりも、その覚悟でここに来たのだ。
だが、
第一、男性経験もない
発狂か、最もひどい場合には、ショック死の可能性さえある。
タナトスを心から受け入れることができれば、そうはならないかも知れないが、サキュバスでもないジルに、そんな芸当ができるわけもない。
彼女は、兄ではなく、自分を夫に選んだのだから。
無論、第二形態に
さらに、そのまま兄を殺すことも可能だと彼には分かっていたが、醜い大蛇の姿など、二度とジルには見られたくはなかったし、もう兄とも争いたくはなかった。
タナトスが死ねば、次の魔界王のなり手がなくなってしまう。
王が空位の間に、神族に攻められでもしたら、今度こそ、魔族は滅んでしまうかもしれないのだ……。
いずれにせよ、選択の余地がない状況であり、あとは嘆願するしか、サマエルには
彼はうなだれ、口を開いた。
「お許し下さい、兄上。そんな条件は飲めません……。
……それにこの場で私を殺しても、彼女はあなたに従いませんよ。
どうか、お考え直しを……」
「たわけ、それくらいのことが分からんでどうする!
彼女は、俺を憎んだあげく自害するか、それとも、食事もとらずに弱り果てるか、どちらにせよ結局、お前の後を追って
──だからこそ、俺は、こうして冷静さをかき集め、貴様と対峙しているのだろうがっ!」
タナトスは、荒々しく弟王子に指を突きつけた。
すると、それまで、ただ黙って成り行きを見守っていたジルが、口を開いた。
「分かったわ、タナトス。その条件、飲みます。明日の朝まででいいんでしょう?」
「ジ、ジル……!?」
サマエルは驚愕して妻を見つめた。
「いいの、お師匠様。あたしの……あたし達のために、また人界を破滅させちゃうわけにはいかないでしょ。
たくさん人が死んじゃう……そんなの嫌。もう人が死ぬところなんて見たくないの。
だから、お願い。我慢して」
「私のことよりキミが……」
「心配か? 大丈夫だ、手荒なことはせん……と言ってやりたいところだがな、我が弟よ。
俺は貴様と違い、感情の赴くまま、好き勝手に振る舞うぞ。
こんな俺にジルを一晩預けたら……どうなると思う?
くっくっく……」
タナトスは、弟を焦らすのを心から楽しんでいるように、嫌な笑い方をする。
「くっ……!」
サマエルは歯を食いしばった。
「ともかく、ジル本人がいいと言っているのだからな。彼女を借り受けるぞ、サマエル。
おっと、その前に、貴様の魔力を封じてやるんだったな!」
「そ、それは……明日、あたしが戻ってからにして……」
震え声で哀願するジルの言葉にも、タナトスは聞く耳を持たず言い立てた。
「いいや、今すぐだ! こいつに、想いの
「そんな……」
ジルの茶色の眼が、潤んでいく。
「ジル……済まない、私が不甲斐ないばかりに、キミをこんな目に遭わせてしまうことになるなんて……」
握り締めたサマエルの拳は、どうしようもなく震えていた。
そんな彼らの様子を満足げに見ながら、タナトスは言った。
「さてと、こうしてる間にも時が移る。さっさと片づけるとするか。
「……はい、兄上……」
サマエルはしようことなく、ひざをつく。
タナトスがあごに手をかけ、顔を少し上向かせたとき、彼は言った。
「一つだけ、お願いがあります。お聞き届け頂けませんでしょうか、兄上……」
「ふん、今さら何だ?」
「……彼女を……ジルを、優しく扱ってやって下さい、彼女は人族の女性です、魔族と同じようには……」
「──黙れ!」
いきなりタナトスは、彼の頬を張った。
「やめて、タナトス! お師匠様をぶったりしないで!」
ジルが第一王子の腕に取りすがる。
「貴様ごときに下知されるいわれなどない、俺は俺の好きなようにやる!
……ジル、もう乱暴はせん、どいてくれ」
少女を押しのけて、タナトスは続けた。
「──さあ、サマエル、覚悟はいいな? 眼は閉じるなよ」
兄王子が顔を近づけてくると、持って行き場のない思いがあふれ、サマエルは、自分の眼に苦しげな影がよぎるに任せた。
タナトスは、またも歪んだ笑みを唇に刻んだ。
「ふん、いつもやけに冷静な貴様の、そんな動揺した様を見るのは実に愉快だな。
ではいくぞ!
──偉大なる魔界の王バアル・ゼブルの息子、“闇の貴公子”サタナエルの名において、ここなる者……“カオスの貴公子”ルキフェルの、刻を飛翔する力、闇を
──シック トランシット グロリア ムーンダイ……ラーブルム・インノケンティア」
呪文の最後の部分は口の中に消え、誰にも聞こえはしなかった。
唱え終えたタナトスは、弟王子に口づけた。
途端に大きな音を立て、部屋の隅に立てかけてあったサマエルの魔法の杖が、砕け散った。
「ふん、杖も、主の力の消滅を感じ取ったとみえる。
──ちっ、この呪文の難点は、相手と唇を合わせねばならん所だが……」
タナトスは、さも不快そうに袖口でごしごしと唇をぬぐった。
「ふふん、どうだ、魔力をなくした気分は? 子供の頃を思い出して懐かしいか?
あの頃の哀れな貴様に再び戻り、これからは生涯、魔力のない者として地べたを
では、行こう、ジル。
サマエル、貴様はここで、俺がジルに何をしているか想像しながら待っているがいい……くっくっく」
第一王子は、勝ち誇った表情で長いマントを跳ね上げ、眼を潤ませている栗毛の少女を包み込み、かすかに震える細い肩を抱いて部屋を後にしようとした。
ジルは大人しく従ったものの、ドアのところまで来ると、思わず夫を振り返った。
サマエルははっとして立ち上がり、手を伸ばして妻を引き止めたいような素振りを一瞬見せたが、彼女が首を横に振ると、力なくその手を下ろした。
二人の後ろでドアが閉まり、一人取り残されたサマエルは唇をぐっと噛みしめて、ドアを凝視し続けていた。
魔力を封じられる以前の彼なら、水晶球を通して彼らの行動を見守ることもできただろう。
だが、今はもう何もできずにただ、立ち尽くすだけだった。
もちろん、魔力を封じられる前に勇を
しかし、サマエルには分かっていたのだ。
陰謀を暴くためとはいえ、父と兄を手にかけたとき……鋭い剣の切っ先が肉を切り裂きながら、脈打つ心臓にまで達し、その鼓動を止めさせる瞬間、吐き気を催す嫌悪感と同時に訪れたのは、表現の仕様もないほどのエクスタシーだった……。
他人の生命を支配し、おのれの手で死を与えることで得られる
そうすれば、守ろうとした少女をも結局、亡き者としてしまうことになるのだ。
(……私は……親兄弟を手にかけることにさえ、喜びを感じてしまう化け物……愛する者を守ることもできず、いや、それどころか……殺してしまうかも知れない……。
どうして、生まれてきてしまったのだろう……)
彼はつぶやいた。
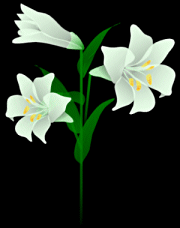
闇が徐々に濃くなりまさり、部屋も暗闇に沈んでいく。
だがサマエルは、生きたまま石像にされたという伝説の人間のように微動だにせず、