戦略を練ることに
「お師匠様?」
「大丈夫だよ、ジル。タナトスに声をかけるから、ちょっと待っておいで」
サマエルは、不安げな新妻に微笑みかけると、兄に念話を送った。
“タナトス。大事な話がある、城に入ってもいいか?
実は、もう黔龍城の中庭まで来ている……ジルも一緒だ”
“き、貴様っ、どの面下げて……今さら、話だと!? ふざけるなっ!”
歯
やはりと思いつつも、なだめるようにサマエルは続けた。
“落ち着け、タナトス。
ジルが選んだことだ。彼女の意思を尊重することに、お前も同意しただろう?”
“うるさい、この、人殺しの泥棒猫めがっ!”
“待って。ともかく、お城に入れてくれない?
ね、タナトス? あたし、あなたに会ってお話したいの”
ジルが話に割り込むと、タナトスは一瞬黙り込み、それから言った。
“……応接間に来てくれ。そこで話そう”
“分かったわ”
「……やっぱりタナトス、すごく怒ってたわね、お師匠様」
ジルは心配そうに、サマエルを見上げた。
「そうだねぇ。ともかく、キミがいてくれてよかったよ、ジル」
(どうやら、私を痛めつければそれで気が済む、といった次元を超えてしまっているようだな、今度という今度は……。
まあ、こんな死に損ないに女性を取られたとあっては、プライドが許さないのだろうが)
サマエルは
「でも、お師匠様……この前来たときとは、全然感じが違うみたい……何だか怖いわ」
黔龍城の中を進むに連れ、ジルは徐々に元気を失い、しまいには、怯えたようにサマエルにしがみついた。
それもそのはず、以前パーティが開かれた時には明るく爽やかに感じられた城の中が、今は薄暗く
「魔族の住居はね、主の意思を反映してしまうのだよ。
あいつが激怒しているから、こんな……入って来る者を拒むような風になってしまっているのだろうね……」
「……そうなんだ。でも、なんか、怒ってるというより、悲しそうなカンジよ。
まるで、このお城、泣いてるみたい……」
そう話すジル自身も、悲しげな顔をしている。
サマエルは心底驚き、非常に珍しいことだったが、声も上ずった。
「な、泣いている!? あの、自信過剰のタナトスが!?」
「うん……」
「悔し泣きか? ……まったく、子供の頃から進歩がないな……」
ため息混じりに彼がつぶやくと、ジルは首を横に振った。
「違うよ。淋しくて、悲しくて、一人ぼっちだと思って泣いてるの」
「悲しい……一人ぼっち? まさか、あいつが」
サマエルは絶句した。
「でもねぇ、お師匠様。
タナトスは、自分がそんな風に感じてるってこと、分かってないよ。きっと」
「……ふうむ。
悲しみを表現する代わりに、怒ってしまう者がいる、とは聞いたことがあるけれど……」
第二王子は当惑していた。
普通ならば、年齢と共に精神の方も育ってしかるべきだというのに、兄王子の感情は、幼少の頃からほとんど成長していないように感じられる。
ジルは、小鳥のように小首をかしげた。
「……タナトスも、悪いヒトじゃないんだけどねぇ……」
「そう……だろうか」
「うん、そうよ」
彼女は真面目な顔でうなずく。
ともかくも気を取り直し、彼は言った。
「それはさて置き、あいつには下手に出た方がいいだろうね。
今までの経験上、説教めいたことを言うのも逆効果だと思う。
改めて私達の結婚の許可をもらいに来た、と言うのが一番無難だと思うけれど……」
「そうね。それしかない……かもね」
同意する妻の表情には、どこか思い詰めたものがあった。
しかし、タナトスをどう説き伏せるかで頭が一杯だったサマエルは、それには気づかなかった。
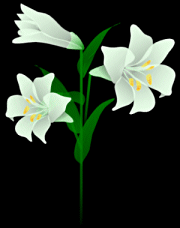
不気味な回廊をいくつも抜け、彼らはついに応接室に着いた。
「……来ちゃったね」
「そうだね……」
二人は顔を見合わせた後、一呼吸置いてサマエルが、大きな一枚板で作られた豪華なドアをノックする。
返事はなかった。
「まだ、来てないのかな……」
「そのようだ。ともかく、中に入ろう」
彼らはドアを開け、広い室内へと足を踏み入れた。
黔龍城の応接間は、例えようもないほど
「……やっぱり来てないね、タナトス」
「心を決めかねているのだろう……私達をどう扱うか。
あいつが来るまで、時間がかかるかも知れない。座って待とう」
サマエルの言葉に、ジルは首を横に振った。
「ううん。あたし、立ってた方がいい」
「そうか。では、お茶でも……」
言いかけた時、乱暴にドアが開き、タナトスがずかずかと入室して来た。
「あ、タナトス……」
「聞いてくれ、タナトス。私達は、改めて結婚の許可をもらいに来た」
先手を打ってサマエルが言うと、第一王子は二人をぎろりと見た。
「……結婚の許可だとぉ?」
頬がこけて顔の輪郭が細くなり、いつにも増してタナトスの目つきは鋭くなっている。
「そうだ。お互いに納得出来ていないと、後々まで尾を引きそうだからね」
「そうよ。だってあたし、二人には、これ以上仲悪くなって欲しくないから」
「ふん……」
あうんの呼吸で話し出す弟夫婦を見据える兄王子の瞳には、以前にはなかった暗い影がたゆたっている。
ややあって、タナトスは、気を落ち着かせるかのように眼をつぶり、大きく息をした。
「……それほどに、俺の許しを得たいと言うのであれば、三つ、条件がある」
「条件……?」
意外に冷静な兄の態度に幾分安堵して、サマエルは尋ねた。
「そうだ、それを飲む気があるなら、考えてやってもいいぞ」
「言ってくれ、タナトス」
「そうだな……まず一つ目は……」
サマエルとジルは息をつめて、第一王子の次の言葉を待ち受けた。
タナトスは眼を開け、言った。
「サマエル、貴様が、オレを“兄”と呼ぶことだ。
いつまでも“お前”呼ばわりや呼び捨ては、腹立たしい限りだからな」
ほっと二人は肩の力を抜き、サマエルは片ひざをついて、身分の高い相手に対する正式な礼をする。
「しかと
……して、次なる条件とは、いかなるものでございましょうか」
その弟を満足気に見下ろして、タナトスは続けた。
「二つ目は、貴様の魔力を封じることだ! 永久にな……!」
「ええっ! そ──そんな、ひどい!」
過酷な条件を聞いても、サマエルは表情一つ変えなかったが、ジルは真っ青になった。
「そう、キミに何かあってももう、ヤツは助けることは出来ない。
それどころか、自分の身を守ることすら、
神族どもに捕らえられ、幽閉でも処刑でも、されてしまうがいいのだ!
あーはっはっは──!」
タナトスは高笑いをした。
「お願い、それだけは……! 考え直して、タナトス……」
必死に頼み込もうとする新妻を、サマエルはさえぎった。
「ジル、それでいいよ。
キミと結ばれることが出来るのなら、私は、魔力のない普通の男として生きよう」
「お、お師匠様……」
ジルの瞳が
「よく言ったな、我が弟よ。いい覚悟だ。
だがそれは無理と言うものだぞ、よっく考えてみるがいい。
ジルが、人間の寿命を
それを分かった上で言っているのか?」
緋色の眼を冷たく光らせ、タナトスは尋ねた。
「それはよく分かっています、兄上。
しかし、彼女が生きている限り一緒にいたい、それが私の願いです。
そのためなら、魔法が使えなくなっても、一向に構いません」
サマエルはきっぱりと答えた。
「だ、駄目よ、お師匠様、そんなの……あたしなんかのために……!」
うろたえるジルに、彼は優しく微笑みかけた。
「気にしなくていい、ジル。私が決めたことなのだから」
「ふん、安っぽいメロドラマだな、まるで!
まあいい、では、最後の条件を言うぞ、よく聞け!」
突き放すようなタナトスの言葉に、どきりとして二人は寄り添う。
そのまま彼らは