※この番外編は、ネタバレ要素を含みます。
<巻の三>本編を読んでいない方は、先にそちらをお読み下さい。
また、三まで読み進めていないと、話が見えないと思います(笑)。
というわけで、<巻の三>をお読み頂けましたか?
では、番外編をお楽しみ下さい。
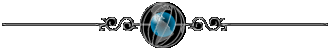
「……おや、珍しい。この気は……」
魔法陣が作動したのを感知し、サマエルは本を書棚に戻すと、屋敷の地下へと下りていった。
「サマエル、久しぶりね」
魔界へと通じる魔法陣から歩み出たのは、彼の叔母、魔界王の異母妹イシュタルだった。
「これはイシュタル叔母上。いつお会いしても、お美しい」
サマエルは少々驚きつつも、彼女の白い手に口づけて、歓迎の意を表した。
「……ですが、いかがなさったのですか?
魔族の魔界への帰還は、まだ終わっていないのでは……」
様々な障害を乗り越え、魔族の第二王子である彼とジルとが結婚式を挙げてから、三月ほどが経っていた。
天界との摩擦を避けるため、サマエルを残して魔界人はすべて魔界へ戻り、二つの世界をつなぐ通路は封鎖されることとなったが、魔族達は現在、人界のほぼ全域に生息範囲を広げていたため、そうした決定を全員に告知するのにも時間を要していた。
イシュタルは
「いいえ、違うの、次元回廊の封鎖を知らせに来たんじゃないのよ」
「では……?」
「ああ、安心してね、新婚家庭を邪魔しに来たんでもないわ」
そう答える叔母の顔色は悪く、サマエルはかすかに眉を寄せた。
「……ともかく、上へ参りませんか?」
「そうね。
「彼女は気にしないと思いますが、どうやら何か、お悩み事がおありのようにお見受けしますので……」
「さすがだわね。まずは上に行きましょ。ちょっと長い話になるから」
「はい、では……」
サマエルは叔母の手を取り、唱えた。
「──ムーヴ!」
サマエルの部屋に着くと、イシュタルは言った。
「これは、ジルにも関係があることなの。呼んでくれないかしら?」
「彼女にも? 分かりました」
彼はすぐさま、妻を呼んだ。
“ジル、私の部屋に来てくれ。イシュタル叔母上がおいでだが、何か話があるそうだ”
“うん!”
思念の返事とほぼ同時に、元気よくジルがドアを開ける。
「イシュタルさん、今日は、いらっしゃい!
……あれ、どうしたの、顔色よくないよ? 具合悪いの? どこか痛い?」
栗色の瞳をくるくるさせて、心配そうに彼女はイシュタルの顔を仰ぎ見る。
「ああ、ジル、どこも何ともないから大丈夫よ。
それより、聞いてちょうだい。
せっかくの二人暮らしを邪魔したくはなかったのだけれど……悪い知らせが二つもあって……」
イシュタルは両手をもみ絞った。
「悪い知らせ……」
「お師匠様……」
二人は思わず顔を見合わせる。
それから、サマエルは気を取り直し、叔母に視線を戻した。
「ともかく、お話し下さい、叔母上」
「……ええ。まず一つ目は、ベルフェゴールが脱獄したのよ」
「あの伯父が? 独りで、ですか?」
「ベル……フェルゴールって、一番悪いヒトよね?」
「そうよ、ジル」
イシュタルは唇を噛んだ。
「……油断したわ、透明化できるフィンズーズのことを忘れていた……。
あいつの手引きでベルフェゴールは逃亡したのだけれど、行きがけの
「えっ!」
ジルは驚いたものの、サマエルは眉一つ動かさなかった。
「フィンズーズ……伯父の使い魔ですね?」
「ええ。すぐ、二人を蘇生させて聞いてみたのだけれどね。
一緒に逃げようとした彼らを、足手まといになるからと、あの男はばっさり切り捨てたらしいわ。
今、魔界全土に手配して、行方を探させているところよ。
カルニヴェアンは、どうしてもわたしの役に立ちたいと泣きついてきてうるさかったから、探索に加えさせてやったけれど、多分もう戻っては来ないでしょうね。
ま、あんな
魔界王の異母妹は肩をすくめた。
「……なるほど。そうでしたか。
それで、もう一つのこととは? こちらの方が、深刻なのではないかと拝察致しますが」
伯父の逃亡をたった一言で片付け、サマエルは続きを促す。
イシュタルは、ため息交じりに首を振った。
「ええ、たしかにこっちの方が、遥かに困った事態かも知れないわ……」
「困った事態って、タナトスのこと?」
「ひょっとして、タナトスのことですか?」
ジルとサマエルの声が、期せずして揃った。
イシュタルは大きくうなずく。
「二人共さすがね、実はそうなのよ」
「まさか……とは思いますが、私達のことでゴネている……とか?」
「あたしに振られていじけちゃったの?」
「ええ、それで困っているのよ。
あの子ったら、すっかりすねちゃって、『俺はもう魔界王になどならん』とか言い出して。
兄上はもちろん、わたしの話にもまったく耳を貸さなくて……」
困り果てたようにイシュタルは言った。
ジルは栗色の眼を真ん丸くした。
「やっぱり。でもあきれた。まるで子供みたいね」
「本当にそう。大きななりをして、まるっきり小さな子供みたいなのよ、ジル。
……やはり
いえ、愚痴を言っている場合じゃないわね、戴冠式はもうすぐ、あと一ヵ月後に迫っているのよ。
……なのにあの子ったら、どうしても嫌だとだだをこねて……」
イシュタルは大きくため息をついた。
「それで……叔母上は、私達に、どうせよと
サマエルは尋ねた。
「……こんなことを頼むのは、とても気が引けるのだけれど、魔界に来てタナトスを説得してくれないかしら。
色々あって、魔界にもあの子にもいい感情はもっていないでしょうけれど、お願い、二人にしか頼めないのよ。
天界は
──お願い、サマエル、ジル、この通りよ、わたしを助けると思って、タナトスを説得して!」
言うなりイシュタルは片膝をつき、深々と
「お、叔母上、おやめ下さい」
「そうよ、そんなことしなくったって、あたし達、魔界に行くわ。
ね、お師匠様?」
「そうだね。そうするしかなさそうだ。
お立ち下さい、叔母上。私達はすぐにでも参りますよ」
サマエルとジルは彼女の手を取り、立ち上がらせた。
「ああ、ありがとう、二人共。このお礼は必ずするわ……」
イシュタルは感激して眼を潤ませ、彼らの手を握り締めた。
「でも、やはり急には考えもまとまらないでしょう。
タナトスをどう納得させるか、冷静に攻略法を考えてみてちょうだい。
明後日、改めて迎えに来るから、よろしくお願いね」
イシュタルが帰った後、彼らはまたも顔を見合わせた。
「……タナトスにも困ったものだね」
「もうちょっと男らしく、きっぱり諦めるかと思ってたのに。
……でも、どうやって説得すればいいのかなぁ、お師匠様」
ジルは困惑したように言った。
「……そうだねぇ」
サマエルもため息をつく。
「まあ、キミに振られて走り去るあいつの後ろ姿を見たとき、このまますんなりとは終わらないのではないか、という予感はあったよ。
ヤツも、プライドが高いからね……。
だが、単純なタナトスのことだ。あれこれ策を弄すより、真正面から堂々とぶつかった方がいいかも知れない」
「そうね……」
「……ともかく、私はもう少し考えてみるよ。
まだ日も高い、キミは気分を変えに、花畑にでも行って来たらどうかな」
「あ、そうだ、もうハーブがなかったのよね、ついでに摘んで来よっと」
「気をつけて行っておいで」
「はーい、行って来まーす!」
ジルはもう、タナトスのことなど忘れたように、元気よく駆けていく。
妻と呼ぶには未だ幼いその背中を見送り、サマエルは考えに没頭した。
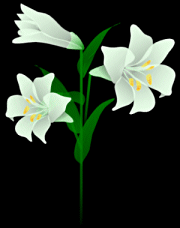
翌々日の朝、迎えに来たイシュタルと共に彼らは、まず魔界にあるサマエルの城、紅龍城へとやって来た。
一旦魔法陣から出て、サマエルは叔母に尋ねた。
「タナトスはどこに? やはり
「……ええ。あそこに引きこもってるわ。
誰彼構わず八つ当たりをするものだから、皆怖がってしまって。
この頃では、ほとんど無人状態なのよ、あの城は」
「では、最近のあいつは、ろくに食事も……?」
サマエルは眉をしかめた。
飢餓状態の夢魔……ただでさえタナトスは激しやすいというのに、それでは冷静な話し合いなど不可能だろう。
「いえ、大丈夫よ。わたしが行ってあげてるから。空腹で苛ついているなんてことはないわ」
「……そうですか。それなら、何とか」
叔母の答えに懸念は消え、最悪の事態は避けられるかもしれないと彼は思った。
「ご飯食べてないの? タナトスが? あたしのせいで……」
ジルは声を震わせた。
「大丈夫、叔母上がちゃんと食べさせているそうだから。
自分勝手なあいつに従わなかったからといって、キミが引け目に思う必要はないよ」
サマエルは優しく言った。
「そうよ、ジル。あなたのせいじゃないわ。あの子が、わがままなだけ。
生まれて初めての挫折を味わっている、といったところね。
今まで何でも思う通りになって来たから、本当なら、いい機会なのだけれど……」
イシュタルはため息をついた。
「ともかく、黔龍城へ参りましょう、叔母上」
「……ちょっと待って。サマエル、何か、いい案を思いついたの?」
「いいえ。当たって砕けろ、といった心境ですよ」
彼は浮かぬ顔で、否定の仕草をした。
「まあ……」
「私だけならともかく、ジルがいます。あいつもそう無茶なことはしない……と思うのですが」
「そうだといいけれど……」
「叔母上? どうかなさいましたか?」
黔龍城へと向かう魔法陣のすぐ手前で歩みを止めたイシュタルを、サマエルは不思議そうに見た。
「……ご免なさいね、やっぱり、わたしは行くのを遠慮した方がいいと思うのよ。
わたしが何か言うと、あの子、またへそを曲げそうな気がするから」
「分かりました、お任せ下さい、叔母上」
「ええ、お願いね、サマエル、ジル」
「頑張ってくるね~!」
ジルは無邪気に手を振って、そのまま二人は魔法陣に乗り込む。