30.魔界王家の禁秘(3)
「陛下? ……いかがされたのですかな?」
司祭アマルリクは、遅まきながら、尋常でない君主の様子に気づいて尋ねた。
「──いかがも何もないわ、まことにかような託宣が下されたと申すのか!?
左様にうろんな話、誰が
魔界王ベルゼブルは、司祭を激しくなじった。
アナテ女神の神託は
アマルリクは青くなった。
「わ、わたくしの言葉をお疑いと
ああ、情けなや、お父君の
「そなた、その神託の言わんとする意味を、真実理解しておるのか!?
サタナエルは魔族が待ち望んだ世継ぎぞ、それをあろうことか、
眼を怒らせ、ベルゼブルは老司祭に指を突きつけた。
「お静まり下さいませ、無論、陛下のご心情は察するに余りありまする。
しかしながら、お父君の御言葉を、よもやお忘れではございますまい?
魔界の君主となるからには、一命を
司祭の弁明は、魔界王の怒りを鎮めるどころか、火に油を注ぐ結果となった。
「
神託に従い王家の血を絶やすなぞ、それこそ本末転倒じゃ!
正気の沙汰とも思われぬわ!」
すると、アマルリクは居住まいを正し、真正面から君主を見た。
「ならば、
血が絶えると仰るならば、側室を持たれるべきでございましたな。
もしくは歴代の王同様、後宮にお通いあそばされるか。
そのどちらもされておらぬのに、それでも務めを果たしていると陛下は申されるのですか……?」
老司祭の口調は静かだった。
しかし、痛いところを突かれたベルゼブルは、頬を
「く、生意気な! 口を慎め、アマルリク!
司祭の分際で、君主の後宮のありように
王と妃が仲睦まじいこともあり、側近の家臣達はこれまで、表立っての批判は控えて来た。
それに反して、低い身分の者達は好き放題に噂を流していた。
後宮に通わない淫魔の王など前代未聞、妃を愛するあまりと言えば聞こえはいいが、実のところ、王は女性を相手にする能力に欠けているのでは、などと言う者、さらには、後宮など解体してしまえ、女達を解放すれば、身分の低い男にも嫁が来て子供も増えるのに、などと過激なことを言い出す者まで現れる始末だった。
そんな根も葉もない風評が、王の知らないところでまことしやかにささやかれている現状を
「……滅相もございませぬ。
わたくしはただ、君主としての自覚をお持ち頂きたいと思うのみにて……」
「それが
余とて王の義務は忘れてはおらぬ!
されど、他のことならいざ知らず、せっかく生まれた王子を生贄にする気など毛頭ない、こればかりは譲れぬわ!」
ベルゼブルは断固として言ってのけた。
「そこまで仰るのでしたら、どうかこの件、大臣達に
彼らの声をお聞き届け頂くこと、それが、魔界の繁栄と
アマルリクは胸に手を当て、深々と頭を下げた。
だが、魔界王は聞く耳を持たず、肩をそびやかした。
「余が王ぞ、魔界のすべては余が決めることじゃ!
家臣共の意見など、何するものぞ!」
司祭は渋い表情で面を上げた。
「……それでは、陛下は、政務をないがしろにされるおつもりなのですかな?
私情に走ったあげく、魔界が滅びても良いと仰る?」
「何を申すか、余は左様なこと、かけらほども思っておらぬわ。
むしろ、そなたの方が鬼畜ではないのか。
子を成すことができぬ人族の女ごときが、何ゆえ王妃の座に居座るのか、などと陰口をたたかれ、長年苦悩してきた妃に対し、やっとの思いで授かりし子を、生贄として火閃銀龍に捧げよ、などと無慈悲に宣告せよと?」
「そ、それは……」
司祭もさすがに口ごもる。
だが、すぐに、意を決したように君主を見据えた。
「ですが、アイシス様も、王家のしきたりや慣習に従うお覚悟の上で、嫁がれたのではございませぬか。
何はともあれ、長く手元に置けば置くほど、愛着も湧いてしまわれます。
対外的には死産という名目で、お子様は諦めて頂く外には……」
「何じゃと!?」
かっと頭に血が上り、ベルゼブルは腰の刀に手をかけた。
だが、それを抜く前に大きく息を吐き、手を離すと首を振った。
「……いかん、まだ酒が抜けておらぬ、冷静に考えられぬわ……」
「お……おお、わたくしとしたことが、
ならば、わたくしは一旦、退出致します、少しお休み下さいませ。
その上で、なにとぞ
司祭は深く礼をすると、
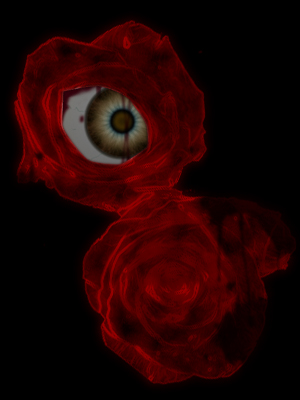
しかし、ベルゼブルの心にはまだもやもやとしたものが残っており、それに突き動かされて、去りつつある老人の背に声をかけた。
「……のう、アマルリクよ」
「おや、もうご決心を?」
老司祭は立ち止まり、振り向く。
「いや、一つ尋ねたい。
先ほどの神託じゃが、他の者……神官などはもう知っておるのか?」
「左様で……いえ、神託を受けたはわたくしのみで、その後は、一刻も早くお知らせせねばと、取り急ぎ参上
それが何か?」
「ああ……いや、よい。ともかく、考えてみるゆえ」
「はい、色々と失礼を致しました。
ご決心がつきましたら、呼び戻し下さいませ」
司祭が
ベルゼブルの瞳が、殺気をみなぎらせてぎらりと光ったのは。
そして、王は鬼の
「──トニトルス!」
緑の雷光が王の手からほとばしり、アマルリクの体を貫く。
「!? ぎゃっ!」
不意を突かれた老人は、ひとたまりもなく大理石の床に昏倒し、幾度か体を
「……あ……」
直後、王は自分が仕出かした事の重大性に気づき、顔から血の気が引いた。
それから、急いで周囲を伺う。
今の一幕を聞きつけて、いつもならすぐに衛士が駆けつけて来るはずだった。
しかし、兵士は皆、祝宴に参加が許されて、酔いつぶれてでもいるのだろうか、私室の周辺は
(不用心じゃが、今日ばかりは好都合じゃ……)
ベルゼブルはひとまず胸をなでおろした。
それでも、夜が明ければ、確実に死体は発見される。
万が一、女神の予言と、それをもみ消そうと凶行に及んだことが
やっとの思いで授かった大切な一粒種なのに、時代錯誤な神託ごときのために、むざむざ死なせてなるものか。
そのためにも、急いで死体の始末をつけなければ。
魔界王は必死に考えを巡らした。
(……灰も残らぬよう焼き尽くし、行方不明ということに……いや、もっと良い方法はないものか……ううむ)
「そうじゃ!」
王は早口で呪文を唱え、秘密裏に遺体をアナテ神殿へ運んだ。
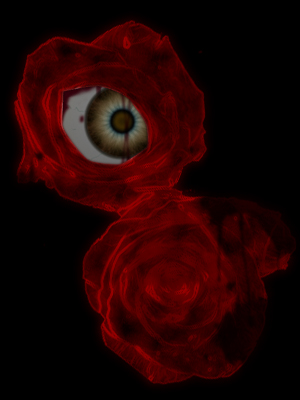
太古、権勢を誇り、王家の存在以上に魔族の心を一つにまとめていた荘厳な神殿の内部は広く、天井も高い。
あちこちに燭台が置いてあっても、闇に沈む部分の方が多いように思える。
聖なる場所ゆえ見張りもおらず、人の気配がないのもちょうどよかった。
ベルゼブルは、黒檀で出来た重厚な祭壇近くに死体を横たえ、苦悶の表情を浮かべたその口の端から滴った血をぬぐう。
その上で、司祭の手指を、胸をつかむような格好にしておく。
(これでよい。心臓の発作で死んだように見えるじゃろうて……)
一息ついて額の汗をぬぐったその時、誰かに見られている気がして、王は、ぎくりと振り向いた。
だが、宮殿内には誰もおらず、耳を澄ませても物音一つ聞こえない。
ほっとした瞬間、またもや視線を感じて、彼は後ろ上方を振り仰いだ。
「誰じゃ!」
だが、返答はなく、そこにいたのは人ではなかった。
揺らめく炎に照らし出されたアナテ女神の巨大な像、その金色の
魔界王は息を呑み、顔をゆがませると、再び呪文を唱えて逃げるように汎魔殿の自室へ戻り、ベッドに転がり込んで布団をかぶった。
(余の悪事に気づく者がいるとしたら、おそらく“焔の眸”のみじゃろう……。
されど、幸い、誕生し立ての王子を“焔の眸”に会わせる“対面の儀”は、完了しておる。
宝物庫に戻っていくシンハには、極上のワインを一樽、振る舞った……ゆえに今頃は、ほろ酔い機嫌で夢の中のはず……心配はいらぬ)
ベルゼブルは自分に言い聞かせた。
それでも、眠りは訪れてはくれず、結局まんじりともしないまま朝を迎えた。
そして、朝早くベッドを出て着替えた頃に、アマルリクの死の一報がもたらされたのだった。
ベルゼブルの思惑通り、司祭は病死とされ、告別式が行われた。
一人残されたアマルリクの幼い孫娘が跡目を継ぐこととなり、罪悪感もあって、王は物心両面の援助を惜しまなかった。
それ以降、妃や幼い
さらに、ミカエルもさすがに懲りたのか、天界は、侵攻どころか監視役の天使さえも置くことを諦めたようだった。
しばらくの間、ベルゼブルは神罰が下ることを恐れていたが、案に相違して、いくら経っても何事も起きず、また、神託もおりなかった。
平穏な日々が数か月続くうち、王は次第に、妃達が悩まされていた悪夢は、アマルリクの仕業だったのではないかと思うようになって行った。
(あやつは口癖のように、やれ最近の若い者は信仰心が薄れているだの、もっときちんと儀式をして、正しくお
その心境は分からぬでもない、されど、生まれたばかりの王子を紅龍の塔に入れよなどと、さすがに許しがたいわ)
司祭の悪事と決めつけることで罪業感も薄らぎ、ベルゼブルが
ただ一つ問題だったのは、それ以降、どんな神託も一切下りなくなったことだった。
不安がる人々に向けて、ベルゼブルは、それは司祭が幼く、まだ神事を行うことができないためで、いずれ復活する、憂慮の必要はないと布告した。
その後は長らく平和な時が続き、“黯黒の眸”の結界が魔界を守っていることもあって、魔族達のアナテ女神への信仰心はさらに薄らいで行った。
う ろん 【胡乱】
1 疑わしく怪しい・こと(さま)。胡散(うさん)
2 不確実であること。あやふやなこと。また、そのさま。胡散。
肯う(うべな)う
もっともだと思って承知する。よいとしてうなずく。
人身御供(ひとみごくう)
1 人間を神への生け贄 (にえ) とすること。また、その人間。人身供犠 (じんしんくぎ) 。
嘴(くちばし)を容(い)・れる
自分とは直接関係のないことに横から口出しをする。容喙(ようかい)する。