24.龍の宿命(2)
その日の深夜、ライラは無事に出産した。
リオンは再び猫になり、戸口に立つ見張りを眠らせると、音もなく女王の寝室に入り込んだ。
ベビーベッドには、男女の双子の赤ん坊が眠っていた。
変身を解いてから、ミルクの匂いがする頬にキスし、一人を抱き上げた時、声がした。
「やっぱり来たわね、魔物。わたしの赤ちゃんをどうする気?」
(やばい!)
慌てて彼がフードを深くかぶり直すのと、女王が叫ぶのとは同時だった。
「誰か来て! 魔物が赤ちゃんを!」
「騒いでも誰も来ないよ、皆、眠ってる。
この子は連れて行くよ。魔族だから、人界にはいられないんだ」
リオンは、腕の中の息子を抱きしめた。
「じゃあ、お前はなぜ人界にいたの!
どうしてわたしに、子供を産ませたりしたのよ!?
卑怯よ、猫に化けたりして!」
女王は、ガウンを羽織ってベッドから降りた。
彼は、頭を下げることしか出来なかった。
「……ごめん。言い訳になるけど、ぼくは、キミと出会うまで、自分が魔物だと知らずにいたんだ。
キミを愛してしまった後で、真実を知り……生きてる世界が違うからと、別れを決めたのに……子供が出来てたなんて……。
全部ぼくの過ちだ。本当にごめん……謝っても、許してもらえないだろうけど……」
「そんな言い訳、聞きたくないわ! それより、赤ちゃんを返して!」
「言ったろ、この子は魔物なんだ。強い魔力を持ち、寿命も人間より長い。
人の世界で生きてくのは無理だ……』
「いいえ、二人共、わたしの赤ちゃんよ!」
ライラは彼に駆け寄る。
リオンは、赤ん坊の額にある、盛り上がった部分を示した。
『見て、ここには角が隠れてるんだ。
いずれ背中のコブからも、黒い羽が生えて来る……ぼくそっくりのね。
そんな子が、人界の王家で、迫害されずに生きていけると思うかい?』
彼はフードを上げて額の角を露わにし、背中の漆黒の翼を広げて見せた。
「……あ……」
女王は、彼と息子を見比べる。
次にリオンは、ベッドに残った女の子を指差した。
「でも、この子はキミに似て、何もないから大丈夫だよ。
それとね、キミの弟の事もあるし、魔族の特徴があるこっちの子を、ファイディーの民はどう思うだろう?」
「そ、それは……」
女王は言葉に詰まった。
「心配いらない、ぼく達となら、この子も普通に生きていけるから。
母親の愛情は受けられなくても、ぼくが、父親としてありったけの愛情を注ぐよ、約束する!」
リオンは深々とお辞儀をした。
そんな彼をライラは見つめ、訊いた。
「教えて。どうしてわたしは、お前のことを覚えていないの?」
「え、……」
今度はリオンが口ごもる番だった。
記憶が戻るかも知れないから、うかつなことは言えない。
「そ、その……ぼくは、魔物……しかも夢魔だ。
でも、キミは女王……相手にされなかったから……実力行使に出たんだ……キミは、酷いことされた、ショックで……記憶が飛んだんだよ、多分……」
彼の答えは歯切れが悪かった。
「本当に? こうして一緒にいると、わたし、何だか心が温かくなる気がするの。
わたし達、そんなに悪い仲ではなかったような……」
リオンは勢いよく顔を上げた。
「まさか! 酷いことされたのに、心が温かくなるなんて、あり得ないよ!
悪い仲じゃなかった、なんて、どうしてそんなこと……!」
リオンの朱色の瞳から涙があふれる。
その刹那、双子が目覚め、同時に泣き声を上げた。
「ご、ごめん、起こしちゃったね、よしよし」
彼は慌てて息子をあやした。
ライラも娘を抱き上げて母乳を飲ませ、おぼつかない手つきでおむつを替える。
大人しくなった子を、彼女はベビーベッドに戻した。
そして、リオンへ向けて手を差し伸べた。
「返して。その子にもお乳をあげなきゃ」
泣き止まない息子を抱いたまま、リオンは
「いらないよ。この子はもう、ぼくと行くんだから」
「そんな、お腹が空いて泣いているのに、可哀想よ。
それに、わたし、あなたが悪い魔物だなんて、とても思えない。
もう少しお話ししましょう」
「分かったよ……」
リオンは渋々、乳飲み子を女王に返した。
ほっとしたライラは我が子に頬ずりし、乳首を含ませた。
おむつも取り換え、息子を娘の隣に寝かしつける。
幸せそうな様子を見て、リオンは、赤ん坊を取り返す気が失せてしまった。
「……今日は大変だったのに、起こしちゃって、ごめんね。
キミも眠った方がいいよ」
「わたしが寝たら、この子を連れていく気ね?」
「い、いや……それは」
「あなたは正直ね。すぐ顔に出る」
「また言われたなぁ……あ」
リオンは口を押さえたが、遅かった。
「ほうら、やっぱり。初対面で無理矢理なんて、嘘でしょう?
わたし達、知り合い……いいえ、恋人同士だったのね?」
「ち、違う……」
「教えて、あなたの名前を。なぜだか思い出せないの」
「駄目だよ……」
「どうして」
「どうしてもさ……」
「わたしね、猫に変身したあなたを初めて見たとき、呼びかけようとした名前があるのよ、きっとそれが、……」
「駄目だ、思い出さないで!」
「だから、どうして?
……もしかして、わたしを捨てたの?
他に好きなひとが出来て、わたしが邪魔になって?
それで、忘れさせてしまったの?」
ライラは畳みかけるように訊いた。
「そうだよ、ぼくはキミを捨てた。
そして、ぼくのことを覚えてたら、キミが苦しむと思って……。
だから……」
「何か理由があったのね?
……あなたはまだ、わたしを愛してくれている、そうなのでしょう?」
「そうだよ、他のすべてが嘘だとしても、ぼくがキミを愛してることは本当だ、今すぐ、さらって行きたいくらいに!
……けれど、それはぼくの勝手な思い込みさ……嫌がるキミを……力尽くで自分のものにした……その結果が……」
リオンは打ちひしがれた。
元々嘘は得意ではないし、洗いざらい話してしまいたくなっていた。
「あなたが淫らな魔物だなんて思えないわ。
力に訴えなくても、難なくわたしを
それに、夢魔は女性を誘惑するのが当たり前なんでしょ、なぜ、否定するの?
やはり何か、わけがあるのね。わたし、あなたのことをもっと知りたい。
忘れてしまったのなら、思い出したいの……」
彼を見つめ続けるライラの深い緑の瞳から、涙が一粒、こぼれ落ちる。
「泣かないで、ライラ。ぼくが悪いんだから。
キスしたいけど、やめておくよ……抑えられなくなるから……赤ちゃんを産んだばかりのキミに、手荒なことはしたくない……。
……さあ、ぼくの眼を見て。さよならだ、ライラ。
キミが産んだのは、女の子、一人だけだよ……」
彼は瞳に力を込め、女王の記憶を改変しようとした。
「あなたはわたしを妊娠させた……だったら今も、体のことなんかお構いなしに、無理矢理押し倒すのも平気でしょう? なぜ、そうしないの?
……やはり嘘なのね、力尽くだなんて」
「違う、……」
思わず、彼は眼を
「覚えていなくても、あなたのことが好きだったのは分かるわ。
ね、もう一度初めからやり直さない?」
「ラ、ライラ……」
彼女が差し出す白い手を、思わず、リオンは取ってしまいそうになる。
「やっぱり駄目だよ。この子はもらって行く。
ぼくは、キミに悪夢を見せに来た夢魔だ。女性の悪夢がぼくの糧……ぼくは自分の同類を増やすためだけに、キミを……」
リオンは必死の形相で、赤ん坊を抱き上げると呪文を唱えた。
「ムーヴ!」
「待って! 行かないで、──ペマウ!」
彼の名を、ライラは思い出せない。
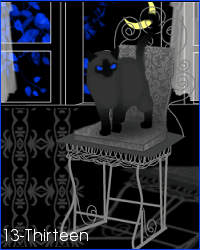
不機嫌そうなタナトスの
『よりは戻さなんだのか、ヴァーミリオンよ。
我は以前、申したはず、ライラの手を決して離してはならぬと』
それには答えず、彼は暗い声で言った。
「シンハ、お願いがあるんだけど」
『何だ』
「この子を連れて来るとき、ライラに気づかれちゃってさ。
他の人達の記憶は操作したのに、彼女のは出来なくて……だから、記憶を、消して来てくれない?
ぼくはもう彼女に会えない……離したくなくなってしまうから……」
ライオンは顔をしかめた。
『それでよいのか、ヴァーミリオン。まこと、忘れられるのか。
赤子の母親を奪うことにもなるのだぞ』
「……仕方ないよ。ぼくだけじゃなく、この子も人間じゃないもの。
どっちみち、角や翼が生えたら、お城じゃ暮らせない。
それにね、子供は男と女の双子だったんだ。
女の子は、外見に魔族の特徴がなかったから置いて来た……二人共取り上げたら、ライラが可哀想だろ……」
『ふむ……』
獅子は、痛ましげに、第二王子の血を引く青年を見た。
「ほう、男子か、どれ」
興味を惹かれたタナトスは、眠っている赤ん坊の顔を覗いた。
「ふん、金髪か。ライラに似ているな」
「瞳の色も彼女と同じですよ。
……残して来た子は、銀髪に紅い眼でしたけど」
『
ともあれ、
さても、赤子の名は?』
シンハは訊いた。
「色々考えて、まだつけてないんだ。えっと、アルとかアルノとか……」
「ち、つまらん名だな」
タナトスは舌打ちした。
『アルとは
「そうだったの、知らなかった……」
『ふむ。人界の織女と
彼は首を横に振った。
「ううん、ただ、響きがいいなって。
あ、そういや、ライラは琴座って意味だったね」
「ふん。それなら娘はヴェガか?」
タナトスは鼻を鳴らす。
「……それも可愛いと思いますけど」
『ならば、アレンウォルドという名はいかがか。
鷲の力、すなわち、権力や支配力を意味するのだが』
シンハの言葉に、魔界の王はうなずいた。
「うむ、いいぞ。王家にふさわしい。後は真の名か」
『アン・ナスル・ターイルでは。飛翔する
「よし、それで決まりだな」
タナトスは勝手に断定する。
『ヴァーミリオン、よいのだな?』
そこで、シンハは念を押した。
「うん、両方いい名前だと思うよ、ありがとう」
久しぶりにリオンは笑顔になった。
「ところで、息子を紹介したいんだけど、シュネやサリエル達はどこに?」
『魔界へ行っておる。
実はリナーシタが体調を崩してな。元より、サリエルの寿命も短いらしいが。
それゆえ、死ぬる前に是非とも魔界を見たいと申して、シュネが付き添った』
「……そっか。心配だね。大丈夫かな」
『汝も休養を取るがよい。その間、赤子は女官に預ければよかろう』
「たしかに、くたびれた面をしているぞ、貴様。
おい、誰か!」
タナトスが女官を呼び、赤ん坊の世話を言いつける。
『我はこれより、人界へ参る』
「ライラのこと、よろしく頼みます」
リオンが頭を上げた時には、シンハの姿はもうなかった。
「……ふう」
気が抜けてソファにへたり込む彼に、魔界王が声をかける。
「リオン、俺の妃になれ」
「は?」
女の童 め‐の‐わらわ
1 おんなの子。少女。
2 そば近く召し使う少女。
眇眇(びょうびょう)たる (眇々たる、眇たる)
とても小さく、取るに足りないさま。または、遥か遠くに見えるさま。渺渺。
機先(きせん)を制する
相手より先に行動して、その計画・気勢をくじく。 「機先を征する」と書くのは誤り。
リオンの息子の名について。
真の名「アン・ナスル・ターイル」は、鷲座の一等星アルタイルのアラビア語から。
普段の名「アレンウォルド」は、古代ドイツ語 arn-wald (または arin-vald)「鷲」-「権力,支配力」で構成された名、Arnold(アーノルド)に由来。
「さらに怪しい人名辞典」より