20.最終戦争(6)
際限なく湧き出るミカエルの軍勢をどうにか撃退し、タナトス達がついに最後の結界へとたどり着いたのは、それから丸一昼夜経ってからだった。
だがそこには、ずらりと居並ぶ神々が守りを固めていたのだ。
“くそ、忌々しい! もう、あとわずかだというのに!”
『焦るでない、“神と敵対する者”よ。
ヤツらは
黔龍の肩の上で、ライオンが、なだめるような声を出す。
“ええい、そんなことは分かっておるわ!”
タナトスが吼えた、そのとき。
「我らが交代致します、タナトス様、少しお休み下さいませ」
耳慣れた声に振り返った魔界王は、紅い眼をカッと怒らせた。
“貴様、なぜここにいる!?
留守居役を言い付けておいたろうが!”
「は……」
どやしつけられ、眼を伏せたのは、マルショシアス侯爵だった。
鮮やかな青い髪を背で束ね、
直後、その後ろに、彼直属の部隊が現れた。
「お怒りはごもっともなれど、王妃様が、加勢に参じよと……」
“何だと! 言うに事欠いて、我が妃の命だなどと!”
「いえいえ、決して偽りなど。
王妃様は、万一のことあらば、神族と同じく転移致せばよいと仰られ……」
“転移!? どこへだ! 人界か!?
それに、神族は俺達相手で手一杯だ、魔界が襲われることなどあり得ん!”
「た、たしかに、そうかも知れませんが、万が一ということも……そ、それに、兵達も、かなり
噛み付くような魔界王の剣幕に押され、へどもどと候爵は言う。
“ふん、この程度、疲れになど入るか”
そっけなく言い放いつつも、タナトスは周囲に眼をやった。
“……ち、たしかにバテ気味の者もいるな。
シンハ、また頼む”
『相分かった』
たてがみと瞳の炎を赤々と燃え立たせ、シンハは、全軍に向けて回復呪文を唱えた。
『──リクパーティオ!』
“わあ、疲れが吹っ飛んだよ、やっぱすごいや、シンハ”
“いつもありがとう、シンハ。これでまた頑張れるわ”
リオンとシュネから、感謝する心の声が届く。
疲労
魔軍が不眠不休で戦うことが出来たのは、こうして回復魔法を使い続けた“焔の眸”のお陰だった。
当然ながら、戦場では常に血が流されている。そのため、魔力の補給も容易だったのだ。
感じ入ったようにマルショシアス侯爵はうなずき、居住まいを正した。
「お聞き下さいませ、タナトス様。
王妃様は、万が一、魔界の結界が破られたりすることあらば、魔界ごと異界へ移住するお心積りでおられるそうでございます。
魔界近くでの戦闘により、敵味方双方の負の感情を取り込み、かなり力を蓄えておられるそうで。
ゆえに、心置きなく戦にご専念下さいますように、とのご伝言でございました」
“何、異界へ移住? ……”
黔龍は絶句する。
『……ふむ、異界か。
過酷な風土と聞き及ぶが、いかなる環境であろうとも、魔族は
神族が追うのも不可能。彼奴らは座標を知らぬゆえ』
シンハは、ぶるんと首を振った。
紅い火の粉が、黔龍の鱗に当たってぱっと散り、黒い体を滑り落ちてゆく。
“……たしかに、
よし、伝言、しかと受け取った。マルショシアス、貴様の加勢も許可してやる”
荒々しかったタナトスの語気も、すでに穏やかになっていた。
使命を果たし、
「はは。ありがたき幸せ。これでようやく、ご恩返しが出来ます」
話がついたところで、シンハは居並ぶ神々に向け、前足を振った。
『戦いの前に、とくと見よ、サタナエル。
シェミハザが示した資料では、ほとんどが老人、ないし壮年であった。
されど、目の前のあやつらは……』
言葉の途中で、シェミハザが現れた。
「失礼致します、タナトス様。至急、お知らせ致したいことが」
“連中が若返っている、ということか?”
タナトスは、あごで神々を示した。
「お気づきでございましたか。
堕天使の長達とも話しましたが、おそらく敵は、最も力の強い年頃の複製を創ったのであろうという結論に達しました」
“ふん、なるほどな”
黔龍は、ライオンと眼を合わせてうなずき、全軍に向けて念を送った。
“──皆、聞け! たった今、マルショシアスが援軍を連れて到着した!
我が妃が、魔軍を案じて派遣したのだ!”
援軍と聞いて、兵達はどよめき、士気はさらに上昇した。
“そして、見ろ! あそこに居並ぶ敵は、全盛期の神々を複製したものだ!
だが、まがい物の神など、恐るるに足らん!”
ここを突破すれば、いよいよウィリディスだ!
──全軍、突撃!”
タナトスの号令一下、最後の戦いの火蓋は切って落とされた。
それでも、やはり最後の砦、敵も、そうやすやすと明け渡すつもりはなく、魔軍は手こずっていた。
何しろ、今まで、神と直接戦った者は誰もいなかったのだから。
敵味方が入り乱れ、壮絶な戦いが繰り広げられていた。
青く輝く故郷を目前にして、心穏やかではいられないシュネとリオンは共に、敵に突っ込んでいく。
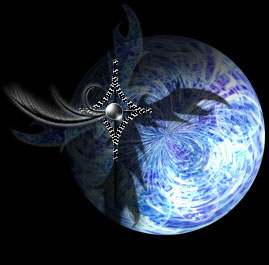
一方タナトスは、前に出たい気持ちを抑え、戦場を
まず敵の数を減らさなければ、最後の結界に近づくのも難しい。
そうした中、敵の大将、ヤヴィシュタ神は、目覚ましい戦いを見せていた。
“
『待て、サタナエル!』
次々味方が倒されていくのを見守っていたタナトスは、ついに待ちの姿勢をかなぐり捨て、シンハが止めるのも聞かず、襲いかかっていった。
“好き勝手に暴れてくれたな、ヤヴィシュタとやら!
今度は俺が相手だ!”
「……黔龍か。
ちょうどよい、貴様を倒せば魔族も仕舞いだ、覚悟するがよい!
──パイロ!」
ヤヴィシュタは呪文を唱えた。
“ふん、そんな弱っちい炎、吹き飛ばしてくれるわ!”
タナトスは叫び、本当に鼻息で、神の炎を散らしてしまった。
“次はこちらだ! いくぞ!
──イグニス!”
「ぐわっ!」
その攻撃は命中し、火の神は黒い炎に巻かれ、身悶えた。
“ふん、口ほどにもない、これで終わりだ!”
タナトスが、とどめを刺そうとした、その時だった。
「ヤヴィシュタ神、助太刀します!
──ブロンデ!」
澄んだ声が響き、黔龍に向けて雷が放たれた。
『この
やっとのことで追いついたシンハは、魔法を使った敵を凝視する。
相手の顔は、アスベエルそっくりだったのだ。
“貴様もいたのか、なぜ邪魔をする!”
タナトスも叫んだ。
「……かたじけない、マナセ様」
だが、助けられたヤヴィシュタは、相手をそう呼んだ。
“マナセ、だと!?”
タナトスは、新たな敵を改めて観察した。
顔は似ているが、髪と眼の色は金と青をしている。
翼もやはり黒ではなく、白かった。
年齢もまた、アスベエルよりも少し年上のようだった。
「そうとも、私は天帝の三男だ。
『神に見捨てられし者』などと一緒にするな、おぞましい魔物め!」
傲慢に少年神は吐き捨てた。
“何だとっ!?
だが、シェミハザが見せた映像には、貴様など……いや、俺が忘れただけか?”
黔龍は、肩の上のライオンに尋ねる。
シンハは否定の身振りをした。
『あれにはおらなんだぞ、たしかに』
「当たり前だ、僕は一度死んでいる。それを、父上が蘇らせて下さった。
そして、この戦いで手柄を立てれば、再び共に暮せると仰った、ありがたいことだ」
少年神は、うれしそうに言った。
“ふん。裏切り防止の虫など入れて、息子を戦場に放り込む親がどこにいる。
そんな最低な親をありがたがるとは、よほどの馬鹿だな、貴様”
冷ややかに、タナトスは言い放った。
「……く!」
顔を真っ赤にしたマナセの代わりに、ヤヴィシュタが言い返した。
「ゼデキア様は、ご自分のご子息さえも、特別扱いはなさらないのだ!
皆と同様の条件で武勲を立ててこそ、天帝の血を引く者としての証が出来ようとな!」
『冷徹なゼデキアのやりそうなことだ。
おのれの血を引く子だとて、複製となれば、使い捨ての駒でしかないと思うておるのであろう、
シンハは重々しく言った。
「何を申すか。
ゼデキア様の深い
左様なことより、タナトス、貴様は先ほど、『なぜ邪魔をする』と申したな。
それはやはり、アスベエルとお前達魔物の間に何か取引が成立していたのに、邪魔をするとは何事だと怒りを感じた、ということでよいのだな!」
ヤヴィシュタは、黔龍に指を突きつける。
“ふん、何のことだ?
魔界に来たときのあやつは、和平使節とも思えぬ腰抜けだった。
たしか、魔法も使えなかったな。それが、ずいぶん威勢よくなったものだと、驚いただけのことだ”
タナトスは平然と言ってのけ、シンハにだけ聞こえるように続けた。
“今の話がミカエルの耳に入れば、アスベエルが不利になる、まとめて片付けるぞ”
“心得た”
天帝の息子であろうと、全盛期の神であろうとも、絶大な力を誇る魔界の龍と守護石の戦闘形態とに叶うはずもない。
いくらもかからずに、彼らは敵を、灰も残さず燃やし尽くした。
そのとき、リオンからの念話が届いた。
“タナトス伯父さん、やっとこさ着きましたよ、シュネも一緒です。
結界、壊していいですよね?”
“ああ、とっととやれ。こちらも、あらかた片付いた”
直後、空間に衝撃波が走り、再び念が届いた。
“やった! もうウィリディスは目の前です、伯父さん!
ぼくらが先に、様子を見て来ますから!”
“よし、罠に気をつけろ。深入りするな、すぐ戻って来い!”
“分っかりました、行って来まーす!”
元気に言って、朱龍と碧龍は並んで転移門をくぐる。
“──皆、聞け! 最後の結界は解かれた!
だが、転移門は一度に大勢は通れん、リオンとシュネが偵察に行った、報告を待ち、突入する!
それまで、少し休んでおけ!
よし、シンハ、今のうちに回復を頼む”
『相分かった、されど、童子らは……』
シンハは心配そうに、転移門の方を見る。
“案ずるな、ウィリディスに入れば、サマエルが接触を図って来るだろう、まだ昇天していなければな”
『……おそらく、凶悪な悪霊と化しておることであろうな』
“そういうことだ、さあ、皆の回復を”
『御意。──リクパーティオ!』
シンハは呪文を唱え、魔軍は、二頭の龍が戻って来るのを待った。