12.最後の晩餐 (3)
移動する間も惜しみ、口移しに精気を送り続けたタナトスは、部屋に着くと、叔母を、そっとベッドに横たえた。
「まだ足りんだろうが、一気に満腹にするのはよくないからな」
「……悪いことしちゃったわね、特にケテルには」
答えるイシュタルの顔色は、まだそれほどよくなってはいない。
彼は肩をすくめた。
「あいつは気にせんさ。それより、なぜ、こんなになるまで……願でもかけていたのか?」
「……まあね。心配で、食欲がなかったこともあるけれど。
天界がすぐに、取引を持ちかけて来ると思っていたし、それにサマエルは、精気を吸わずにいても、ひと月は平気って……」
タナトスは、額に手を当て、大きく息をついた。
「何て無茶を。
あいつは人族との混血だし、紅龍の力もある、純血の淫魔とは一緒に出来んだろうに」
「そうね……」
イシュタルは眼を閉じた。
その目蓋も痛々しく落ちくぼんでいる。
色
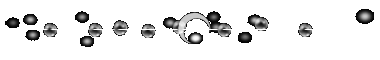
「待って……あ」
起き上がろうとする
「いえ、戻りたいわよね、奥方のところへ」
「構わんぞ。大体、一回では足りんだろうが」
「……いいの?」
上目遣いにイシュタルは尋ねる。
「遠慮はいらん、しかし、こんなになるまで、よく
年中、汎魔殿中の男どもが叔母上の相手をしたがっているというのに、もったいない限りだ」
タナトスは、体の下の女体を改めて眺めた。
抱き心地がよかった豊満な肉体は、今や、皮膚の上から骨が数えられるほどになってしまっている。
夏の雷雲のようにむくむくと苛立ちが湧き上がり、膨れ上がってゆくのを彼は感じた。
だが、それを爆発させることなく、彼は抑えた声を出した。
「前から思っていたのだがな。叔母上、俺の後宮に入ってはどうだ?」
唐突な申し出に、イシュタルは眼を丸くした。
「な、何を言うの……」
「くそ親父に義理立てするのはいいが、叔母上はまだ若い。
せっかくの女盛りを、棺おけに片足突っ込んだジジイのために浪費したあげく、しなびたミイラになってくたばりたいか?」
彼は、ずけずけと言ってのけた。
「相変わらず口が悪いわねぇ。実の父親に対して、そんな悪態……」
「ふん。あんな男!」
タナトスは、ぷいと横を向いた。
「やっぱり、親の愛情を受けられないと、そうなってしまうのかしら。
わたしが子供を産んで差し上げられたら……あの方も、お前やサマエルを可愛がったでしょうに……」
彼は、けげんそうな顔をした。
「叔母上が子を産むのと親父が俺達を可愛がることに、何の関係がある?
土台、あの男はガキに愛情など持てんのだ。
サマエルはともかく、確実にヤツの血を引く俺に対しても、気分次第で殴る蹴る、あげく首を絞める……」
「ちょっと待って。それは、お前が、サマエルにしていたことでしょうに!」
うろたえたように、イシュタルは彼の話をさえぎる。
彼は、叔母をじろりと見た。
「それがどうした。親父にされたことを、俺はそのままヤツにしていただけだ」
「ええっ!?」
イシュタルは青ざめ、絶句する。
「母上が死んで、あの男は、俺のような出来の悪いガキはいらんと思ったのだな。
つまり、親父の態度は叔母上とは無関係だ、自責の念に駆られる必要などまったくない。
もし首尾よく赤子を産めたとしても、俺達の二の舞になったろうさ」
がっくりと肩を落とし、イシュタルは目頭を押さえた。
「そうかもね……わたし、何も見てなかったわ……」
「いや、叔母上は、よくやっていたと思うぞ」
「え?」
「若い未婚の王族女性が、産んでもおらんガキを二人も面倒看る羽目になったら、普通は乳母に任せるだろう、誰も文句は言うまい。
それを、親身になって世話してくれたのだ。
親父が粗暴な振る舞いをしたのも、叔母上が寝込んでいた間だけだ。
だから、改めて礼を言おう、叔母上、かたじけない」
タナトスは上半身を起こし、頭を下げた。
「よして。わたし、母親代わりなんて全然出来てなかったわ」
「いや、叔母上がいなければ、サマエルはガキの時分に死んでいたはずだ。
あいつがせっかく還って来ても、叔母上に何かあったら、自分のせいだとくよくよするに決まっている、ヤツのためにもどうか自愛してくれ」
「でも……」
言いかけたイシュタルは不意に顔をしかめ、宙を見上げた。
金の粒を散らした藍色の瞳が、
「どうした?」
「ベルゼブル様がお呼びなの、行かなくちゃ」
起き上がりかける叔母を、タナトスは押し倒した。
「駄目だ」
「何するの、放して」
弱々しく、イシュタルはもがく。
「行くな。呼ばれた瞬間、うんざり顔をしたくせに」
「う、嘘よ、そんな……」
そう答えた叔母の眼が泳ぐのを、彼は見逃さなかった。
「俺が断ってやる」
「駄目、……」
“おい、くそ親父、叔母上は今、俺と寝ている、邪魔をするな!”
“……タナトス? どういうことじゃ、イシュタルが……そなたと……?”
枯れ木が風で鳴るような、かすれた念話が返って来る。
“俺は貴様を許さんぞ!
餓死寸前まで追い込まれた叔母上にも気づかず、のうのうと寝こけおって!”
“な、何!? 餓死じゃと!?”
驚愕した様子の父親に、彼は思念で追い討ちをかけた。
“さっさとくたばれ、この死にぞこない!
そうすれば、叔母上は好きなときに男と寝て、好きなだけ精気を食らうことが出来る!
もう邪魔するなよ、叔母上を殺したくなければな!”
たたきつけるように念話を打ち切ると、彼は唇を離し、にやりとした。
「これでもう、思い残すことなく食えるぞ、叔母上」
イシュタルは少し困った顔で、それでも笑みを浮かべた。
「最後の晩餐ってわけ?」
「まだそんなことを……!」
「冗談よ。さっきので、かえって空腹が刺激されてしまったわ」
「そうこなくては。自分に素直になった方がいい」
タナトスは、再び叔母に覆いかぶさっていった。

何度も愛し合い、空がわずかに明るんできた頃、ふとタナトスは汗に濡れた顔を上げた。
しかめ面で鼻をうごめかしていると、イシュタルが眼を開けた。
「行くの? 眠らないお妃が待っているものね」
「いや、まだ、夜は明けておらん。ただ、嫌な臭いを嗅いだものでな」
「え? ……あ、
部屋の中には
「ち、臭くてかなわんな!」
タナトスは、険しい顔で吐き捨てた。
「まあ。あの花は、香りの宝石とも呼ばれて、珍重されているのに」
「嫌なものは嫌だ!」
彼はそっぽを向く。
「そんなに? 魔界の奥地にだけ咲く、とても珍しい花なのよ。
ずっと昔の誕生日に、一輪だけ部屋の前に置いてあったの。
贈り主は分からなくて、今も気にかかっているのだけれど……」
イシュタルは、うっとりとした眼差しになった。
それを横目で見、彼は自分を指差した。
「夢を壊して悪いが、それは俺だ」
「えっ、お前が!?」
イシュタルは、藍色の眼を真ん丸くした。
タナトスは
「ふ、今思えば、たわけたことをしたものよ。
それというのも、汎魔殿の庭師に
「どうして、直接、渡してくれなかったの?」
「渡そうとしたさ。だが、叔母上の周りにはいつも人がいた。
「そうだったの、可哀想なことをしたわね」
タナトスは
「いや。俺が
そもそも、俺を嫌っている叔母上に、花を贈ろうなどと思ったことが間違いだったが」
「そんな、嫌ってなんか……お前がわたしを嫌ってたんでしょ。
亡くなったアイシス様はお美しく、完璧なお母様だった……わたしなんか、足元にも及ばないもの」
「それは違う。俺はただ、俺を見て欲しかっただけだ、弟ばかり構っておらずに。
気を引こうとしてはいつも失敗し、叔母上には怒られてばかりいたが」
「まあ……!」
イシュタルは口を押さえ、言葉をなくした。
タナトスは、遠くを見るような眼差しになった。
「母上が亡くなって、親父は俺を構わなくなり、俺は独りだった。
アルブを殺してしまった後は、一層孤独だった……。
俺を見るたび、親父は苦虫を噛み潰したような面でそっぽを向き、貴族達は震え上がって、召使どもさえ寄りつかず、……まあ、自業自得だが。
俺は、アルブの墓参り以外、何もする気になれなかった。
そうして、毎日花を取りに行くうち、庭師と顔なじみになったのだ。
俺が、死人に花など意味なかろうと言うと、庭師は、そんなことはない、故人は、あの世で生前同様の生活をし、手向けられた花は、その庭に咲くのだからと言った……。
特に、女は花が好きだから、喜ばないはずがないともな」
叔母の凝視を感じながら、彼は淡々と続けた。
「俺は、叔母上も花が好きかと聞いた。
庭師はもちろんだと答え、あの花を譲ってくれたのだ。
何年も丹精込めて育て、ようやく一輪だけ咲かせた、貴重な花を。
ヤツは、気づいていたのかも知れん……当時の俺の気持ちに。
叔母上の喜ぶ顔が見たい、弟に向けられる笑顔の、何分の一かでいい、微笑みかけて欲しいと願っていた、俺の心に」
「……そうだったのね」
イシュタルはつぶやき、引き出しから、細長いガラスの小箱を取り出した。
途端に強い芳香が立ち昇り、タナトスは息を呑んだ。
中には、闇中草が、あのときのままの姿で咲いていたのだ。
漆黒に近い藍色の花びら、金色のおしべ……それはどことなく、イシュタルの瞳に似ていた。
「ついに見つけたわ、贈り主を。
気づけなくてご免なさい、そしてありがとう、タナトス。
この花は、お前が来たから強く匂ったのね、きっと」
感慨深げにイシュタルは言い、彼を抱きしめた。
「い、いや……」
タナトスは柄にもなく、頬を赤らめた。
「その庭師にも、お礼を言わなくちゃね。
……お前、闇中草の花言葉を知っていて?」
「知るわけなかろう、そんなもの」
タナトスは
「『わたしを見つけて』よ」
「何?」
「闇中草は、昼は地中に潜み、夜、つぼみだけ地上に出して咲くの。
花が放つ高貴な芳香は、闇が深くなるほどに強さを増すわ。
極上の蜜を求める虫は、香りだけを頼りに、闇の中からこんな暗い色の花を探し出すのよ。
庭師は、わたしに、お前の心を見つけて欲しかったのね」
「あやつめ、味な真似を。今度墓に行ったら、褒めてやろう」
「……死んだの、その人?」
彼はうなずいた。
「クニークルスは短命だし、元から若くはなかったからな。
魔界で唯一の友だった……お陰で、心に刺さった棘がまた一本、抜けた気がする、すがすがしい朝を迎えられそうだ。
……と言っても、夜明けまでにはまだ間がある、もう一回どうだ?」
答えの代わりにイシュタルは、彼に口づけた。