6.光の檻(3)
ぐったりとなった魔物の首に、ミカエルは手を当ててみた。
弱々しいが、まだ脈はある。
「ふん……今日は、ここまでにしておいてやるか、死なせては元も子もない。
看守ども、檻を磨いておけよ!」
そう言い捨て、意気揚々と、天使長は引き上げていった。
「……すさまじいな」
声もなく、血の気の引いた顔で立ち尽くしていた看守達の一人が、口火を切る。
「ああ、本当に……」
うなずいた天使も、青ざめていた。
「いくら、相手が悪魔だって、何もここまで……」
釣られて言いかけた別の天使は、慌てて、拝むように手を合わせた。
「あ、今の、ミカエル様には内緒にしてくれよ、頼むから……!」
「言うわけないだろう、皆、そう思ってるんだから、なあ」
最初に口を開いた天使が同意を求めるように見回すと、同僚達から次々に、賛同の声が上がる。
「たしかに、少し酷過ぎる……」
「見てるこっちが痛いと言うか……」
「背中が痛くなった……」
「思わず自分の翼に触れてしまった……」
そんな中、一人が、はっとしたように言った。
「おい、待て、さっき、ミカエル様は、掃除しろと言わなかったか?」
「そうだった!」
「磨いておけと……!」
「急げ!」
掃除用具を手に、慌てて檻に入って来た看守達だったが、一面の血の海に息を呑み、吐きそうになる者も出た。
一人が、意識のないサマエルを指差し、訊ねた。
「看守長殿、こいつ、手当した方がいいんじゃないですか? 死んではまずいんですよね?」
アスベエルが答える前に、他の天使達が言った。
「いや、そんな命令、受けてないぞ」
「そうだ、下手なことをして、ミカエル様のご
すると、訊いた天使が反論した。
「でも、死んだら、絶対、我々のせいにするに決まってるぞ、ミカエル様は。
そしたら、全員、地下研究所送り……」
「うわあ、それだけは勘弁だ……!」
七人の天使達は震え上がった。
地下研究所送り、それは天使達にとって、地獄行きと同義語だったのだ。
「もういい、俺がやる。責任も俺が取るから」
アスベエルは、きっぱりと言った。
魔物の無残な傷に顔を歪めながらも、自分のローブを引き裂き、傷口にあてがって止血していると、同僚達と入れ違いに檻を出ていたベリアスが、小さな木の箱を手にして戻って来た。
「看守長殿、薬をお持ちしました。包帯もあります」
「ああ、ありがとう、気が利くな」
「いえ。でも、彼は、敵ながら
でも、生皮を剥いでみろとか言い出したときには、ちょっと驚きましたが」
薬を手渡しながら、
「……そうだな。
まあ、空腹のまま何日も拷問されて、さらに、でかい斧を突きつけられて、切り刻んでやるとか脅されたら、気が変にもなるさ。
まして、彼は王子、魔界じゃ大切にされて来たんだろうに、こうも酷く……」
ため息をついて、首を振り、それから、アスベエルは顔を上げた。
「さて、ベリアスはこのまま俺を手伝って、他の者は、清掃作業にとりかかってくれ。
……生きて明日を向かえたいなら」
「はい、看守長殿」
天使達は声を揃え、命令に従った。
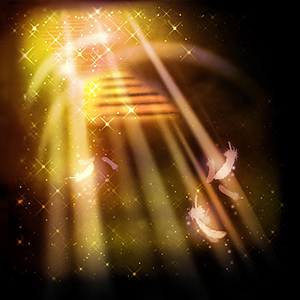
気づいたとき、サマエルは、粗末なマットにうつ伏せに寝かされ、すり切れた毛布がかけられていた。
眼に映る檻は、以前と変わらず、輝きに満ちて血の染み一つなく、背中の傷の痛みさえなければ、何もかも夢だったかと疑ってしまうほどだった。
手枷は外され、裸では気の毒だと思われたのか、短く切り揃えられた彼自身のマントが、腰布のようにして巻かれていた。
枕元には、冷めた薄いスープが入った金属の碗と、縁の欠けたカップ入りの水、そして干からびた小さなパンが、金属の盆に乗せられて置いてあった。
食欲が湧くような食事ではなかったが、回復のためには、多少なりとも栄養をつけなくてはならない。
痛みのせいで腕を動かせない彼は、盆の上のパンに噛りつき、スープや水にも直接口をつけた。
ほんのちょっと飲み食いしただけで、強い疲労感に襲われ、彼は眠りに落ちた。
どれくらい経ったのか、天使が二人、再び檻に入って来て、彼は目覚めた。
「ちょっとは食えたみたいだな、こんなもの、王族の口には合わないだろうが……。
ともかく、また薬を塗ってやるよ。痛むと思うが、我慢してくれ」
そう言って、アスベエルは毛布を剥いだ。
「いや、それには、及ばない……ありがとう、アスベエル、と、そちらは、たしか、ベリアス……だったね。
もう、だいぶ楽になった……この寝具も、包帯も片づけて、もう一度、手枷を、はめたら、いい……。
食事も、これ以上は、不要だ……怪しまれてしまう、ぞ……。
特に……アスベエル……、ミカエルに疑われている、ようだったし……私のことなど、放っておけばいい……敵に、同情し、命を落とす……なんて、馬鹿らしい、だろう?」
痛みをこらえているせいで、魔界の王子の言葉は途切れがちだった。
アスベエルは、ぽかんとした。
「な、何を言ってんだ、あんた。
敵に捕まって嫌なのは分かるが、腹も減るだろうし、こっちは、少しでも快適に過ごさせてやろうとしてるんだぞ、それを断るって?」
サマエルは、かすかに
「気を、悪く、しないで、くれ……気持ちだけ、もらって、おくよ。
それよりも、シェミハザ、から、色々と、話は、聞いている……こんなことが、ミカエルに、知られたら……。
私などの、ために……お前達を、酷い目に、あわせたくない……のだよ。
さあ、手枷を……遠慮は、いらない……私は、捕虜、なのだから……当然の、ことだ……うっ」
痛みに歯を食い縛りながら、サマエルは腕を揃えて差し出した。
断食のせいで腕は肉が落ち、手枷の跡が一層、痛々しく感じられた。
「ちょ、ちょっとお待ちを。あなたは、どうしてそこまで、わたし達のことを……?」
敵と知りながら、ベリアスは、思わず敬語を使ってしまった。
魔族の王子は、淋しげに微笑んだ。
「口を、割ろうと、割るまいと……私はいずれ、必ず、処刑、される。
情けを、かけても……無駄な、こと……それだけ、だ……」
「なぜ、そんなことを言う?
一般の魔物と違って、貴族は、魔界へ帰すのが通例だ、あんただって、いずれは帰れるはずだぞ」
アスベエルの言葉に、サマエルは、ゆっくりと否定の身振りをした。
「私を、捕らえた、ミカエルの、ホムンクルスは……最初、私の、子孫達を、狙った……ようだ。
四龍のうち、一頭でも、殺して、しまえば……天界は、勝利、出来ると……。
つまり……捕えられた、龍は、必ず、処刑、される、ということ……。
ましてや、私は……カオスの、貴公子……魔界最強の、龍……なのだから、生きて、ここから、出すわけもない、のさ……。
だから、早く、手枷を……ミカエルが、来る前に……」
促すサマエルに、今度は、ベリアスが否定の仕草をして見せた。
「まだいいですよ。ミカエル様がここへ来るのは、多分、四、五日後ですから。
あの方も、まあ、色々とお忙しい身ですし。
拷問は……あなたがひどく弱ってしまったので、少し間を置くことにしたみたいです」
「だから、今までみたいに、自力で傷を治したことにすればいいさ」
そう言うと、アスベエルは、布を外し始めた。
「あり、がたい……が、親切に、して、もらっても……礼も、出来、ない……。
ああ……出来そうな、ものが、一つだけ、あるか、な……」
魔界の王子の意味深な目つき、色っぽい流し目に、天使の一人、ベリアスの頬がみるみる紅潮していく。
裸同然で粗末な寝具に包まっていても、絶世の美貌の持ち主には変わりがない。
その
だが、顔をしかめた看守長が、それをさえぎった。
「やめろ、ベリアス。ミカエル様にでもなったつもりか?
無理をさせたら、傷口が開いてしまうぞ」
その途端、夢から覚めたように、ベリアスは頭を振った。
「あ、も、申し訳ありません、看守長殿、そんなつもりは……。
わたしとしたことが……どうしたんだろう、何だか、急に、その……」
サマエルは微笑んだ。
その
「ま、まことに失礼を……お、王子様、ごゆっくり養生をなさって……」
「私、を呼ぶのは、サマエル、でいい、よ。
では、あり、がたく……言葉に、甘えるとしよう。
囚人に、見返りも求めず、親切に、してくれる……こんな、心優しい者達を、ミカエルは、なぜ……手酷く扱う、のだろう、ね……」
ベリアスは、ばっと顔を上げた。
「心など、わたし達にはない、と思ってるんですよ!
……あ、いや、あなたに言っても仕方ないですけど……」
サマエルは眼を伏せた。
「……そう。
私に今、力があったら、お前達も、すぐに、解放してあげられるのだけれど、こんな状況、では……済まない、ね……」
アスベエルは不思議そうに尋ねた。
「何で、天使のことを、そんなに気にかけるんだ? あんたには関係ないだろうに」
「……虐げられる者の悲しみ、苦しみが、私には、よく分かるからだよ。
私は幼い頃、魔族の王子でありながら、なぜか、魔法が使えなかった。
母が、私を産むとすぐ亡くなったせいもあり、父にはうとまれ、兄には母殺しとののしられて殴られ続け、召使達にまで“取り替え子”と陰口をたたかれる、生き地獄のような生活……幼い私は耐え切れず、自殺を図った……。
そのとき助けてくれたのが、“焔の眸”の化身、シンハだった。
しかし、本当は、彼こそが、私の魔力を奪った張本人だったのだ。
予知夢を見たのだそうだよ、大人になった私が彼を殺し、“焔の眸”を破壊するという、ね。
彼は、予言の獅子とも呼ばれ、その予知は、かつて一度も外れたことはなかった。
そこで、彼は、産まれたばかりの私を襲い、殺そうとしたのだ……」
いつの間にか、言葉が滑らかに出るようになっていた。
話に引き込まれた天使達は、身動きも忘れて聞き入っている。
その様子に、サマエルは眼を細め、続けた。
「それは失敗した、ありがたいことにね。
彼は迷い、赤ん坊の魔力を封じれば済むと考えて実行に移したが、その結果が、私の自殺未遂……。
彼は悩んだ末、どうせ予言が外れないなら、そばで少しでも慰めてやろう、そして……大人になった私にすべてを話し、潔く殺されようと決意した……。
しかし、その告白を聞いたとき、消されたはずの幼少期の記憶が蘇り、私は、彼の優しさを思い出すことが出来た。
結局、予言は
初めは断られてしまったけれどね。
私を愛していないからではなく、自分の罪の重さに耐え兼ねて……。
無生物を妻にするなど気違いざただとミカエルは言ったが、たとえ宝石でも心を持つのなら、生き物と同等に扱って何が悪いのだろうね。
それでも、中々いい返事をもらえなくて……紆余曲折あったが、どうにか結婚まで漕ぎ着けたのだよ」
彼が、照れたように頬を染め、話を打ち切ると同時に、天使達は我に返った。
「……あ、いかん、薬を塗るんだった。ベリアス、そっちを頼む」
「は、はい」
サマエルの思惑をよそに、生真面目な看守達は、彼の傷の治療にかかった。
かんき【勘気】
主君・主人・父親などの怒りに触れ、とがめを受けること。また、その怒りやとがめ。