6.光の檻(1)
時は、サマエルが捕えられた日の翌朝にまで
サマエルが意識を取り戻すと同時に、すさまじい光が襲いかかって来た。
「うっ……!」
きつく目蓋を閉じていても、光は、鋭い刃のように突き刺さって来る。
無意識に視力を絞り、彼は眼を開いた。
前方に、何筋もの輝く光が、縦格子を形作っていた。
三方の壁、床、天井、すべてが磨き立てられた黄金で出来ているため、その光が乱反射し、
下級の魔族なら一瞬で蒸発してしまうかも知れない、聖なる光の洪水……しかし、上級魔族であるサマエルにとっては、その中にいる苦痛も、耐えられないほどではなかった。
彼は、しばらく、それらをぼうっと眺めていた。
やがて、霧が晴れるように、思考力が戻って来る。
(ここはどこだ……私は、なぜ……。
ああ……そうか、あの時、シュネを助けようとして……。
では、ここは天界……そして、これが、かの有名な“光の檻”か……。
なかなか美しい……)
「……む?」
動こうとして始めて、
着衣はすべて剥ぎ取られ、彼の裸身を隠しているのは、光で金色に染まった長い髪だけだった。
彼は知るよしもなかったが、捕らえられた直後、シュネ同様、無残に腫れ上がっていた皮膚は、すでに癒えてしまっていた。
彼は、自分を捕縛している手枷を、じっくりと観察した。
頑丈な作りで何の飾りもないが、おそらく魔封具なのだろう。
「──ムーヴ!」
念のため唱えてみるが、予想通り魔法は発動しない。
特に気落ちすることもなく、彼は冷たい壁を支えに立ち上がった。
先ほどから
「うわっ……!」
触れた途端に放電が起き、すさまじい衝撃が体を走り抜けて、火花が周囲に飛び散った。
それにもひるまず、サマエルは檻から出ようと試みたが、見かけにそぐわぬ頑強な光の障壁は、あくまでも彼の脱出を阻んだ。
仕方なく、身を引いた彼は、はっとして胸元に触れた。
「ない……!」
ニュクスが二回もくれた大切な貴石、ウィルゴまでもが奪われていた。
彼としては、四つの石をすべて身につけていたかったのだが、ウィルゴは持ち主を守護する力を持つのだし、代表として一つ持っているだけでいいと、ダイアデムが言ったのだ。
「置いてくればよかったが、とっさにそんな余裕は……にしても、戦の捕虜を丸裸にし、装身具まで盗るとは。
イナンナが言ったように、まるっきり追い
彼は、かつての妻、ジルの従姉が、ミカエルをそう称したことを思い出し、顔にかかる銀の髪を、苛立たしげに後ろへと振りやった。
次の瞬間、聞き覚えのある声が響いた。
「装飾品ごときの心配より、それを飾るおのれの首が、胴体と泣き別れになることの方を案じたらどうだ、蛇め!」
「ミカエルか」
魔界の王子は、静かに顔を上げた。
「さても面憎いヤツよ、少しは驚いて見せたらどうなのだ!」
檻の外に、魔族にとっては仇同然の大天使が立ち、彼に指を突きつけていた。
サマエルは肩をすくめた。
「まったく驚いてもいないのにか?
記憶操作が行われていると聞いたとき、真っ先に頭に浮かんだのは、本物から抜き出した記憶を複製……ホムンクルスに注入し、戦に投入する作戦ではないか、だった……うれしくもない正解だな。
それで、私が倒したのはホムンクルスか? それとも、お前の方が複製なのか?」
「くっ! 我が本体だ!
天使の長ともあろう者が、悪魔ごときにそうたやすく、やられてたまるか!」
ミカエルは、自分の胸を叩いた。
「……道理で。執念深いお前らしくもなく、至極あっさりと死んだし、死ぬ間際には、
あの時、偽者が言ったことは、やはり虚偽というわけか」
「ホムンクルスが何を言ったかは知らぬが、天使の長たる我の複製ぞ、悪魔ごときに何ゆえ、偽りなど言わねばならぬ!」
ミカエルは足を踏み鳴らした。
その様子を見ながら、サマエルはくすくす笑い、右生え際の、アメジスト色の一房を手に取った。
この光輝の中では、元の色は判然としなかったが、それでも彼には心強い、魔族としての
「冗談だよ。あの言葉が偽りでないことは、とっくに証明済みだ。
……にしても、からかうと面白いねぇ、お前は」
「き、貴様! 捕虜の分際でふざけおって!」
感情的なミカエルに対して、サマエルは冷静そのものだった。
「それにしても、捕虜を眠らせて運ぶとは考えたな。
逃げられる心配がない、利口な遣り方と言っておいてやろう」
すると、大天使は得意げに、にやりとした。
「そうだろう、あの触手に仕込んであったのは、特製の催眠剤よ。
さすがの貴様も、睡魔には勝てなんだようだな。
されど、通常ならば、まだ十日ほどは昏睡しておるはず……何ゆえ、かように早く目覚めたのやら、係の者を詮議せずばなるまい。
まったく忌々しい毒蛇めが、その間に脳をいじくって、記憶を直接抜き出してやろうと、手ぐすね引いておったのに」
「残念だったな、
私は純粋の魔族ではないし、カオスの力の加護も受けていて、大抵の毒物には耐性があるのだよ。
それに、私の脳をどうこうしたところで、何も得る物はないぞ。
こんなこともあろうかと、記憶には厳重に錠を下ろしておいたからな。
他の魔族でも同じこと、同意の上で、私が鍵をかけた。
たとえ、王たるタナトスを捕らえたとしても、お前達は、魔界の秘密を知ることは出来ない……私がいる限り、何一つな」
サマエルは、誇らしげに胸を張った。
「くそ、捕らえた斥候どもの記憶を吸い出そうにも、何も出て来ぬわけだ……!」
口惜しげに大天使は言った。
サマエルは、ぎらりと眼を光らせた。
「ところで、その、催眠剤とやらの開発時には、さぞかし多くの同胞を、実験台にしたのだろうな」
それを聞いたミカエルは気を取り直し、再び不敵な笑みを浮かべた。
「くく、その通りだ。二度と目覚めず、切り刻んで墓穴に放り込んだゴミ共も数知れぬわ。
まあそれも、貴様を捕らえる役には立ったのだから、本望であろうさ。
されど、貴様も、案外愚か者よ。つまるところ、貴様さえ堕とせばすべてが手に入る……左様な大事を、おのれで口にするとはな。
では早速、貴様の体に訊くとしようぞ、魔界の秘密とやらをな!」
ミカエルは、そばに並んだ天使の一人に、荒っぽく合図をした。
天使はうなずき、手にしていた大きな鍵を、光の格子にかざす。
一条の青い光が格子に向かって伸び、中央に、人一人がどうにか通れる隙間が出来た。
「さあ、今から、たっぷりとこれをくれてやる、覚悟するがいい」
ずかずかと檻に入って来たミカエルの手には、びっしりと鋭い刺が生えた、太い
サマエルは肩をすくめた。
「なるほど、この檻自体が魔封具……中では魔法が使えないというわけか。
原始的な方法でしか拷問出来ないとは、ご苦労なことだ。
まあ、日頃の運動不足の解消になる、とでも考えるのだな」
「粋がっても無駄だ!」
ミカエルは、ぴしりと鞭を鳴らし、彼を睨みつけた。
「まずは、魔界の結界の
そうすれば、命は助けてやらんでもないぞ」
刹那、サマエルの紅い眼が、再び冷ややかな光を帯びた。
「私とて魔界の王子だ、お前ごときの脅しには屈しないぞ。
それに、私が吐いたら用済み、その場で首を
何が、命は助けるだ、白々しい」
「ふん、その強情さがいつまで持つか、試してやる!
許しを乞うなら、今のうちだぞ、薄汚い魔物め!」
大天使は鞭を振り上げた。
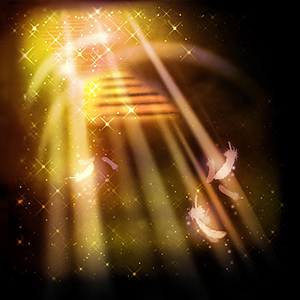
これで終わったと思うなよ、これから毎日責め立て、必ず吐かせてやる……!」
夜もふけて、捨て台詞を吐いて汗だくのミカエルが引き上げていくと、ようやくサマエルも、一息つくことが出来た。
(やってくれたな、愚天使め。
鞭の傷は、大したことはないが、あばらは全部、折られたか。
両手首と左足も……まあ、この程度、治癒には大してかからないが……。
水……があるわけもない、か)
「く……」
痛みをこらえて半身を起こす。やはり、檻の中には何もない。
壁や床に点在している、囚人を縛り付けるための鉄の輪と、少し離れた床に排水口らしき穴が一つ、口を開けているきりだった。
彼は仕方なく、床に流れた自分の血をなめた。
そうしている間にも、冷たい床が、容赦なく体温を奪ってゆく。
「そら、飲みな」
昏睡状態に近い眠りに落ちる寸前、声が降って来て、サマエルはびくっと眼を開けた。
目の前に、汚れ、あちこちへこんだ金属の器が置かれており、中には水が入っていた。
「……?」
眼を上げると、天使が一人、かがみ込んでいた。
黒い眼、同色の長い巻毛、肌は象牙色……それは、先ほどミカエルの隣にいた天使で、金髪
整ったその顔つきも、見知った天使の分類にはないもので、おそらく、大天使なのだろう。
「ありがたい……」
考えるのはそこまでにして、サマエルは、肘をついて頭を起こした。
手首は使えないので持ち上げるのは諦め、器に顔をつけ、夢中で水を飲んだ。
天使はさらに、ずたずたに切り裂かれたマントをかけてくれた。
「あんたのだ、ミカエルがこんなにしたんだが、裸よりは増しだろう。
食事は与えないように言われてるから、俺に出来るのはここまでだ、悪く思うなよ」
「重ねて礼を言う……だが、なぜだ? 私は……」
「敵の王子だってのは知ってるさ。けどあんた、ミカエルのホムンクルスを
心の中で思わず、
それでも、どうせなら、本体のあいつを片づけて欲しかったな。
皆も口には出せないが、そう思ってるさ」
天使は肩をすくめた。
「……聞いた話以上に、ミカエルは嫌われているのだな」
「ああ。神族はピンキリだが、あいつは特に酷いからな。
皆、命が惜しいから、仕方なく命令を聞いているだけさ。
でも、駄目だな……俺は嫌われてるだろうし……」
そこまで話したとき、不思議そうなサマエルの視線に気づき、天使は慌てて言いやめた。
「いや、何でもない、こっちのことだ。俺はアスベエル。“光の檻”看守長を勤めてる。
ま、長なんて名目だけだし、あんたのことも気の毒に思うよ。
その傷だって、癒してやりたいのは山々なんだがな」
「無理だろう……二重の意味で」
「そういうことだ。俺もぎりぎり生かされてる身で、命は大切にしたいんでね。
おっと、長居は無用だ」
そそくさと、アスベエルは檻から出ていった。
その後も拷問が続いたが、どれほど日にちが経ったのか、サマエルにはもう分からなくなっていた。
食事は与えられず、水も、アスベエルが時折こっそりと飲ませてくれる程度で、傷の治りも徐々に悪くなり始めていた。
しゅしょう【殊勝】
2 心がけや行動などが感心なさま。けなげであるさま。
かいさい【快哉】
《「快なる哉(かな)」の意から》ああ愉快だと思うこと。胸がすくこと。