12.龍の死闘(4)
タナトスは、息を殺し、魔法医の手元を凝視していた。
本当は、怒鳴りつけてでも急がせたくて仕方がなかったのだが、そんなことをしても邪魔になるだけと、自分を抑える分別はあった。
サマエルもまた、胸の上で拳を固く握り締め、息を
医者の作業を見守ると言うよりも、体が徐々に石に変わっていく苦痛に耐えているようだとタナトスは思い、念話で声をかけた。
“おい、痛むのか?”
サマエルは首を横に振った。
“いや、平気だよ、大したことはない”
“嘘をつけ。苦しそうだぞ”
“私にとって、苦痛は最大の喜びだからね”
“……変態め”
彼の言葉に、サマエルは何も答えず微笑んだ。
そのとき、エッカルトが膝を打った。
「そう、思い出しましたぞ、たしか、あれに載っていたのだった……!
──リブロ!」
彼は今までのものよりも、遥かに古びている書物の一群を呼び出した。
それらを机に乗せ、次々ページを繰って行くが、目当ての物にはまだたどり着けない。
タナトスは、急かせたいのを懸命にこらえ、魔法医の動きをただ見つめていた。
そうして、息詰まる時間がどれほど経っただろうか。
突如、エッカルトは弾かれたように顔を上げた。
「おう、これだ、“呪文で解けぬ石化の解呪法”……あり申した、これですぞ!」
「何、あったか!」
しかし、その眼に飛び込んで来たのは、様々な記号や図形の羅列で、彼は眉をしかめて魔法医を見た。
「何だ、これは?
わけも分からん妙な符号が、書き連ねてあるだけではないか。まったく読めんぞ」
「いえ、これは、我が男爵家に代々伝わる覚書のようなものでございまして、内容はすべて、暗号で記されておるのでございます。
悪用されては困るような事例や、貴族、ことに王族の方々の名誉に関わる事柄も、多々ございますれば」
「
医者の長い説明に苛ついたタナトスは、ついに声を荒げた。
「も、申し訳ございませぬ」
急ぎエッカルトは、大昔の先祖が遺した暗号に眼を凝らした。
「ええ……これを解読致しますと。
『患者の血縁者が、石化部分に精気を吹き込むと解呪出来る場合がある、ただし、大量の魔力を必要とするため、力弱い者がこれを行えば、命を落とす危険もある』、とのことでございます」
「精気を吹き込む……なんだ、そんな簡単なことか」
並大抵の手段では、弟の特殊な石化を解呪するのは無理だと思い、身構えていたタナトスは、拍子抜けしてつぶやいた。
魔法医は厳しい表情で、否定的に答えた。
「いえ、お言葉ほど、容易なこととは思えませぬ。
実は、この下にはいくつか、別な書き手の註約がついておりましてな。
成功したのは、ごく狭い範囲の石化、それも数例のみで、患者のみならず、術者までもが死亡した事例があると……。
お力あるタナトス様と言えども、かなり難しいこととなられまするは
ことにサマエル様の場合、患部が広範囲に渡っておられますゆえ」
「ふん、火閃銀龍に勝ち目のない戦いを挑んでいたときの、先の見えない気分よりは遥かにましだ。
聞いたか、サマエル。割と簡単なことで治るらしいぞ」
「無理をするな、タナトス。お前に、もし、何かあったら……」
「何もあるわけがなかろう、すぐに治してやる、大船に乗ったつもりでいるがいい」
自信満々で自分の胸をたたくと、タナトスは、弟の心臓目がけて侵食を続ける石化部分の先端に口づけた。
「あっ」
サマエルの体が、びくりとする。
「どうした? 痛むのか?」
「い、いや……」
「おお、ご覧下され、お二方。石化が解けておりますぞ!」
エッカルトが声を上げた。
その言葉通り、彼が口づけた辺りが、サマエル本来の肌に戻っていた。
「よし、続けるぞ」
「……ああ、うっ」
夢中になって続けるうち、タナトスは、自分が口づけるたびに弟が体を動かし、声を上げる理由に気づいた。
「ははぁ、貴様、感じているのだな?
俺はただ、石化を解こうとしているだけだぞ?」
からかうように彼が言うと、サマエルは頬を赤らめ、そっぽを向いた。
「くく、恥じる必要はあるまいい、俺が教えたのだ、俺に反応するのは当然だろうが?」
笑いながら、タナトスはさらに精気を与え続ける。
「ち、違……くうっ!」
サマエルは否定しつつ歯を食いしばるが、体はどうしても、兄に反応してしまう。
「ふん、貴様はいつもそうだ、口よりも体の方が正直なのだからな。
それほど、俺に抱かれたいか? ならば……」
タナトスはマントを外し、人目もはばからず服を脱ぎ始めた。
石化は、もうほとんど解けてしまっていたし、彼も空腹だったのだ。
「や、やめろ!」
「そういえば、貴様の中で二度モトを抱いたが、あいつもまだ名残惜しそうだったな」
「やめろと言うのに! エッカルトもいるのだぞ!」
サマエルは、彼を押しのけようともがくが、腕の力だけでは無理だった。
石化が解けたばかりの足はまだ言うことを聞かず、頼みの魔力は火閃銀龍に吸い取られて、簡単な呪文も使うのは難しかった。
そんな弟の手を押さえつけ、タナトスはにやりとした。
「くく、今まで試したことはなかったが、貴様だったら、誰かに見られている方が感じるのではないか?」
サマエルの顔から血の気が引いた。
「え、い、嫌だ、そんな……!」
「エー、ゴホン、ゴホン」
男爵位も持つエッカルトは幾度か咳払いをしてみせたが、一向にタナトスが態度を改めないのをみると、声に威厳を込め、主を
「タナトス様、お
弟君は、まだお体が完全ではございませぬ、今、無理をすれば、どんな反動があるか知れませぬぞ」
しかし、命令されることが何より嫌いなタナトスは、カッと眼を怒らせた。
「黙れ、エッカルト! 男爵ごときの分際で俺に逆らうなら、この場で息の根を止めてやるぞ!」
魔法医もまた、怒りを
「いいえ、黙りませぬ、わたくしにも、患者を守る義務がございますゆえ!」
「もういいよ、エッカルト。私が言うことを聞けばいいのだから。
代々魔界王家に仕え、今また私の命を救い……そんな大事な家臣を、私のために死なすわけにはいかない。
さあ、兄上、どうぞご
サマエルはそう言い、抵抗をやめた。
「ふん、初めから大人しくしておればいいのだ。
エッカルト、聞いたか。こいつも同意している。貴様は隣室に下がっておれ、後でまた呼ぶ」
タナトスは、手で追い払う仕草をした。
「それでは、失礼致します」
不服そうな魔法医が足音も高く退出するやいなや、魔界の王は部屋に結界を張り、弟に覆いかぶさっていった。
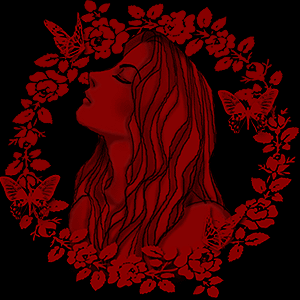
それでも、さすがのタナトスも、大量の精気をサマエルに与えて疲れており、また弟の体調をも気遣って、いつもほど激しくはしなかった。
隣に横たわるサマエルの、汗に濡れた絹糸のような髪をなで、彼は言った。
「やはり、貴様は極上だな。モトとは比べ物にならん……ずっとこうしていたいくらいだ」
「……そう。こうして私をもてあそぶために、魔界に残って王になれ、などと言っているのだな、お前……」
虚ろな眼を宙に
「いや。たしかに、俺はお前にそばにいて欲しいと思っている、だが、強要する気はない。
それに、貴様が王になったら、俺が付け入る隙はなくなるぞ。
魔封じの塔に俺を幽閉して、拷問することも可能だ……あるいは、処刑することもな」
タナトスは、自分の首を斬る真似をした。
「お前、そこまで考えて……?」
思わずサマエルは、視線を兄に注ぐ。
「どの道、俺が貴様を抱くのはこれで最後だろう。“焔の眸”が文句たらたらだからな。
それはさておき、俺はずっと……どうすれば、俺が今まで貴様にして来たことの
貴様が女だったなら、子を
「それは無理だ。同母兄妹で結婚、まして王妃などとは。誰も納得しないよ」
第二王子はきっぱりと言った。
「ふん、アナテは、モトを夫にしていたぞ」
「大昔のことだし、私達とは条件が違う。
魔力こそ強かったものの、アナテは王家の血を引かず、王亡き後、彼女と結婚出来る王族は他にいなかった……女王であり続けるためには、息子を夫にするしかなかったのさ」
「では、貴様はどうあっても、王になる気はないというのか、それでは……」
「待ってくれ」
さらに話を続けようとする彼を、サマエルはさえぎった。
「先に、エッカルトを呼んでくれないか」
「……ああ、貴様の体を診せる必要があるな」
魔法で二人の体を清め、タナトスは服を着る。
指を鳴らして結界を解くと、彼は隣室に向かって声を張り上げた。
「おい、エッカルト! 戻って来て、サマエルを診ろ!」
「失礼致します」
それから、第二王子の脈を取り、全身くまなく調べ始めた。
「どうだ?」
タナトスは、ぶっきら棒に訊く。
「わたくしが診ますところ、石化は完全に解けておりますが。
いかがでしょう、サマエル様、どこか、痛みなどはございましょうか?」
エッカルトは心配そうに尋ねた。
「いや、ないよ。強制リハビリのお陰で、血の巡りがよくなったからかな」
皮肉っぽく、サマエルは返した。
「それはようございました」
心から安堵し、魔法医は笑顔になった。
「では、貴様に用はないな、帰っていいぞ」
タナトスが手を振ったとき。
サマエルが口を開いた。
「いや、まだエッカルトには用がある。
ああ、タナトス。その前に礼を言っておこう、お前のお陰で思い出せたよ、すべてを、ね」
「思い出せた? 何をだ?」
タナトスは、けげんそうな顔をした。
「ねぇ、エッカルト、本当に酷い夜だったな……。
知らずにいれば……私の運命も、今より少しはましになっていたかも知れない……そんな気がするよ……」
サマエルは、悲しげに自分の肩を抱き、首を横に振った。
そのとき、タナトスは、魔法医が青ざめていることに気づいた。
「貴様、何か知っているのか?」
「は、はて、わたくしめには、何のことやら、さっぱり。
ご、御用がなければ、わたくしはこれにて」
そそくさと退出しようとした魔法医の首に、いきなり、サマエルが抱きついたのはそのときだった。
「逃がさないよ、エッカルト」
「サ、サマエル様!?」
眼を剥くエッカルトの顔に、第二王子は頬をすり寄せる。
「もう隠していても無駄だよ、エッカルト。私は思い出したのだから。
今こそ真実を告白するときだ。お前だったのだね、私の……」
「何ぃ、こいつが、貴様の実の父親だと!?」
思わずタナトスは、叫んでしまっていた。