8.光中の闇(2)
“相分かった”
その返事と同時に、フェレスは現実世界に戻っていた。
「た、大変よ、サマエルが捕まって……」
「捕まっている!? 誰にだ!」
「嫌、苦しい、放して」
フェレスはもがく。
「我が兄弟を放せ、タナトス。それでは話も出来ぬ」
二人の間にニュクスは割り込み、フェレスを救い出して尋ねた。
「“焔の眸”よ、サマエルを捕らえているとは何者か?」
「お、驚かないで聞いて。相手は、あの、
フェレスは息を弾ませ、答える。
思いもよらない名前が出たことで、タナトスは眼を
「な、何ぃ、火閃銀龍だとぉ!? たしかか!」
「ええ、そう名乗っていたわ。それに、あんな巨大な龍が、他にいるとは思えないし」
「ふうむ、火閃銀龍とはまた、厄介な。
ともかく、詳細を聞かせよ、“焔の眸”」
冷静な兄弟石の言葉に促されて、フェレスは息を整え、話し始めた。
「まず、内部に入ったら、やはり、魔族の怨霊達が現れてね。
押し問答していると、初代の紅龍モトが出て来て彼らを
「……モト。
アナテの息子であり、夫でもあった……
“黯黒の眸”の化身は、感慨深げにつぶやく。
「そんなことはどうでもいい、続きはどうした!」
タナトスが荒々しく叫び、フェレスは急いで話を続けた。
「サマエルは、火閃銀龍に飲み込まれそうになっていたわ。
闘おうにも、すさまじい力で
モトは今、一人でサマエルを守ろうと頑張ってくれているの。
だから、一緒に来て、タナトス」
フェレスは、かつての主の手を取った。
「分かった、行ってやる」
当然のように身を乗り出したタナトスに向け、ニュクスは言った。
「待て。おぬしのみでは対抗出来かねようぞ、相手が火閃銀龍ともなれば。
他の龍、朱と碧龍も連れて行かねばなるまい」
「そうだわ、シュネの呼び声なら、サマエルを目覚めさせることができるかも知れない!」
そう言うと、ニュクスの体は輝き出す。
次に現れたのは、紅毛の少年だった。
「オレが呼びに行きゃ、シュネは……あ、っつっても、まだ彼女にゃ、魔族
びっくりするだろーし、どうすっかな」
ダイアデムは腕組みをした。
「この際だ、すべてを聞かせておいたがよい、いずれ、否応なく知ることとなるのだ。
ニュクスの言葉に、ためらっていたダイアデムもうなずいた。
「そーだな。んじゃ、タナトス、お前はリオンを呼んで来てくれ」
「分かった。ニュクス、お前はここにいて、サマエルを見ていてくれ」
「心得た。気をつけてゆけ、二人共」
「ああ」
「じゃな!」
ダイアデムとタナトスの姿は同時に消える。

「……火閃銀龍、か」
人界の魔法陣から出て、“焔の眸”の化身と別れたタナトスはつぶやいた。
別れ際、ダイアデムは彼に、サマエルの精神内部での体験を見せてくれた。
その中で火閃銀龍は、自分の願いを伝えようと、彼の子供に宿ったと言っていた。
生かそうと試みたが、赤ん坊は死ぬ定めだった、とも。
彼がまだ王子だった頃、クニークルスの女性、フィッダが産んだ奇形児。
背中で融合した二つの体、頭は四つ、瞳はそれぞれ別の色……黒、紅、朱、
そして『父よ、我は“火閃銀龍”の化身。予言はひずみ、生まれ
(くそ、火閃銀龍め、いくら死ぬ運命だったとしても、勝手に、俺の子に宿っただと……?
それにだ、ヤツは本当に、子供を生かそうとしたのか?
どう見ても、あの赤ん坊の姿は、火閃銀龍を具現化したようだったぞ。
あやつが宿ったせいで、俺の子は死んだのではないのか?)
タナトスは、ぎりりと歯を食いしばった。
「……まあいい、ヤツを吊るし上げ、口を割らせればいいことだ!
──ヴェラウェハ!」
決意を口に出すと気分も落ち着き、タナトスは、ファイディー城に向かった。
“おい、リオン。俺だ、タナトスだ。
サマエルが危機に陥っている、貴様の助けが必要だ。
門の前にいる、急ぎ出て来い”
城門の前で、彼はリオンに呼びかけた。
“え、えええっ!? ちょ、ちょっと待ってて下さい、すぐ行きます!”
焦った返事が聞こえて来て、すぐに茶髪の少年が現れた。
「タ、タナトス伯父上、父さんが危機って!?」
サマエルを父と呼ぶことに決めてから、リオンは、タナトスをも伯父と呼んでいた。
タナトスは無言で、少年の額にいきなり指を二本、押しつけた。
「えっ、な、何……!?」
説明が面倒になった彼は、ダイアデムに見せられたことを、面食らうリオンにそのまま送ったのだった。
「わ、分かりました、急がなくちゃ、父さんが危ないんですね」
青ざめた顔で、リオンは言った。
少年の腕をわしづかみにし、心急くままタナトスは呪文を唱えた。
「行くぞ、
──ヴェラウェハ!」
一方、魔法学院に着いたダイアデムも、頭をひねっていた。
「……っと、何て言やいーかなぁ。
“黯黒の眸”は、全部話しちまえって言ってたけど……。
あーもー、ンなトコで、うだうだしててもしょーがねー、当たって砕けろだ!」
心を決めた彼は、シュネに念話を送った。
“シュネ、オレだ、ダイアデムだ。
サマエルがヤバいことになっててさ、キミの助けが必要なんだ、一緒に魔界へ行ってくんねーか?
門のトコにいるから、すぐ出て来てくれ”
「ダ、ダイアデム! サ、サ、サマエル様が、や、やばいって、ど、どういうこと!?」
一瞬後、赤みがかかった金髪の女性が、彼のそばに出現していた。
彼女は焦ると、どもってしまう癖があるのだった。
「あ、あのよ、話せば長くなっちまうんだけど……」
ためらう彼に、シュネは緑柱石の眼を向け、不思議そうな顔をした。
「ど、どうしたの、い、急ぐんじゃ、ないの?」
「えーと……実はな、キミに、その、色々言ってないコト、あってさ……。
うー、くそ、めんどくせー、オレの記憶、見てくれ!」
ダイアデムは彼女の手を取り、タナトス同様、まずは、サマエルの内部世界での出来事を見せた。
それには数分を要した。
「た、大変、や、やっぱ、い、急がなきゃ!」
叫んだシュネの手を、ダイアデムは放さず、言った。
「待ってくれ、キミにはもう一つ、見せなきゃいけねーんだ」
「え、もう一つ?」
不審そうな彼女の眼を、“焔の眸”の化身は見返すことが出来ず、うなだれた。
「……ああ。
キミが腹立ててもしょうがねーけど、でも、それでも、一緒に来て欲しいんだ、これ見ても」
「わ、分かった。と、とにかく見せて。
は、早くしなきゃ、いけない、んでしょ」
「ああ」
第二の記憶を見せ終わるには、数秒しかかからなかった。
それは、シュネを魔法学院に送っていったダイアデムが帰宅した直後の、彼とサマエルの会話……そのごく一部分だった。
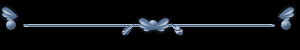
記憶の中で、ダイアデムは言っていた。
「けど、血筋のこと、シュネに言わなくてよかったのか?
もう戻らねーかもしんねーぜ、彼女」
サマエルは否定の仕草をした。銀の髪が、朝日を浴びて煌く。
「いや、必ず戻って来るさ。いずれ彼女も気づくだろう、自分が、普通の人間とは決定的に違う、ということに。
もう、薄々感じているかも知れないが」
紅毛の少年は肩をすくめた。
「何で教えてくれなかったんだ、って恨まれちまうかもな」
「そうだね。ただ、短い間でも彼女には、普通の女性として生きて欲しかったのだ」
「でも、結局は、魔界と天界との戦に巻き込んじまうことになるんだろ?
そん時になって、今までの生活を捨てて戦えって、酷くねーか?」
サマエルは眼を伏せた。
「たしかに辛いところだが、彼女が魔族として覚醒すれば、人間の中で普通に暮らすことは難しい。
成長速度も、人間とは違うしね」
「たしかにな」
「彼女は、我ら魔族の幸運の女神、存在そのものが周囲の者の心を和ませ、未来に明るい希望を持たせてくれる。
真実を告げなかったのは、彼女への、ほんのささやかなお礼なのさ。
恨まれてもいい、彼女には、一つでも多く素敵な思いをさせてやりたい。
思い出すたびに心が温かくなるような思い出を、人間の中でたくさん作って欲しいから」
ダイアデムは、にっと笑った。
「心配いらねーよ、シュネは明るくって強い。
何があっても、めげやしねーさ。お前よりもジルに似たんだな」
「そうだね。これで念願の四龍が揃い、ついに我らは、朱の貴公子とエメラルドの貴婦人を加えた、最強の力を手に入れた。
運命の時はもう、すぐそこまでやって来ている……」
魔族の王子は、未来に思いを馳せるように遠い眼をした。
「予言通りなら、今度こそ、魔族は天界に勝利出来るってわけか」
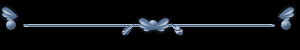
そこで、いきなり記憶は途切れ、シュネは現実に引き戻された。
「つまり、キミは魔族で、そんで、サマエルの子孫なんだ……リオンと同じく、さ」
ダイアデムが、おずおずと付け加える。
それに答えるシュネは、意外なほど冷静だった。
「へえ、そうなんだ。
まあ、何となく、そんな気はしてたんだよね……サマエル様の子孫てのは、さすがに予想外だったけど。
でも、やっぱり、もっと早く教えて欲しかったな」
「いや、だから、サマエルは、キミに幸せになって欲しいって思って……」
「うん、気持ちはうれしいんだけど。
あたし、人界じゃ、あんまりいい思いしてなくて。
この姿になっても、違和感ありまくりで……周りの人達が、急にちやほやして来んのも、何だかさ……」
シュネは、大きなため息をついた。
そんな彼女を、ダイアデムはちらりと見た。
「
「……そう、かも。だから、あんまり人界に未練ないんだ。
それよか、早く、サマエル様を助けに行こうよ」
「ああ。けど、そんなに居心地悪いんか、ここ」
彼は学院の建物を指差す。
「居心地悪いっていうか、ここは自分の場所じゃない、って感じ?
その訳がようやく分かったよ、あたし、人間じゃなかったんだ……あ、そんな顔しないで、ダイアデム。
これでも、うれしいんだよ、すごく。
あたし、自分が何か分かんなくて、ずっと心細かったんだ。
けど、あたしは魔族で、しかも、サマエル様の血を引いてるんだよね。
なんかさ、すっごくうれしいよ」
シュネは微笑み、“焔の眸”の化身は、ほっと胸をなで下ろした。
「そんじゃ、行こうか」
ダイアデムは、手を差し出す。
「うん……キミに
その手をそっとシュネは取り、二人は魔界へと向かった。