4.迷宮の宝石(1)
その一月後、汎魔殿の謁見の間にて。
「タナトス陛下におかせられましては、ご機嫌うるわしく……。
久方ぶりにご尊顔を拝する栄誉に恵まれ、喜びもひとしおでございます。
……おや、いかがなされました?
何やら、お元気がないようにお見受け致しまするが」
冬の朝、葉に降りた霜のような銀髪、猫に似た、縦長の
久しぶりに汎魔殿に
「貴様こそ、どうした。引退し、
もう、孫の相手に飽きたのか?」
タナトスは、
「お陰様で、心静かな隠居生活を満喫しておりましたが、それもいいところ、数年止まりでございますな。
暇が増えてまいりますと、汎魔殿にてお仕えしておりました頃が懐かしくなりまして。
失礼ながら、陛下のご機嫌
「ふん、俺の顔が見たくなっただと? 見え透いたことを言うな。
どうせまた、誰かに、いらんことを吹き込まれたのだろう」
「さすがは陛下。実は先日、わが城にパイモンが参りましてな。
近頃、陛下はご気分がお優れにならないご様子、どこかお悪いのではないかと申すのでございますよ。
魔法医にお見せしたいが、我々ではお聞き入れ下さるまい、それがしの方から勧めて欲しいと……」
タナトスは、どうでもよさそうに肩をすくめた。
「……医者? 俺が大人しいと病気と考えるのか、単純なヤツめが。
まあいい。心配はいらん、どこも悪くないと言っておけ。
それにしても、パイモンとは意外だな。
あやつはいつも、やれ、俺が人の話を聞かん、真面目にやらんとほざいてばかりいたものを」
「陛下のおんためを思えばこその、小言でございましょう。
以前は、“焔の眸”閣下が、あなた様をたしなめて下さいましたが、サマエル様のもとへお
「……ダイアデム、か……」
ふとタナトスの視線が宙に浮き、暗くたゆたう。
プロケルは、琥珀色の
(たしかに妙だ。
いつもであれば、『陛下』とお呼びしたことに必ず反発なさるのに、それもないとは。
パイモンが心配するわけだ……)
「それでは、何か、ご心配事でも?
わたくしめでよろしければ、ご相談にお乗り致しまするぞ。
無論、誓って他言など致しませんので、どうかお聞かせ下され」
プロケルは、パイモンが、今までのことを洗いざらい語っていったことなどおくびにも出さず、そう促した。
だが、タナトスは、心ここにあらずと言った風で、彼の方を見ようともしない。
沈黙が続く。
「……タナトス“陛下”?」
不興を買う覚悟で、元公爵はさらに声をかけてみたが、魔界王の返答は、気のないものだった。
「貴様に話しても、どうなるものでもない……」
「されど、多少は、お気が楽になられるやも知れませぬぞ。
わたくしとて、かつては公爵位を頂いた身、ダテに年を取ってはおりませぬからな」
プロケルが食い下がると、タナトスは、ようやく視線を彼に向けた。
そして、けだそうな声で尋ねる。
「では聞くが、貴様の妻は、親が決めた相手だったのか?」
意外な話題だったが、プロケルは問い返したりはせず、答えた。
「いえいえ、とんでもございませぬ。
相手の身分が低かったため、親を始め、親類縁者にもこぞって反対されました、『世間体が悪い』と。
ですが、最後には、強引に押し通しましたよ」
「ほう……」
初めてタナトスの表情が動き、それに後押しされて、プロケルは話し続けた。
「強引と申しましても、それがしも魔界の貴族の端くれ、色々としきたりもございます。
考えましたあげく、方々に頼み込み、相手を、さる貴族の養女にするという形を取って、身分を釣り合わせましてな。
それにて、ようよう、婚姻に漕ぎ着けた次第でございますよ。
ははは……いやはや、お恥ずかしいことで。若さゆえ、出来たことでしたな。
今では、到底、あれほどの気力はございませぬよ」
元公爵は、頭をかいた。
「別に恥ずかしいことではなかろう。
ふん、俺が思っていたのよりは皆、色々と苦労しているものなのだな……」
タナトスはつぶやく。
「では、やはりどなたか、意中の方がおいでなのですかな?
あなた様は魔界の王、いかような女性でも思うがままでしょうに」
「それが、そうもいかん……どうも、とことん嫌われてしまったようでな。
情けないことに、どうすればよいのやら、俺にはさっぱり分からん……」
タナトスは、暗い表情で額に手をやり、ため息をついた。
(おやおや、これはお珍しい、女性のことでお悩みとは。
だが、いい機会だ。パイモンが気をもむ、跡継ぎの心配もこれでなくなるやも知れぬ)
プロケルはそう思い、続けた。
「左様でございましたか。差し支えなくば、お相手をお教え願えませんかな」
「……聞いたら驚くぞ。そして、おそらく、貴様もやめろと言うだろう……。
俺自身も忘れた方がいいと思い、何度も諦めようとしたのだが、あの女の面影がどうしても頭を離れん……」
タナトスは頭を振り、再び深い息をついた。
「ともかく、ご事情をお話し下さいませ、それがしは口を挟みませぬゆえ。
すべてをお聞き致しましてのち、意見など述べさせて頂くとしましょう」
「そこまで言うのなら、聞かせてやる。
俺が想っている相手とは、“黯黒の眸”だ」
途端に、縦長の虹彩が円盤のように広がったが、プロケルは約束を守り、口をつぐんでいた。
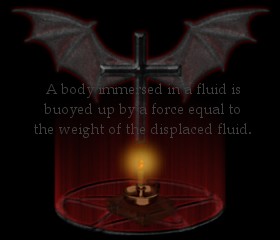
「驚いたか? 無論、“黯黒の眸”の化身だがな。
一年半ほど前、ほんの気紛れで女の体を創ってやったのだが、ヤツの物質化能力を、俺は見くびっていた。
分かるか? ニュクス……“夜”と名付けたその女を、初めて見た俺の驚きが。
あいつは夢の女だった。俺の理想、そのものの姿をしていたのだ!
衝撃から立ち直ると、俺はニュクスを連れ歩いた。
皆の
……初めは、ただそれだけだった。
だが、時が経つうち、ニュクスを、かけがえのないものと考え始めている自分に気づき、俺は驚いた。
相手が一般の魔界人ならまだしも、前科ある“黯黒の眸”……。
共にいる時間が楽しければ楽しいほど、心の中の疑念は膨らみ、大きくなった。
俺も、ヤツに操られているのではないか、とな。
そこで、俺は強力な結界を張り、ニュクスも遠ざけることにした。
ところが……だ。
影響を絶ったと言うのに、その面影は、離れれば離れるほど俺を悩ませた。
あいつが、俺を操っていたのではなかったのだ。
そこへ、ダイアデムが来て、ニュクスは精霊、赤ん坊と同じだから、独り立ちするまでは面倒を見ろ、無責任だとわめきおってな。
そこで、俺は心を決めた。ニュクスに謝罪し、そばにいてくれと頼んだ。
しかし、あいつは俺を拒絶し、姿を消してしまったのだ。
汎魔殿からは出られまい。とすれば、地下迷宮に隠れたのだろう。
だが、あれほどの広大さを誇る迷宮、さらに、“黯黒の眸”が気配を断つのに
──とまあ、こういう次第なのだ。
笑うなり、ののしるなり、好きにするがいい、プロケル」
「……何とまあ……」
プロケルはそう言ったきり、しばらく二の句が継げなかった。
「ふっ、あきれ果てているのだろう、貴様?
俺としたことが、馬鹿な罠にはまったものさ。サマエルのことを笑えんわ。
その上、自業自得で逃げ出されたというのに、忘れられんのだからな、まったく情けない」
タナトスの唇の端が、自嘲気味にほんの少し持ち上げられたが、眼はまったく笑ってはいなかった。
「左様でございましたか……」
「パイモンに言っておけ。
俺がわめこうと黙ろうと貴様らには関係なかろう、勝手につまらん会議でもやっていろ、俺はそのすべてに同意してやると。
辞めさせたいのなら、さっさと
「されど、諦めなさってよろしいのですかな、タナトス様」
「仕方あるまいさ、どうすることも出来ん。
俺が、心から愛した者はいつも、手が届かんところに行ってしまうと決まっているようだ……」
タナトスの緋色の眼は、遥か遠くを見つめていた。
プロケルは、この魔界王のことを、いつも強気の自信家で、やることは強引で、けれど、本当は優しいところもちゃんとある、元気なやんちゃ坊主のように思っていた。
なのに、今、目の前にいるタナトスは、まるで別人のように
プロケルは、自分の子を叱るとき同様、琥珀色の瞳をカッと燃え上がらせた。
「左様に気弱なことでどうなさるのですか、タナトス様!
あなた様は魔界の王、お相手は魔界の至宝の片割れなのですぞ、王妃になさるかどうかは別としても、何も問題はございませんでしょう。
それを、あなた様らしくもなく!」
今度はタナトスの緋色の眼が、大きく見開かれた。
「プロケル、貴様は反対せんのか?」
「わたくしには、陛下のご健康の方が大事でございますよ。
あなた様が、その女性を得られてお元気になられるのでございましたら、多少の身分差やその他の雑事など、どうでもよいこと」
タナトスは肩をすくめた。
「そんな風に言うのは、貴様だけだ。
俺がニュクスを連れて歩くたびに、誰彼となく騒ぎ立てて大変だったのだぞ。
それを、身近に置くことにしてみろ、どうなるか……」
「おやおや、これは、魔界全土を
陛下は、いつから、周りの雑音に、ご意見を左右されるようになられましたので?」
プロケルが澄まして言うと、タナトスはあっけにとられ、それから大声で笑い出した。
「あっはっは! 貴様の言う通りだ、俺としたことが、まったくどうかしていたな。
くっくっく……ああ、久しぶりに笑った、礼を言うぞ、プロケル」
「まあ、女性の扱いに関して言えば、たしかにタナトス様は無器用でいらっしゃいますな。
では、どうか、それがしめに、人界へ通じる魔法陣の使用をご許可下さい。
サマエル様に、ご相談申し上げて参ります、もちろん内密に」
「サマエルに、だと……?」
せっかく機嫌がよくなりかけたタナトスの眉間に、稲妻めいたものが走る。
百戦
「サマエル様は、“焔の眸”殿を
いわば、宝石の精霊との結婚生活に関しては、ご先輩に当たるのですぞ。
それに、“焔の眸”殿にならば、“黯黒の眸”殿が、あなた様から逃げておいでになるその理由が、お分かりになるやも知れませぬ。
ご許可願えませんでしょうかな?」
タナトスは少し考えた。
「ふん……貴様がどうしても行きたいというのならば、止めはせん。許可してやる」
「ありがたき幸せ。では、さっそく行って参ります」
プロケルは再び膝をつき、礼をする。
そして、すぐに立ち上がり、時空の門が設置してあるサマエルの子供部屋に急いだ。
魔界王タナトスは、その背中を無言で見送った。