13.破滅の足音(3)
ここにおいて、二万年前に予知されたシンハの予言は、現実のものとなったのだった。
それまで、常に吹きつけていた熱い風が、ぴたりと止まり、照りつけていた太陽の輝きまでもが、少し色
「ダイアデム……死んじゃったなんて、ウソ、ウソだ……。
またぼくをからかって、どっかから、ぴょんって飛び出してくるつもりなんだろ……?」
涙が幾筋も、リオンの頬を伝って、滴り落ちてゆく。
「わたし、たったの一日で、大事な人を二人も亡くしてしまったわ……」
ライラも、悲しみで胸が一杯になり、涙がとどめなくあふれた。
「シェミハザ、お前は天界に帰ってミカエルに報告するがいい、“焔の眸”はたしかに処刑されましたと。
それとも、既に報告済というところかな?」
嘆く少年達とは対極的に、サマエルの口調は淡々としていて、何の感情も現れてはいない。
表情もまた、さざなみ一つない透き通った湖面のように、平静そのものだった。
セラフィには、フードの奥に隠された顔自体は見えなかったものの、第二王子の態度を不審に思った。
自分でさえ不覚にも、涙が込み上げて来そうになったというのに、この王子はなんと冷淡なのだろうと。
魔界王になれなかった上に追放までされて、王位の象徴である“焔の眸”には、あまりいい感情を持っていなかったのだろうか? と。
「サマエル様……」
「どうかしたのか?」
何一つ変わったことなど起きていないといった風な、淡白な返事が返って来て、熾天使は二の句が告げなくなった。
「い、いえ、何でもございません。仰せの通り、ただ今の
それを聞くと、ライラと抱き合っていたリオンは、涙をふくのも忘れて振り返った。
「えっ、じゃあ、ダイアデムの予言も、お前が謀反企んでるってこともバレちゃってるの?
なんでお前、平気でいられるんだ?」
「あー……こほん、大丈夫でございますよ、リオン様。
先ほど、結界を強化したとき、そういう都合の悪いことは自動的に削除し、差し障りのない映像と音声にすり替わるよう、細工を施しておきましたので」
咳払いでごまかしたものの、天使の声は少々乱れ、眼もうるんでいた。
「存外、抜目がないのだな、貴様。
まあ、それくらいの用心あってこそ、謀反の成功も望めると言うものだが。
シェミハザ、今後はよしなに頼むぞ。
俺の手足となり、“焔の眸”の仇を討つ手助けをしてくれ」
そう話すタナトスの眼差しは暗く、声も沈んでおり、天使はその様子に衝撃を受けた。
無論、プロパガンダもあるのだろうが、天界では冷酷無比と
対する天界の高位者は、低位の者をいたわる気持ちなど、まったく持っていない。
魔界人の方が、天界人よりも遥かに情があると知った熾天使は、自分の選択の正しさを確信した。
それだけに、“焔の眸”の最期は、仲間の死と同等に思われて、彼は余計に悲しかった。
「タナトス様、お
シンハ殿に変化する時、少々時間をかけて頂きましたので、結界に細工する暇が取れたのです。
おそらく、あの方はわざと……」
「……そうだったか」
「はい、“焔の眸”殿は恩人にも等しいお方です。何なりとお申し付け下さいませ」
セラフィは、うやうやしく頭を下げた。
会話に加わらずにいたサマエルは、つぶやいた。
「……“焔の眸”はなぜ、わざわざ私に消されたがったのだろう。どうして。
それほど罪の意識が強かったのか?
あるいは……いや、先祖ベリアルとの約束に、そうまで縛られることもないし、もう恨んだり、憎んだりはしていないと言ったのに」
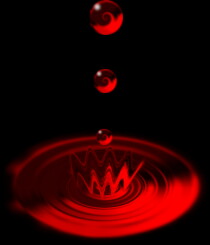
彼が首を振った時。
それまで、ただずっと、リオンの胸の中で声を忍んで泣いていたライラが、涙に濡れた顔を上げた。
「お分かりにならないのですか? サマエル様。
ダイアデムは、あなたが好きだったのですわ、だからどうしても、とどめはあなたに刺してもらいたかったのでしょう」
サマエルは息をのみ、彼女に指摘されて、初めてそのことに思い至った自分にあきれた。
「……ああ、そうか。愚かだな、私は……」
「先ほどの話にしても、大好きな人にあんなこと、言えるわけがないですわ。
ましてや、気位の高い彼のこと、あなたに知られるくらいなら、死んだ方がましだと思ったのでしょう。
それでも、話してしまったのは、もう最後だから……せめて、本当のことを知っておいてもらいたいと、そう思ったに違いありません。
きっと、わたしでも同じことをしたと思いますわ……」
サマエルは眼を伏せた。
「……そうだね。今になって思い当たるよ、ライラ。
ダイアデムは、罪を告白する時、とてもためらっていた。いつもの彼らしくもなく。
消滅が恐いのだろうと、その時は思ったのだが……。
彼は、私の魔力を封じた話と、自分のトラウマ、どちらを話すべきか思い迷ったあげく、消えたくないと思いつつも、私に憐れみをかけられるくらいならと、辛い決断をしたのだね……。
可哀想なことをしてしまった……」
タナトスは肩をすくめた。
「ふん、貴様の魔力を封じていたのが“焔の眸”だったとはな。
しかし、ヤツの気持ちに今頃気づいたのか、間抜けめ。
ライラの言う通り、あやつは“王の杖”、プライドはかなり高かったからな。
あのトラウマを知り、今後はどう接したらよかろうと思い迷っていた俺に、ダイアデムはこう言い放ちおった。
『自分に憐れみなど掛けたら、速攻で魔界王をクビにしてやる』、とな。
だから、俺も、今まで通りに扱ってやることにした。
それに、あいつも同情されまいとして、余計に生意気な口を利きおってな……」
「ああ、それで。でも、ダイアデムらしいや」
「本当にそうね、リオン……」
ライラはリオンにうなずいてみせ、それからサマエルに言った。
「さっき彼は、あなたが自分をペット程度にしか思っていない、と繰り返していました……。
でも、わたしには、彼が、必死にあなたを思い切ろうとしているようにしか、見えませんでした。
それに、予言の当たり外れなど、どうでもよかったのだと思いますわ。
最後は、あなたに魔力のすべてを捧げて、消滅したかった。
でも、それが無理と分かった時、女性に変身してみせることで、気持ちを伝えようと……。
それなのに、分かってあげなければ、ダイアデムが気の毒過ぎますわ」
意地っ張りのダイアデムが、素直に好きだと打ち明けているわけがない。
だから、サマエルは、彼の気持ちを知らないのだろうとライラは思い、自分が代わりに伝えようとしたのだった。
しかし、彼女の思いに反して、魔界の王子は、静かに否定の身振りをした。
「知っていたよ、ライラ。彼が、私を好いていてくれるということは……。
これでも鈍くはないつもりだし、本人から直接、聞きもしたのでね」
「まあ、あのダイアデムが……?」
まったくのすれ違いではなかったと知った王女は、驚くと同時に胸をなで下ろした。
「思い出してみると、子供時代、父にさえ
そこで、私は無邪気に、彼は私のことが気に入っていて一緒にいてくれるのだと思い、だからあの頃、私は彼を、とても好きだった。
彼さえいてくれれば、他に何もいらない、と思うほどに……。
なのに──なのに、私の魔力を封じ、悲しみと苦しみの元凶を作ったのは、彼だったのだ。
彼の告白は、私に、とてつもなく大きな衝撃を与えた……。
幼い日々……あれほどシンハを信じ、すがって生きていたのに、彼はただ封印が解けないよう、また、万一解けてしまった時、すぐにも私を殺せるよう、見張っていただけだったのか?
そう思ったら、奈落の底に突き落とされたようで、目の前が真っ暗になってしまった……」
サマエルは暗い表情で、ふっと息を吐く。
シェミハザは、自分の勘違いに気づいた。
サマエルは冷淡なわけではなく、“焔の眸”と仲違いをしていたわけでもなかった。
あまりにも衝撃が大き過ぎ、
タナトスも、それには気づいていた。
子供の頃、弟にもう少し優しくしてやればよかったかと後悔したが、後の祭りだった。
サマエルは、兄の視線に気づくと首を振り、話を続けた。
「だが、私は疑問を持った。
なぜ、シンハは、見張るだけで私を殺さなかったのだろう、機会はいくらでもあったのに?
……そう考えたら、彼の気持ちが分かったのだ。やはり、私を好いていてくれたのだと。
初めこそ、監視のつもりだったかも知れないけれどね。
だから、尋ねてみたのだが、彼の返事はそっけなくて……。
『お前なんか嫌いだ』の一点張りさ……」
「そう言ってたね。ダイアデムは意地っ張りだから。
本人は、隠してたつもりなのかも知れないけど、あの態度じゃね。
ぼくにだって、バレてんのにさ……」
リオンが言うと、サマエルはほんの少し微笑んだ。
「そうだな、リオン。
あの日、お前を締め出した後、芝居のためにと女性に変身させた時、本音を聞きたくて再び尋ねてみたのだが、返事はやはり同じでね。
それで、私もつい意地になって、無理矢理認めさせてしまったのだ。
私の理想の女性を具現化したフェレス……彼女の美しい唇で『大っ嫌い』と言われるのは、正直なとこ辛くてね……。
あの夜、私の強引さに負けてしまった後で……フェレスは、私の胸の中で泣きじゃくったよ。
『言いたくなかった』と……。理由を聞いてもどうしても言わなかったが、今なら分かる。
本当の心を知られてしまえば、私が手心を加えたくなり、とどめを刺せなくなると思っていたのだね。
実際、その通りだったのだが。約束しておきながら、守れなかった。
やはり軟弱者だな、私は……」
「そんなことない! サマエルは、優しいだけだよ!」
「サマエル様……」
いきさつを聞いた王女は切なくなり、その眼からは再び涙があふれた。
「泣かないでおくれ、ライラ……。
なんだか私は、女性を泣かせてばかりいるような気がしてきたよ……」
雨にしっとりと濡れた若葉のような、深い緑の瞳を見ているうち、第二王子がようやく、悲しみに身を任せる気になったときだった。
“まさしくその通りだな!
だが、そなたが泣かすのは女性ばかりではあるまい、魔性の者よ。
サソリの毒針のごとく汚れた
──そなたのゆくところ、空を暗黒の闇が覆い、人々の顔は悲しみで曇り、鳥は歌わず、草木も芽吹かず、作物は実を結ぶこともなく、立ち枯れてゆくのだからな……!”
盛んに言いはやして世間に広く知らせること。