13.破滅の足音(2)
「他に方法はないの!? そうだ、話し合いで平和的に解決しようよ!」
リオンの提案に、天使は首を横に振った。
「
それに、彼を処刑しなければ、平和どころか戦争が始まってしまいますよ」
「え、戦争!?」
「そうなれば、人界にいる魔族の命運は尽きる。おそらく、皆殺しだろうな。
魔界には結界があるが、人界の同胞は、まったくの無防備。
つまり、現状では、人界で細々と暮らしている同族達──詳しい数は不明だが、混血児を含めると一万人ほどはいるだろうと推測される──その彼らを、人質に取られているも同然なのだよ」
淡々とサマエルは言った。
「ええっ、皆殺し……一万人も!?」
リオンは青ざめた。
魔界の王は、いかにも悔しげに、拳を掌に打ちつけた。
「くっ、今は駄目だ、最終的な準備が整うには、あと二千年かかる!
その間は、どうあっても戦は避けねばならん!」
「二千年とはまた……」
熾天使は眼を見張る。
「どうして、そんなにかかるの!? 何で、今すぐ準備出来ないのさ!」
「うるさい、もうその話は終わりだ、どけ、リオン。
気は進まんが、俺がやる。こいつの主人であり、王たる者の務めだ」
タナトスが、詰め寄る少年を押しのけたとき、入れ代わるように、サマエルが彼の前に立ちはだかった。
「待ってくれ、その役目、私に譲ってくれないか。
シンハは、私が生まれた朝、私に消される予知夢を見たのだよ。
それで、予知通りにしてくれと頼まれていてね」
「……何? 初めて聞いたぞ、そんな話」
「彼はごく最近まで、私と彼自身の記憶を閉じていたから。
それゆえ、私のわがまま、お聞き届け頂け願えませんでしょうか、魔界の王、タナトス陛下」
弟王子は、静かに片ひざをつき、王に対する正式な礼をした。
「ちっ! こんなときだけ尊称で呼ぶな!」
怒鳴りつけても、サマエルは頭を下げたままでいた。
眉をしかめた魔界王は振り向き、“焔の眸”に問いかけた。
「ダイアデム、この際だ、もう予言の一つや二つ、外れたところでどうでもよかろうが?」
当然、いつもの憎まれ口が聞けるものと思ったのだが、返って来たのは、紅毛の少年の深い一礼だった。
タナトスは面食らった。
プライドが高い“焔の眸”の化身が、彼に頭を下げたのは、イナンナとの別れの時以来である。
それにしても。
以前のダイアデムは、弟を見るたび怯え、逃げ回っていたが、実はこれほど想っていたのか。
ひょっとしたら、イナンナに対するよりも深く。
おそらく“予知”うんぬんは名目に過ぎず、どうせ消されるならと、心に決めていたのだろう。
「ふん、ならば、好きにしろ」
“焔の眸”の心情を理解した王は、渋々といった風を装い、許可した。
「……心よりの感謝を」
サマエルは、深々と頭を下げてから立ち上がり、ダイアデムに向けて手をかざす。
宝石の化身は、覚悟を決めたように深呼吸をし、眼を閉じた。
「──パーディション!」
少年の体が青白く発光し、光が王子の掌に吸い込まれていく。
表情も変えず、サマエルが魔力の吸収を続けるうち、化身は、ふらりと倒れかかった。
リオンは、思わず前に飛び出し、紅毛の少年を支えた。
「もうやめて、サマエル!」
「邪魔すんな、あっち行ってろ、ガキ!」
彼をさえぎったのは、意外にも、ダイアデム自身だった。
しかし、リオンはひるまない。
「嫌だ、絶対どかないよ!」
「結構ガンコだな、お前。けど、何でオレをかばう?
いっつも、バカにしてばっかいたのにさ。
それに、オレは、魔物と言ったって、血も通ってない宝石に、魔力が宿っただけのもんだ。
魔界の王権の象徴、と言やぁカッコイイけど、実際にゃ使い魔以下。
清純な女のコから見りゃ、たしかに薄汚れたバケモノさ……」
「それは違うわ! もう許してくれたはずでしょう?」
「違うよ! いつまでも根に持ってないで、許してあげて!」
ライラとリオンは、同時に叫んだ。
ダイアデムはうつむいた。
「根に持ってんじゃねーよ、腹立てたのは、図星だったからさ。
オレは、バケモノどころか、生きてさえもいない、ただの物体なんだから」
「そんなこと言うなよ!
ぼくは、お前が魔物でも宝石でも、それ以外の何だって、ちっとも構わない!
お前は、色々教えてくれた。からかわれたときは頭に来たけど、百年も独りぼっちでいた後だったから、同じ年頃の子とケンカしてるみたいで、何だかうれしかったんだ……。
ぼくは、お前のこと、友達だと思ってるから」
「やっぱお前、サマエルと性格似てるよ。すっげーお人よし……」
眼を潤ませるリオンから顔を背け、ダイアデムはつぶやいた。
ライラも、懸命に涙をこらえて言った。
「あなたのお陰で、ファイディーは救われ、わたしは自分の気持ちに気づいたわ。
それに、いくらイナンナの子孫でも、わたしを助けなければならない義務は、あなたにはないのに、王女だからと、思い上がっていたのね。
それに気づかせてくれたことにも、お礼を言わなくては。ありがとうございました」
彼女は、深く頭を下げる。
ダイアデムは息を呑んだ。
遠い昔、直接聞くことが出来なかったイナンナの声が、過去から
かつて愛した人の面影を色濃く残す少女を、彼は涙にかすむ眼で、ただ見つめることしか出来なかった。
そんな彼の心情を察したように、サマエルが言葉を継ぐ。
「魔力とは意志の力、すなわち、“想う心”の力だ。
だから、魔力が宿った時点で、無生物のお前も心を持った……つまり、生物と同等の存在になったのだ。
それから、これだけは明言しておこう。
私は、お前をただの石だとか、使い魔などと思ったことは一度もない。
……あの時、心にもないことを言うのは本当に辛かった、許してくれ」
王子は深く
刹那、ダイアデムの瞳に希望の光が灯ったが、たちまち、それは長いまつげの陰に隠された。
「……ホントに、そう思ってんのか? 最期だからって、心にもないこと……」
そのつぶやきの途中で、タナトスが強引に意見を挟む。
「ああ、たしかにな。
王にさえ文句を言う小生意気な奴だが、俺も貴様を単なる石と思ったことはない。
もし、そう思っていたら、貴様がタメ口を利いた瞬間に、砕いていたぞ」
(えっ、マジ……?)
サマエルだけでなく、自分が王に選んだ相手にもそう言ってもらえたことで、ダイアデムは驚き、かつ喜んだが、それを素直には出さない。
「へっ、何だよ、お前ら。安っぽい同情なんてごめんだぜ!
さあサマエル、さっさと終わりにしてくれ、中途半端じゃ辛れーんだからよ」
「ダメだよ! サマエル、何か彼を助ける方法はないの!」
必死の思いでリオンは叫ぶが、第二王子は否定の身振りをした。
「残念ながら、ない。分かっておくれ、私も辛いのだ……」
「もういいって、リオン。オレの使命は、魔界王家の者を守ること。
そのためにある予知力が、オレはもう、お払い箱だって言ったんだからさ」
いつも通りの軽い口調で、ダイアデムは言う。
「お払い箱なんて……」
「それに、約束したよな、サマエル。必ずお前がやってくれるって」
「…………」
無言でうなずいたものの、これほど早く、その時が来るとは思っていなかった王子は、胸が締め付けられるような思いを味わっていた。
“焔の眸”を魔界に帰しても、その場しのぎにしかならず、いずれこうなることは、彼にも分かっていた。
ただ、宝石の化身への想いを断ち切るための時間が、彼は欲しかったのだ。
「……ああ、駄目だ。済まない、やはり私には出来そうにもない。
自分から言い出しておいて悪いが、タナトス、代わってくれないか」
サマエルの声は、抑えようもなく震えていた。
「何だと!? 今さら、俺にやれと言うのか、たわけ者が!
約束したのなら、しっかり最後までやってやれ!」
軟弱者が嫌いなタナトスは、緋色の眼を光らせ、冷酷な口調で言い返した。
しかし、一方で、弟が弱々しいからこそ、“焔の眸”は心魅かれたのかも知れないとも思った。
トラウマのせいで、自分のような荒っぽい男には心から打ち解けられないのだろうと。
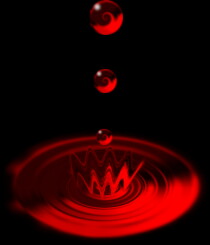
「……やっぱ、ダメか。しょーがねーな」
ダイアデムは、ぽりぽりと頭をかき、ため息をついた。
その体がまた、紅く光り始める。
「よせ! 消滅が早まるだけだぞ!」
サマエルは思わず叫ぶ。
「お前がダメだってんなら、自分でやるっきゃねーだろ?」
光りながら、宝石の化身は言う。
「そんな、やめてくれ!」
「やらせておけ、サマエル」
タナトスは、弟の腕を捕らえた。
「放せっ、タナトス!」
「たわけ者、ヤツの気持ちも察してやれと言うのに!」
二人がもみ合ううちに、光は消え、そこにうずくまっていたのは、紫がかった紅い髪を床に這わせ、華奢な体を紫のドレスに包んだ女性だった。
白い肌は青ざめ、訴えかけるように第二王子を見る瞳の鮮やかな紅い色は、急速に薄らいでいく。
瞳の金色の炎もまた、今にも消えそうに揺らいで、苦しげにあえいでいた。
フェレスは、色あせた唇を震わせ、サマエルに向かって手を差し伸べるのがやっとだった。
もはや、声を発することも出来ない。
「──フェレス!」
サマエルは、兄の腕をもぎ放し、駆け寄って彼女の手を取ろうとした。
だが、一瞬遅く、フェレスの体は再び光に覆われる。
そして、彼の手に触れたのは、血が通った柔らかな女性の肌ではなく、冷たく硬く滑らかな魔界の至宝、“焔の眸”だった。
すでに紅い色を失い、透明になった宝石の内部には、まだ黄金の炎が細々と揺らいでいたが、皆が見つめる中、ついに炎は静かに燃えつき、消えた。
「さらばだ、“貴石の王”よ。
長の年月、魔界王家に尽くしたその功績は、王家が存続する限り、
俺も、貴様のことは忘れん」
タナトスが、重々しく言った。
宿る魔力がなくなれば、“焔の眸”は、単なる石と成り果て、シンハを筆頭とした化身達もまた完全に消滅し、二度と戻っては来ないのだ。
しばし、サマエルは言葉もなく、輝きを失った宝石を両手で抱え込んで、甦らせようとでもするかのように、ただ凝視し続けていた。
それから、彼は意を決して顔を上げた。
「惑星が見る、夢の結晶“焔の眸”よ。
世界が
混沌より再び星が生まれ出ずる時、今一度、夢の結晶として顕現するがいい、その時には私も生まれ変わって、再び相まみえよう……。
さらばだ、シンハ、ダイアデム、フェレス……。
私は、いつも夢に見ることだろう、お前達と、そして……紅い、禍々しいまでに美しく輝くお前達の本体、“焔の眸”を……!」
サマエルは、宝石を持つ手を高々と差し上げた。
緋色の瞳に、闇の炎が黒々と燃え上がる。
「さらばだ。
──ディザルヴ!」
刹那、
「危ない!
──カウンターベイル!」
思わず、リオンは飛びすさって結界を張り、ライラを守った。
他の二人も、同様に結界を張り、防ぐ。
弟王子は、ただ一人、まったく防御しなかった。
刃のごとく鋭い幾千もの欠片が、四方八方に飛び散り、彼の顔や手に無数の傷を付けた。
ローブがずたずたに切り裂かれ、はためく。
だが、血が滴り落ちるのも意に介さず、彼は黙して立ち尽くしていた。
飛び散った破片は、氷が溶けるように、砂漠の紅い砂に吸い込まれてゆく。
氷と違うところはただ、濡れた跡を残さないことだけだった。
サマエルは、そのまま両の拳を固く握りしめていた。
傷がすべてふさがってしまうと、彼はゆっくりと拳を開く。
しかし、何も残っているはずもなく、彼は静かに、手をローブにしまい込んだ。