13.破滅の足音(1)
「ダイアデム。こうなってしまっては、行く道は消滅より他にはない……」
サマエルの声は、かすれていた。
「何で、彼が消されなきゃいけないの、ただ、ぼくらを助けただけなのに!」
リオンが先祖に詰め寄ると、ダイアデムは、彼を叱りつけた。
「サマエルを困らせんじゃねーよ!
魔物は、人間に手を出しちゃいけねーってのが掟だって、教えただろーが!
オレが殺ったんだから、オレが罰受けんに決まってんだろ」
「だって、本当は、とどめ刺さなきゃいけなかったのは、ぼくなんだよ……」
リオンはうなだれた。
「ご免なさい、わたしのせいだわ、わたしがあなたを召喚してしまったから!
サマエル様の下へ連れて行ってと、無理に頼まなければ、こんなことには……!」
輝く銀髪をなびかせてソファから降りたライラは、宝石の化身の手を固く握った。
涙を溜めた美しい緑の瞳に、イナンナの面影を見たダイアデムは首を振り、優しく王女の手を外した。
「いいや、キミのせいじゃない。予言された未来は変えられねーんだ。
キミに呼ばれなくっても、結局はおんなじことになったさ」
「嫌だよ、大昔の予知なんかで、未来が決められてしまうなんて!
一生懸命やれば、必ず未来は変えられる! いいや、絶対変えてみせる!」
どうにも切なくなって、リオンは叫んだ。
しかし、宝石の精霊はかぶりを振るだけだった。
「……ガキは無邪気でいいよな、けど、どう頑張っても変えられねー時もあるんだ、覚えとけ」
それから、ダイアデムは、天界の使いに視線を向けた。
「おい、天使。シンハも別れを言いたいってよ。変化するぞ、いいだろ」
セラフィは顔色を変えた。
「い、いけません。それは、あなたの戦闘形態なのでしょう。
変身したところで逃げられはしませんよ、何十人もの天使が砂漠を取り巻き、強力な結界を張り巡らしているのですから」
宝石の化身は、思い切り険しい顔をした。
「逃げるだぁ!? 何でオレが、ンなみっともねーことをしなきゃなんねーんだよ!?
オレにだって、魔界の王位の象徴としてのプライドってもんがあんだぞ、なめんなよ、バカ天使!」
ののしられても、天使は警戒を解かない。
「何と仰られましても、駄目なものは駄目です。
もし、逃げられでもしたら、わたくしのみならず、人界にいる天使達全員が、連帯責任を取らされてしまうのですから」
「そんならさー、鎖で縛るとか、檻に入れっとか、結界を強化するとかよ、気が済むまで何でもやりゃあいーじゃん。
それにだなぁ、ドジ踏んで天使をクビになっちまったら、魔界で拾ってやってもいーんだぜ?
そーすりゃ、あんたは堕天使、めでたくオレらの仲間入りってわけだ。
いい考えだろ?」
ダイアデムはニヤリと笑い、茶目っ気たっぷりに片目をつぶって見せた。
熾天使は、思わず息を呑んだが、すぐに立ち直り、余裕を見せるように笑みを浮かべ、言い返した。
「からかわないで頂きたいものですね。
それとも、それがかの有名な、魔族お得意の“堕落への誘惑”なのですか?
いずれにせよ、ミカエル様がお聞きになったら、激怒されて……」
「──けっ、その、お偉いミカエル“様”が怒り狂ったって、痛くもかゆくもねーぜ!」
少年は不機嫌そうに口を挟み、下唇を突き出した。
「──ったく神族ってのはセコイな、マジに最期だってーのに、別れも言わせてくんねーのかよ!」
「……分かりましたよ。
ミカエル様には怒られてしまうでしょうが、わたしとしても、天界の名誉は守りたいですからね。
しばしお待ちを。結界を最強にしますので」
熾天使は、根負けしたように許可を出し、同僚達に思念を送る。
腕組みしてそれを見つめるダイアデムの瞳は、いたずらっ子のように輝き、唇には微笑みさえ浮かんでいた。
「完了ました。逃げようとしても無駄ですよ、こうなったら」
強化を終えたセラフィは、彼に念を押した。
「しつけーぞ。
けど、こんな強えー結界ん中じゃ、時間食うな。気長に待ってろ、天使」
ダイアデムの体が、紅い光に覆われていく。
そこまでは、いつもと同じだったが、やはり変化はすんなりとはいかない。
その間、熾天使は優雅な動作で複雑な印を切りながら、呪文をつぶやき続けていた。
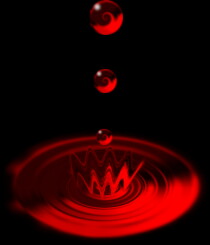
しばらく後、ようやく少年の体は爆発的に輝き、魔界の猛獣が出現した。
『聞くがよい、シェミハザ』
右眼を紅く燃え上がらせ、ライオンが第一声を放った途端、天使は驚き、がくんと
「な、何でそれを、わたくしの識別名をご存じなのです!?」
「……識別名って何? セラフィ」
リオンが不思議そうに訊いた。
「あ、ああ……ええと、……」
驚き覚めやらぬ顔で、熾天使は答えた。
「天界ではですね……大天使以外の天使は、使い捨ての駒なのです。
おそらくそのためなのでしょう、階級ごとに判で押したように同じ姿をしておりまして、下位の天使は番号で呼ばれますが、わたしのように多少地位がある者には、“識別名”が与えられます。
しかし、その名をなぜ、魔族であるシンハ殿が……」
『“予言の獅子”とも呼ばれる我が、汝の名を知ることなど、造作もない。
その名が、“見張る者”という意味を持つこともな』
魔界の獅子は、平然と言ってのける。
「そこまでご存じとは……!」
セラフィは大きく息を吸った。
ライオンは、紅い瞳に黄金の輝きを炎のように宿らせて、重厚な声で続けた。
『しかと聞くがよい、堕天使よ。
汝の企みは未だ時期
しばし身を慎み、疑念を招く言動は避けよ。
やがて、必ずや、好機は来たるであろう。
それまで汝の
汝が天界に籍を置きつつ、神族の動静を魔界へ流す方がより有効なるがゆえに』
「何ぃ、謀反だと!?」
「堕天使っても言ったよね?」
「……どういうことですの?」
サマエル以外は皆、意外な話に驚いた。
中でも、驚きの度合いが最も大きかったのは、熾天使本人だったろう。
“謀反”という言葉が出た瞬間、驚愕のあまり頭が真っ白になり、彼は膝をついた。
それでも、何とか気を取り直し、わななく手を胸に当て、臣下の礼を取る。
「お、お聞き及びの通りでございます、魔界王タナトス陛下、王弟サマエル殿下、並びにリオン殿下。
わたくしは、とうの昔に天界を見限っており、この機会に堕天する覚悟でおりました。
どうぞ、あなた様方の配下に……」
「たわけ、誰がそんな世迷い事を信じるか!
寝返った振りで俺達をスパイしろと、ミカエルに命じられているのだろうが!」
魔界王は乱暴に話をさえぎり、敵対する種族の男を睨みつけた。
「そう冷たくしなくともいいのではないか、タナトス。
彼のことを、神族としては例外的に話が分かると言っていたろう」
サマエルは、取り成そうと穏やかに口を挟んだ。
以前会ったときの態度から、この天使は、いずれ天界を離れるつもりなのではないかと、彼は密かに感じていたのだ。
「……う、まあな。だが、これが罠でないと言い切れるか?
あの腹黒い連中のことだ、どんな計略を仕掛けてくるか見当もつかん、簡単に信用してたまるか!」
タナトスは、熾天使の頭から爪先までを、いかにもうさんくさそうに眺め回した。
「お、お疑いはごもっともです、魔界王陛下。
すぐに信用して頂くのは無理なことと、覚悟は致しておりました。
ですが、シンハ殿もお認め下さいました。信じて頂くわけには参りませんでしょうか。
このような機会は、二度と巡っては来ないかも知れません。
どうか、わたくしめの切なる願いをお聞き届け下さり、配下にお加え下さいませ……!」
心臓が口から飛び出そうな思いで、熾天使は白いローブの胸に手を当て、深々と頭を下げた。
「むう……」
その
だが、ライオンは落ち着き払った眼差しで、彼を見返しただけだった。
「……ふん、では一応、信用しておいてやる。
本当に寝返ったかどうかは、貴様の態度を見ていれば、おのずと分かることだからな」
「ありがたき幸せでございます。
必ずやこのシェミハザ、お役に立ってご覧にいれましょう。
わたくしの忠誠は、永遠にあなた様のものでございます、偉大なる魔界の君主、黔龍王タナトス陛下」
またもセラフィは、うやうやしくタナトスに礼をする。
王は不機嫌な顔をした。
「陛下はよせ。俺はその呼び方は好かん。名前だけでいい」
「み心のままに。タナトス様」
熾天使は立ち上がり、魔界のライオンに頭を下げた。
「ご助言深く感謝致します、シンハ様」
『耐えるも忠義と心得よ、しからずんば、謀反も成功は致さぬ』
獅子は厳粛な面持ちで答えた。
「忍耐は美徳、でございますね。
今まで通り、ミカエルにこき使われながら、密かに牙を磨いでいることと致しましょう」
『汝の心がけに、必ずや報いはあろう』
「ありがとうございます」
またも礼を述べてから、堕天使は、心苦しげな表情になる。
「ところで、シンハ様、そろそろお時間でございます、皆様にお別れを……」
『相分かった』
ライオンは重々しくうなずき、タナトスの前に進んだ。
『これにて
汝には差し出た口を多々利きもしたが、我は魔界王家の長老格でもあるゆえ、汝のため、あるいは魔界のためを思い、その刻々に我なりに尽くしてきたつもりだ。
それにまた、
「そうだな。あいつといると、退屈だけはしなかったのは認めてやる。
さらばだ、“貴石の王”よ。長の勤め、誠に大儀であった。
時折手に負えんと感じることもあったが、貴様の忠誠心は疑いようがなかったぞ」
『かたじけなき言葉、痛み入る。冥土への良き土産となろう。
魔界王家の守護たる“焔の眸”は、これにて役目を果たし終え、今後は冥土にて、汝らの行く末を見守ることとなろうぞ、さらばだ、サタナエルよ』
シンハは次に、少年達の前に歩を進めた。
『朱の貴公子リオン、ならびに人界の王女ライラよ。
達者で暮らせ、さらばだ』
「さよなら、シンハ。ありがとう、お前のことは忘れない……」
「さ、さよ……なら……」
ライラの眼からは、もう涙があふれ始めてしまっていて、それだけ言うのがやっとだった。
『我が消滅は定め、悲しむには及ばぬ、王女よ』
シンハは、王女に優しく声をかけ、それからゆっくりとした歩調で、第二王子に近寄っていく。
サマエルは、その姿を眼に焼き付けておこうとするかのごとく、彼を凝視し続けていた。
『ルキフェルよ、取り立てて申すことはない。
汝は我が罪を許してくれた。
後は、“誓い”を守ってもらえさえすれば、それでよい』
「……そうだったね」
サマエルはフードの奥で、辛そうに眼を伏せた。
二人の会話は、ただそれきりだった。
『さらばだ』
“焔の眸”の体は、再び輝き始める。