1.“焔の眸”(1)
「おや……あれは……」
干草を積んだ荷車をロバに引かせ、ゆっくりと砂漠を進んでいた少年が、まぶしそうに額に手をかざしてつぶやいた。
一歩間違えば、命を落としかねない危険なこの土地も、長年ほとりに住む彼にとっては、自分の庭のようになじみ深いものだった。
遠目が利く少年の視線の遙か先には、黒っぽい鳥が一羽、大きく輪を描いて空を舞っている。
「砂漠ワシが、あんな風に飛ぶときは……大変だ、急がなくちゃ!
──ハイッ!」
日に焼けてはいるものの、なかなか整った顔立ちをしている少年は、手綱を振るい、ロバはスピードを上げ始めた。
もうもうと巻き上がる砂煙を残し、今にも壊れそうに激しくきしみながら、荷車は進む。
「……間に合うといいけど……」
栗色のまっすぐな髪が、砂漠の乾いた風になびき、少年は額の汗をぬぐった。
「あ、あそこだ!」
じりじりしながら、しばらく進んだところで、ようやく遠くに、目的のものが見えて来た。
半ば砂に埋れた、人影らしきものが。
「──おーい、そこの人、大丈夫!?」
口に手を当て叫んでみても、反応はない。
「まずいな……モウム、急げ!」
少年は眉を寄せ、ロバをさらに走らせる。
目の前に来てみると、倒れていたのは、やはり人間だった。
ロバを止める間ももどかしく、彼は水筒を引っつかみ、その人物に駆け寄った。
ほっとしたことに、弱々しくはあるものの、ちゃんと
「よかった、生きてる! しっかりして、水だよ、ほら!」
急いで上半身を抱き起こし、ひび割れた唇に水を流し込む。
「うう……」
相手はうめき声を上げたが、目は覚まさなかった。
「よいしょっと」
荷車に載せようと抱き上げる。
その体は予想外に軽く、はらりと落ちたフードの下から、美しい少女の顔が覗いた。
「わあ……すごく綺麗な女の子……」
少年の栗色の眼が、うっとりと少女に注がれる。
あまり日に焼けていないところを見ると、砂漠の住人ではないのだろう。
それから、彼は、こんなことをしている場合ではないことに気づいた。
「な、何をやってんだ、ぼくは! 急いで、家に連れて行かなきゃ!
早くしないと死んじゃうかも……!」
「その娘、置いていってもらおうか」
背後から、不穏な響きの声が聞こえて来たのだ。
「──!?」
はっとして振り返った少年が見たのは、薄汚れたローブを着込んだ、一人の男だった。
「ば、
とっさに、彼は、少女をかばうように荷車の前で両手を広げた。
漠賊とは、砂漠を渡る隊商や旅人を襲う強盗団のことである。
男は否定の身振りをした。
「いや、俺は賊などではない。その娘の相棒だ。
二、三日前のひどい砂嵐で、はぐれてしまったのが、ようやく再会出来たのだ、返してくれ。
オアシスの方向さえ教えてくれれば、後は、わたしが背負って行くから」
「えっ、相棒?」
「そうだ。オアシスはどっちだ?」
男は重ねて訊いた。
その声は、くぐもっていて、聞き取りにくい。
だが、少年が返事をためらったのは、それだけが理由ではなかった。
「ああ、これは、彼女を助けてくれた礼だ、取っておいてくれ」
「…………」
差し出された金貨に見向きもせず、少年は口を固く結び、相手を観察した。
男は、暑い日差しを避けるため、長い布を、頭だけでなく顔にまで巻きつけていた。
無論、そのこと自体は、珍しくはない。
しかし、勘がいい自分の背後に、いつの間にか忍び寄っていたという事実、そして何より、唯一外から見える、ただならぬ輝きを放つ眼が、どうしようもなく、少年の警戒心をかき立ててやまなかったのだ。
(……何か、嫌な感じ……。
こういうときの勘って、外れたことないんだよな……)
この男は只者ではないと、彼は直感していた。
「どうした? さあ、早く受け取って、オアシスを……」
そうとも知らず、さらに金を突き出す男の手を、少年は払いのけた。
「そんなもん、いらないよ!
大体、お前が、この子の相棒なんて、嘘なんだろう!」
「そう、嘘よ! そいつは、わたくしを追って来たの!」
そのとき、澄んだ声が砂漠に響いた。
荷車の少女が目覚め、叫んだのだ。
「──ちっ! ならば、力尽くでも!」
男は舌打ちし、少女に向かって行こうとする。
「逃げて!」
少年は叫び、男に足払いをかけた。
「うわっ!」
怪しい男は倒れ込む。
言われるまでもなく、少女は荷車から飛び降りて、よろめきながら走り出していた。
いったん倒れた黒衣の男は、砂を蹴散らして立ち上がり、少年を殴りつける。
「──痛っ!」
さらには、腰の大剣を抜き放ち、倒れた少年の襟首をつかんで、鋭い先端を鼻先に突きつけた。
「死にたいようだな、貴様」
背中を冷たい汗が流れたが、少年は歯を食いしばって問いかけた。
「お、お前、何で、あの子を追い回してんだ!」
男は肩をすくめた。
「死んでいく奴に話す義理もない。さあ、覚悟しろ!」
「わあっ!」
男が剣を振り上げ、彼が思わず眼をつぶった、その刹那。
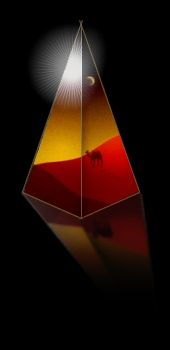
「なーにをしてるの、お馬鹿さんー!
わたくしは、ここよー!」
少女が、こちらに向かって、手を大きく振り回していた。
はっとして顔を上げると、男は、少年を砂にたたきつけた。
「ち、あっちが先だ!」
「やめろ、よせ!」
「邪魔だ!」
足にしがみつく少年を、邪険に蹴り付け、男は剣をぎらつかせながら、少女に追いすがる。
「逃げても無駄だぞ、こんな砂漠では隠れる場所もない!
大人しく、わたしと一緒に戻っていただこう、ライラ!」
「──嫌よ! 戻って、アンドラスに伝えなさい、力で人々を支配するなんて、長くは続かないと!」
息を切らしながらも、少女は叫び返し、走るのをやめなかった。
だが、疲れ切ったその足は、ともすればもつれがちで、男の確実な足取りに
見る間に、彼らの距離は縮まってゆく。
「……まずいな、どうにかしなきゃ……ん? そうだ、そろそろ時間だ。これで逃げられるぞ!」
少年は、荷車に飛び乗り、ロバに鞭をくれる。
「ごめんよ、モウム。でも、頑張ってくれ!」
出来るだけロバを急がせて、ようやく二人に追いつくという頃、周囲が暗くなり始めた。
「キミ、手を! 早く!」
彼は、追い抜きざまに声をかけ、伸ばされた少女の手を取った。
「ま、待て!」
叫ぶ男の腕をかいくぐり、干草の上に少女を乗せる。
「駄目、すぐ追いつかれるわ!」
焦る少女に、少年は手を振って見せた。
「大丈夫だよ! ほら!」
「え……ああっ!」
いつの間にか、風が砂を巻き上げ始めていた。
「毎日、この時間になると、ここら辺にはすごい砂嵐が来るんだ、こいつを使えば!」
風の
「きゃあ、上がって来たわ!」
「こっちに来て!」
少年は、少女と席を入れ替える。
「くそっ、砂で前が見えん!」
そして、眼をこすっている男の腹に、思い切り蹴りを入れた。
「──落ちろ!」
「うっ、くそっ」
干草の上に倒れ込んだ男は、すぐに跳ね起きて剣を抜き、眼を閉じたまま、闇雲に振り回し始めた。
「わっ、やめ……あぶ、危ない!」
揺れる狭い荷車の上、逃げ場はない。顔をかばう少年の腕や体に、否応なく傷がついていく。
「こ、こうなったら……!」
少年は、首から下げて服の中に隠していた鎖を引き上げ、涙滴形をした銀色のロケットに何事かささやいた。
刹那、男の剣目掛け、紫色の稲妻が走った。
「──ぎゃあっ!」
不意に全身がしびれ、たまらず荷車から転げ落ちる男を置き去りにして、砂嵐の中、ロバは
息を弾ませながら、少年は、女の子のいる席に戻った。
「……ふう、これで、もう、大丈夫だよ。
でも、もう、ちょっと、あいつと、距離、開けといた方が、いい、よね」
「は、はい……」
少女は、まだ硬い表情でなずく。
「あ、代わるよ」
彼は再び
風が強くなり、さすがに進むのが困難になると、彼は手綱を引き、汗だくのロバをねぎらった。
「よーし、モウム、もういいよ。ご苦労だったね、ありがとう」
「で、でも、こんなところで砂嵐に遭ったりしたら、死んじゃうわ!
二日前にも、死にそうな目に遭ったの! 荷物も全部なくして……」
少女はかすれた声でいい、がたがたと震えた。
「心配しないで。平気だよ、これがあれば」
彼は、ポケットから小さくたたまれた布を取り出し、広げ始めた。
「……そ、それは?」
「母さんが作った魔法具さ。これをかけると、どんな砂嵐でも、絶対飛ばされないんだよ」
少女は、緑の眼を見張った。
「……すごい魔法具ね。とても強い力を感じるわ……」
薄く引き剥がされた
少年は、それを荷車全体にかけ、すっぽりと覆い隠した。
「中で、嵐が過ぎるのを待とう」
「ええ」
二人は布の下にもぐり込み、干草の上に座った。
「この力が分かるってことは、キミ、魔法使いなんだね?」
「え……ええ、あまり力は強くないけれど……あ、大変、血が」
少女は、レースのハンカチを取り出し、彼の傷を押さえようとした。
「だ、大丈夫、平気だから。みんな浅いし、すぐ治るよ」
すると、少女は急に居住まいを正し、深々と礼をした。
「危ないところをお救い頂き、まことにありがとうございました。
わたくしは、……ライラと申します」
「あ、いや、僕はリオン……だよ、とにかく、よかったね」
いきなりのていねいなあいさつに面食らいながら、彼は答えた。
「リオン様ですね、本当にありがとうございました。
一時はどうなることかと、ゴホッ、ゴホッ」
言葉がノドにつかえ、ライラは咳き込む。
「……あ、ノドが渇いてるんだよね? ほら」
リオンは干草の中から水筒を見つけ出し、少女に渡した。
「──み、水!」
少女は眼の色を変えてそれを受け取り、口に当てた。
手が震え、干草の上にこぼしてしまいながら、むさぼるように水を飲む。
「少しずつだよ、慌てないで」
「……す、すみま……ゴホッ、ゴホッ」
熱風と砂に痛めつけられた喉に水が染みて、少女はむせ返った。
「大丈夫? この後、少し、ぼくの家で休んでいくといいよ」
少年は、その背中を優しくさすった。
前に旅人を見つけたときには、すでに死体となっていて、しかも、かなり砂漠ワシに食い散らかされた後だったから、少女が生きていたことに、彼はほっとしていた。
「……い、いえ、ご迷惑でしょうから……」
少女は首を横に振った。
「遠慮なんかいらないよ。ぼく、母さんが死んじゃってから、一人で暮してるんだ」
「でも……」
「疲れてるでしょう? それにもうすぐ暗くなる、夜、独りで砂漠を越えるのは無理だよ。
後で、ぼくが道案内してあげるから。
……ね?」
リオンは少女に微笑みかけた。
迷っていた旅人も、自分よりも年下に見える彼の、まだ子供っぽさの残る笑顔と優しい栗色の瞳、無邪気な声に、警戒を解いたのだろう。
「……それでは……少し、だけ……」
そう答え、ふらっと倒れかかった。
「あ、キミ、ライラ……!?」
リオンは驚き、揺さぶってみたが、少女は、完全に意識を失っていた。
「体が弱ってるのに、悪いヤツに追っかけられて、必死で走ったんだもんな。
早く、家に連れてって、休ませなきゃ」
干草にライラをそっと寝かせ、彼は、布の端をめくって見た。
砂嵐は通り過ぎ、太陽が顔を出しているものの、日暮れが近い。
彼は、ロバにも少し水をやり、手早く布をたたむと家路を急いだ。