9.緋色の花嫁(5)
ひとしきり、うれし涙にむせんだ後、プロケルは、胸元のポケットから絹のハンカチを出して顔をぬぐった。
「……いや、年を取ると、涙もろくなっていけませぬな、せっかくの良き日に、涙なぞ禁物。
ささ、どうぞ、お式を始めて下され。せっかくの日が
「そうね」
イシュタルはうなずき、それから、花嫁に眼を止めると、顔をしかめた。
「あらあら、ジル。髪が、くしゃくしゃじゃないこと。
……それに、そのドレス、ここの素晴らしい景色には、どうもそぐわないわねぇ……」
「そ、そんなに、くじゃぐじゃ……?」
慌てて髪をなでつける少女を横目で見ながら、イシュタルは魔法を唱えた。
「──ストーラ!」
瞬時に、花嫁の髪には
同時に、ドレスも変化した。
その間に、サマエルは、紅い宝石の髪留めを魔法で出し、乱れた髪を押さえた。
プロケルが手を打つ。
「おお、ジル! 素晴らしいですぞ!」
「ほんと、すごいわ、綺麗よ、ジル。さっきより、もっと!」
涙をふいたイナンナもまた、
「今度こそよくご覧なさい、ジル。
──カンジュア!」
イシュタルは、もう一度、鏡を呼び出した。
「わあ……これが、あたし?」
驚きながらも、心置きなく、ジルは鏡の中の自分を眺めた。
緋色のシルクサテンのしなやかなドレスは、とても彼女に似合っていた。
ドレスの裾部分には、キラキラした光沢が美しい、柔らかな半透明のオーガンジーが幾重にも重ねて用いられている。
それは、やせ過ぎの体型をカバーしているだけでなく、さりげなく豪華な雰囲気も
髪と同様、
もちろん、ジルにとって、これほど高級、かつ上品な衣装を身にまとうのは初めての経験だった。
「とても綺麗だよ、ジル。花のようだ。
ここで、式を挙げることにしてよかったよ。本当に素敵だ」
サマエルは、笑みを浮かべて心からの賛辞を述べ、少女は頬を赤らめた。
「お、お師匠様も素敵よ。でも、どうして、二人とも服が真っ赤なの?」
「花嫁衣装の緋色は、“血の最後の一滴まで、夫たる者に捧げます”という意味よ。
そして、花婿は……」
言いかけてイシュタルは、ちらりと甥を見た。
サマエルはうなずき、言葉を継いだ。
「花婿の紅い服装には、“この血のすべてを賭けても、妻たる者を守り抜く”という強い決意が込められているのだよ、ジル」
「ふぅん、そうなの……何か、すごいのね」
少女は言いながら、改めて魔界の王子を見つめた。
サマエルもまた、ここ一月ほどの試練によってかなりやつれていたが、そのことでいささかも容姿が衰えることはなく、かえって、その美しさは増しているように感じられた。
彼の
上着は、戴冠式に着用していたものよりかなり短く、膝くらいの丈で、ズボンも体の線に沿っていた。
胸ポケットには、咲き
「さあ、二人とも、こちらに来て。始めるわよ」
イシュタルが声をかけ、手招く。
「待つがよい、これを……」
そのとき、魔界王が歩み寄り、ジルに、ヴェルヴェット張りの小箱を手渡した。
「えっ、何……?」
彼女が開けてみると、透き通る濃い青色の石がはめ込まれた、金の指輪が入っていた。
「これは……? 見覚えがあるような……」
それを見たサマエルは、首をかしげた。
「……あ、そういえば、お師匠様のお母さん、夢の中で、こんな指輪してたよ」
ジルの言葉に、王子は眼を見開いた。
「えっ、では、これは……!」
ベルゼブルはうなずき、遠い眼差しをする。
「……左様、アイシスの形見じゃ。
必ず、ルキフェルの結婚相手にくれてやるようにとの、たっての望みじゃったゆえな……」
「陛下……ありがとうございます」
「どうもありがとう」
サマエルは、ジルと一緒に、深々とお辞儀をした。
「さ、お式を始めましょう」
イシュタルが促した。
それから、
アイシスの指輪には、魔法がかけられていて、持ち主の指にぴったりと合い、いつまでもフィットし続けた。

その後、イナンナは、プロケルに頼み込んで、もう一度、タナトスに会ったものの、やはり受け入れてはもらえずに、失恋の痛手を癒す旅に出た。
役目を果たし終えたプロケルも、二人を祝福しつつ、別れを告げて、魔界へと帰還した。
この半年後、人界に残ることを選択した一部の者を除き、魔族の撤収が終わると共に、二つの世界をつなぐ次元回廊は完全に閉じられることとなる。
「……何だか、すっごく静かね……。
イナンナも、プロケルさんも、いなくなっちゃって、あんなにしつこかったタナトスも、もう来ないなんて……」
数年ぶりに、屋敷で二人切りとなった晩、ジルは夕食を摂りながら言った。
「淋しいのかい、ジル」
サマエルの問いに、少女は首を左右に振った。
「ううん。でも、ちょっとヘンな感じ。急に、がらーんとなっちゃったから」
「……たしかにね……」
彼はうなずき、部屋を見回した。
家具の配置も数等も、一切変わってはいないのに、ついこの間までそこにいた人達の姿が見えず、話し声も聞こえない……それだけのことで、妙に広く感じられてしまうのが不思議だった。
「……そうだ。一つ、聞いてもいいかい?」
サマエルは、少女に視線を戻して尋ねた。
「なに?」
「本当によかったのかな、これで。
キミは、……タナトスと一緒にいたかったのでは……」
「──それはないわよ、絶対!」
最後まで聞かずに、彼女はきっぱりと言ってのけ、サマエルは微笑んだ。
彼はもう、フードで顔を隠してはおらず、当然、角も翼もそのままだった。
「……そう。だったら、心配しなくとも、そのうち、にぎやかになるよ、ここも」
「え? どうして」
ジルは首をかしげた。
サマエルの微笑が深くなる。
「私達に……子供が出来れば、ね」
「あ、そ、そっか……」
栗毛の少女は顔を赤らめた。
「でも、急ぐ必要はないよ、キミはまだ若いのだし。二人だけの時間も楽しみたいしね」
「う、うん、そうね、お師匠様」
ジルは、紅くなったままうなずき、焦って食事を再開した。
ようやく、彼らを隔てる障害がすべて消えたかに思われたが、サマエルは、すぐにジルと結ばれる必要性を感じなかった。
ジルは、まだ無邪気なままで、彼のことも相変わらず“師匠”と呼んでいたし、焦ることもあるまいと思ったのだ。
丹精込めて育てた花の、つぼみが開くのを楽しみに待つように、彼は少女の成長を待った。
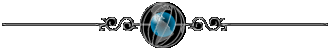
それから、五年ほどが経ち、最初の子供が生まれた。
息子は、当然ながら強い魔力を持っていた。
長ずるにつれ、放射される力はさらに強さを増し、そのため、サマエルとジルが結ばれたことに、天界も気づいた。
そこで、ミカエルではない大天使が次々遣わされ、ジルと子供を力尽くで天界へ連れ去ろうとした。
さすがに
しかし、怒りに燃えるサマエルが、手を下すまでもなかった。
その頃すでに、人界で知らぬ者がないほどの魔法使いになっていたジルに、彼らはまったく歯が立たず、すごすごと引き上げていったのだ。
魔界にも、幾度か使者が立てられ、話し合いが持たれたようだったが、サマエルの思惑通り、戦にはならずに済んだ。
その後、さらに三人子供が誕生し、やがて、それぞれ結婚して親元を離れ、サマエルとジルは二人だけの生活に戻った。
ジルは、やはり天界の血筋なのか、それとも、サマエルのそばにいるためなのか、あまり年を取らなかった。
孫達も大きくなり、曽孫が生まれ、彼らがまた子孫を残し……。
そうやって、ゆっくりと年月が過ぎていく。
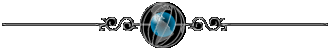 ※ サマエルとジルの結婚後の様子については、番外編「BLUE MOON」にてどうぞ。
※ サマエルとジルの結婚後の様子については、番外編「BLUE MOON」にてどうぞ。
柔らかいのに弾力性がある。基本的には綿だが、絹で織られたものもある。