8.黒き月の見る夢(2)
「サマエル、サマエル! お願い、正気に戻って! サマエル!」
誰かが繰り返し、ただ一人の名を呼んでいた。
それもまったく耳に入っていない様子で、眼を閉じ、ソファに腰掛けている第二王子の整った顔には、魔界ではまったく見せたことがない、至福の笑みが浮かんでいる。
ここは、紅龍城のサマエルの部屋だった。
広くはあるものの、一国の王子が住んでいたとは思えないほど、意図的に華美な装飾が避けられている私室で、懸命に声をかけていたのは、後ろ手に縛られ、床に転がされたイシュタルだった。
ダイアデムと同時に捕えられ、この城に監禁された彼女の両手足には、装身具に似せて作られた魔法具が冷たい輝きを放ち、魔力を封じている。
「サマエル、わたしの声が聞こえないの!? 答えて、サマエル!」
先ほど、この部屋に連れて来られてから、彼女は、甥の意識を呼び覚まそうと一心不乱になっていた。
そして、今、その奮闘は実を結びつつあった。
数え切れないくらいの呼びかけに、サマエルはようやく反応を見せ、眼は閉じたままだったものの、顔を上げ、ゆっくりと首を左右に動かし始めたのだ。
やがて、形のいい唇が開かれ、言葉を発し始める。
「……叔母様? ああ……叔母様の声、が、聞こえる気が、する……?」
「やったわ! サマエル、目覚めたのね!」
イシュタルは喜んだ。
「ああ、叔母様、起こさない、で……僕、今、とってもいい夢を見てるんだ……こんなに、いい夢、僕、初めて見るよ……。
だから、起こさないで、叔母様……」
話し始めたのも束の間、再び、サマエルはうなだれてしまう。
「駄目、そんな夢なんかに、溺れちゃ駄目よ!」
イシュタルは、もどかしげに体を揺らし、必死にそばまで這っていって、甥をつついた。
「ねえ、ジルはどうするの! 今も人界で、お前を待っているのよ、あの娘は!」
すると、眼をつぶったまま、彼は首をかしげた。
「……ジル? ……誰? 聞いたことが、ある……けど……?」
「お前、彼女のことまで忘れてしまったの!?
ジルと結婚するんだって、うれしそうに報告してくれたじゃないの!」
王子は眉を寄せた。
「ジル……と、結婚……僕が?」
「そうよ、サマエル! 思い出して!
タナトスとお前は、彼女を取り合っていたのでしょう!」
その言葉に、サマエルは再び顔を上げる。
「……そう、だった……タナ、トス兄様は……いつもジルに……」
「思い出したのね、そうよ、サマエル! 眼を開けて、わたしをご覧!」
もう少し、あと一押しで完全に目覚めさせられる。
イシュタルの心に、希望が差したその刹那。
「せっかくよく眠っているものを、起こしてもらっては困るな、我が
突如、上から声が降って来た。
そのいやらしい響きに、もちろん、イシュタルは心当たりがあった。
「ベルフェゴール! あんた、こんなことして許されると思っているの!?」
上目遣いに、噛み付くような口調で言い立てる。
大公は、ぶよぶよの眉間に深いしわを刻んだ。
「おぬしまで、我を左様に呼ぶか、あばずれめが」
「何よ、魔界王家の面汚し! 早く、サマエルを元に戻しなさい!」
身をよじらせて、彼女は異母兄を睨みつける。
「黙れ、この
ならば!」
ベルフェゴールは、怒りのままにイシュタルに飛びかかり、力任せに、ドレスの胸元を引きちぎった。
「──いやあっ!」
思わず彼女は悲鳴を上げる。
と、いきなり、サマエルが眼を開けた。
「叔母上? どうなさったのですか?」
その口調は、思いがけずしっかりとしている。
「……? 私は……今まで何を……」
彼は困惑した表情で、周囲を見回し始めた。
「ち!」
ベルフェゴールは、慌てて異母妹から身をもぎ離し、懐から黒い革表紙の書物を取り出した。
「サマエル、おぬしは我の下僕、命あるまで眠るがよい!」
「うっ!?」
本が光を発すると共に、額や手足に埋め込まれた宝石が輝き、サマエルは一声上げて、ぐったりとなる。
「サマエル、駄目よ、眠っては!」
イシュタルは叫んだ。
「いくら呼び立てようとも、無益よ。この“書”が、サマエルの心を縛りつけておるのだからな」
得意げに、ベルフェゴールが鼻先に突き出す書物を見て、彼女は顔色を変えた。
「そ、それは“禁呪の書”!? 封じられていたはずなのに!」
大公は、にたりと笑った。
「我が封印を解いた。これさえあれば、サマエルは永遠に我が
こやつを通じ、我が影の王として魔界の実権を握るのだ!」
“禁呪の書”……百とも、百八冊とも言われる、禁断の魔術書……には、
魔界王家にも、わずか五冊ほどが、宝物庫の地下に封印されてあるだけだった。
「あんた、
異母妹の言葉に、ベルフェゴールは否定の身振りをした。
「いやいや、左様な詰まらぬことをすれば、幾つ命があっても足りぬわ。
もっと穏便に、密やかに、我は魔界を統治するのだ……サマエルの陰におれば、それが容易に出来よう」
イシュタルは、藍色の眼を怒らせた。
「表立って、王を
潜王とは、王家の血を引いていない、あるいは身分不相応なのに王を名乗る者のことであり、僭称とは、身分を越えた称号を、勝手に名乗ることである。
「何とでも申すがいいわ。
……なれど、これ以上、ここにおぬしを置いておっては、サマエルが再び目覚めぬとも限らぬな。
共に置く方がよいと思うたのだが……面倒な」
思わず大公が
「そういうことでしたら、このわたくしが、王妹殿下を別室までご案内致しましょう……」
言いながらカルニヴェアンの小さな紅い眼は、
ねずみそっくりな二本の長い前歯の脇から舌を出して、ぺろぺろと薄い唇をなめ回し、幾度も生唾を飲み込む。

このとき、イシュタルは四万歳弱、人族では三十半ばに当たる女盛りであり、対するカルニヴェアンはニ万歳で、サマエルと同年代の二十代後半、アリオーシュは六万歳、五十代後半に相当した。
そして、ベルフェゴールは、魔族の平均寿命、十万歳を優に越え、十三万歳にも達していた。
だが、色欲を筆頭とした様々な欲望は、まったく衰えを見せず、脂ぎっている外見も、十万歳をようやく越えたばかりの弟ベルゼブルより若かったため、忌まわしい黒魔術に手を染めているのではないかと、人々は噂していた。
若返りの術には、同胞の血肉を使うのが一番効果的なのだった。
「わ、わたしに触れたら承知しないわよ!」
もがく異母妹を冷たく見下ろし、大公は言った。
「ふん……戴冠式は一週間後だぞ、カルニヴェアン」
「心配ご無用。三日で、言うことを聞かせてみせます……よっと」
背の低い子爵は、意外に力があるところを見せて、イシュタルを軽々と担ぎ上げた。
「な、何をするの!? 降ろしなさい、カルニヴェアン!」
「ご心配せずとも、すぐに降ろして差し上げますよ、広いベッドの上に、ね」
にやにや笑いながら、ねずみ似の子爵は、もがく美女を背負い、部屋を後にする。
「待て。おぬしら、決して無理をするでないぞ」
手をすり合わせ、それに続こうとするアリオーシュに、ベルフェゴールは声をかけた。
「ほう……あなた様でも、妹ごのこととなるとご心配ですかな」
意外そうな顔で振り返った男爵に、大公は肩をすくめて見せた。
「愚か者、左様なことを申しておるのではないわ。
腹違いとは申せ、イシュタルは、我が父にして偉大なる前王、バフォメットの娘。
サキュバスの総元締め、最上級の女夢魔だと言うことを
リリスごとき、足元にも及ばぬのだぞ。
おぬしら下級貴族では、十人束になろうとも、あの女を堕とすどころか、満足させることさえ
アリオーシュは、つり上がった眼を見開いた。
「ほう、それほどとは……」
「我が気にかけておるのは、おぬしらの方だ。
ついに、我らが魔界の支配権を手にするというせっかくの晴れ舞台に、腰を抜かして出席出来ぬなどという
「……なるほど、それはごもっとも。肝に銘じておきまする。
子爵にも、しかと申し伝えましょうぞ」
男爵は胸に手を当て、優雅にお辞儀をした。
(……とんだ大根役者よの)
ベルフェゴールはつぶやいた。
目の前にいる鶴のように
「……何か?」
「いや、こちらのことだ」
ベルフェゴールは胴体にめり込みそうな、太い首を振った。
「……ともかく、分不相応なサキュバスに溺れた男の哀れな末路、おぬしも存じておろう。
精気を吸われ尽くし、廃人となり果てるのだぞ。
我も手伝うてやろう。しばし待っておれ。サマエルの術を強化し、すぐ参る」
「は。お待ち致しておりまする……カルニヴェアンにも知らせねば」
大公に釘を刺されたアリオーシュは、あたふたと子爵の後を追った。
「さ、サマエル、起きよ。隣室へ参れ」
その言葉に眼を開けたサマエルは、何事もなかったように立ち上がり、扉へと向かう。
途中、彼の唇が、かすかに動いていることに気づいたベルフェゴールは、何を言っているものかと耳を寄せた。
「……叔母様、ご免なさい……目が覚めたら、きっと、お話しますからね……。
とっても……いい夢なんだよ……。
父様と、母様は、いつも、にこにこしてて……僕を、ぎゅっと、抱きしめてくれて……他の皆も、とても優しいんだ……」
そこまで言うと、サマエルは小首をかしげた。
(何と……!)
大公は我知らず、ぎゅっと眉根を寄せた。
第二王子は、さらに話し続けた。
「でもね……変なんだ……。
誰に訊いても、僕は一人っ子で……兄弟はいない、って言うんだよ……。
父様に訊いたらね……兄様は……死んで生まれたんだって……。
だから、お前は……その分、長生きして……いい王様にならなきゃいけないぞ、って……父様は……優しく、頭をなでてくれたよ……。
……ねえ、叔母様……僕と、タナトス兄様は……夢の中でも、一緒にいられないんだねえ……」
悲しげなその口調は幼く、声も子供のようだった。
ベルフェゴールは舌打ちした。
(……ちっ、未だ、今見ているものを、“夢”と認識できておるとは……。
先ほどといい、さすがは魔族の王子、“禁呪の書”を用いても、一日やそこらでの完全支配は無理か。
……まあよいわ。あと六日のうちに、意思のすべてを、絡め取ってしまえばよいこと)
「よし、サマエル、そこに
「はい……ご主人様」
青白く光を発する魔法陣の中央に、王子は従順に横たわる。
大公は再び“禁呪の書”を開き、かつて唱えたと同じ、長い呪文の詠唱を始めた。
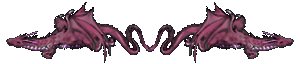
一週間後。戴冠式の日がやって来た。
サマエルは、独り、静かに控え室に座していた。
その心は完全に支配され、紅い眼も虚ろに見開かれて、何も映してはいない。
背中でゆるやかにまとめられた銀髪と、長い
そして、衣装だけでなく、レースの長手袋、革の短いブーツ、さらには、翼を包むマントまでもが白に統一されているため、その美貌と相まって、人界では花嫁と間違えられかねない出で立ちを、今日の彼はしていた。
従来、魔界では、純白の衣服は
これは、
その一方で、魔界王及び女王の戴冠式での衣装は、太古より白と定められていた。
魔族の君主は、“死を超越して魔族を導く者”とされ、式後、黒衣に着替えることが慣例となっていた。
「お時間でございます、お出ましを」
呼びに来た女官にうなずいて見せ、サマエルは立ち上がった。
「ご出座! ご出座──!」
掛け声と共に、華々しくラッパが吹き鳴らされ、空中から、香り高い純白の花びらが振りまかれ始めた。
荘厳な音楽をパイプオルガンが奏でる中、第二王子が、しずしずと舞台の右袖から登場する。
途端に、
「サマエル様、万歳!」
「新魔界王陛下、万歳──!」
重要な儀式時にのみ使われる、格式高いシャンデリアの
舞台中央にしつらえられた、黄金よりも美しく希少な貴金属──人界ではオリハルコンとも呼ばれる──で作られた大型の玉座。
“玉座の間”を埋め尽くす家臣達の衣装は、当然、黒一色で、白装束の新魔界王サマエルは、際立っていた。
「シンハ閣下のお出まし──!」
再びラッパが鳴り響き、今度は、左袖から、黄金に輝く魔界の獅子が現れ、観衆の熱気は、
こうして、ついに、