1.陰謀への招待(1)
朝が訪れた。
「お師匠様、おはようございま~す!」
栗毛の少女が、元気な声であいさつをし、席に着く。
この少女、ジル・アラディアは、四年前、
「おはよう、ジル」
穏やかに答え、いつも通り魔法の授業を始めたものの、サマエルは、どこか上の空だった。
「お師匠様、どうしたの? ぼんやりして。雪の季節は、まだ先よ」
弟子に声をかけられて、サマエルは我に返った。
「あ……あ、すまない、ジル」
「どっか具合でも悪いの?」
「大丈夫だよ。ただ……昨夜、ちょっと気になる夢を見てね……」
彼は、心配そうに顔を覗き込んで来る少女に、微笑んで見せた。
「……夢? 恐い夢を見たの?」
ジルは可愛らしく小首をかしげる。
サマエルは
「いや、恐くはなかったな。
男か女かも分からない人物が出て来て、『危険』と告げて消える、という夢で……よく知っている相手のような気がするのに、いくら考えても、誰だか分からなくてね。
そのせいか、心に引っかかってしまって……」
「ふ~ん、そういうのって、気になるもんね。
でも、正夢だったら困るわ、何か危険があるのかしら?」
「……分からない。今まで見た予知夢とも、少し違うようだ……」
サマエルは、心ここにあらずと言った表情で、視線を遠く
「よく眠れなかったんじゃない、お師匠様。
顔色が悪いみたい、休んだ方がいいわ」
「眠くはないが、やはり気になるな。ちょっと調べてみたいから、午後の授業は休みにしよう。
……今日はいい天気だ、花畑にでも、行ってみたらどうかな」
「うん」
その日の夕食は、ジルと魔界の公爵プロケルだけという淋しいものになった。
彼女が帰って来てからも、もう少し調べたいからと、サマエルはまだ地下室にこもっていたのだ。
氷剣公とも呼ばれるプロケルは、サマエルの父、魔界王ベルゼブルにより、人界へ派遣されて来ていた。
次期魔界王に決定しているサマエルの兄、タナトスがジルを気に入って妃にしようとし、元々彼女を密かに思い続けていたサマエルと、三角関係に陥ったために。
ここにはもう一人、ジルの
ジル達と同居を始めてから、彼女は、タナトスを愛してしまったのだった……彼が、
「正直なところ、イナンナ殿には、あまり深入りして頂きたくはないですなぁ……」
料理上手なサマエルの使い魔が腕を振るった、さほど豪華ではないが、
その眼は、食卓上の灯りを反射して、猫そっくりに輝いていた。
「……どうして? やっぱりイナンナが、魔法を使えないから?」
「そればかりではございませぬぞ。
魔界の環境は過酷ゆえ、人族の
「ふうん。魔界の宮殿にいれば大丈夫だって、タナトスは言ってたけど……」
プロケルは、ため息をつく。
「それは無論、
いかんせん、イナンナ殿は、まったく魔法がお使いになれない……。
彼女が王妃となれば、家臣達の中から、様々懸念の声が上がるのは
「魔界の王妃様が、魔法使えないんじゃ、やっぱり駄目……なの?」
おずおずとジルは尋ねる。
公爵は厳粛な顔つきをした。
「
「そう。どっちにしろ、あたしは魔界に行くつもりないから、関係ないけど」
「左様、左様」
魔界公は、幾度も深くうなずいた。
「かようなことを申せば、タナトス様にはお叱りを受けましょうが、それがしも、それが賢明だと思いまするぞ。
それゆえ、イナンナ殿にも、タナトス様を諦めて頂ければと思うておるのですが……」
ジルは、顔をしかめた。
「えー、誰を好きになるかは、イナンナの自由でしょ。
でも、せめてタナトスが、王子様じゃなかったらよかったのにね。
そしたら、ずっと人界にいられるし、イナンナに魔力がなくたって、別によかったのに……」
プロケルは否定の仕草をした。
「いやいや、たとえ、タナトス様が王子でないと仮定致しましても、あのお方はおそらく、あなたのことを……」
「そう……かしら。
あたし、タナトスのことは、特に嫌いってわけじゃないんだけど……」
言葉を
「それ以上、
出来得るならば、皆が幸せになれればよいと、それがしも思ってはおりまするが……」
「うん、そうね……」
彼女はうつむき、後は二人とも、黙々と食事を口に運んだ。

その少し前。
「タナトス様、なぜ……わたくしを、お誘い下さいましたの……?」
有頂天のイナンナは頬を染め、そう尋ねていた。
波打つ銀髪をきっちりと後ろでまとめ上げ、腰には鋭い剣を帯び、彼女は、一見すると少年のような出で立ちをしていた。
美しい顔の少しつり上がりぎみの眼は、静かな湖面にも似た深い緑色を
豊かな胸は、軽量の鎧に隠れてはいるものの、身のこなしが優美なこともあって、女性であることは隠しようもない。
幼い頃、ジルとは同じ村に住んでいたのだが、母と共に伯爵家に引き取られて以来、離れ離れになっていた。
村が疫病で全滅した後、従妹が賢者に助けられ弟子になったと人伝えに聞いた彼女は、サマエルの屋敷を尋ねて来て同居することとなった。
そして、時折ジルに会いに訪れるタナトスを愛するようになっていった。
しかし、いくら剣技は
たとえ、彼が、従妹のジルを想っていなかったとしても、相手にされるわけもなく……仕方のないことだとは言え、いつも悲しい思いを味わって来た。
それだけに、今回、魔界に招かれた少女が、ぼうっとなるのも無理はなかったのだ。
そして、胸をときめかせているイナンナと向かい合い、対照的な表情を浮かべているのが、彼女の思い人だった。
冥界の大河の流れを思わせる黒髪、きつい光を湛えた紅い瞳を持ち、頭には二本角、背中にはコウモリに似た翼を生やした男。
彼こそが“
「キミを誘った理由だと? 聞いてどうする、そんなもの」
王子にふさわしく、宝石の飾りがついた豪華な衣装と、金の縁取りマントに身を包んだ彼は、
「い、いえ……ちょっと、気になったものですから……」
「ふん。一人で魔界に帰っても退屈なだけだからな。
本当は、ジルを連れて行きたいところなのだが、サマエルのヤツがうるさい。
誰か手頃な者がいないかと話していたところへ、たまたまキミが来たから、声をかけてみただけだ。
それでは不服か?」
(ええっ! たまたま、来たから? 誰でもよかった、の……?)
一瞬、少女はショックを受けたものの、偶然にせよ、声をかけてもらえて幸運だと、前向きに考えることにした。
「い、いいえ、光栄ですわ。喜んでお供させて頂きます」
「そうか。では、行こう」
「はい……」
「……にしてもだ、サマエルめ。
あんなことがあったというのに、いまだにジルの保護者面をしておるとは……!
浮浪者も同然の身で、まったくもって
タナトスは整った眉をしかめ、王族にはふさわしくない悪態をついた。
愛する少女ジル、その師匠が、彼とは犬猿の仲である実の弟だったために、無闇に彼女を連れ出すわけにはいかなかったのだ。
その上、魔界王家の世継ぎとして、魔界でやるべきことも多々あり、
それで、イナンナを誘った本当の理由も、素直に口に出せなかったのだった。
数ヶ月前、サマエルのちょっとした油断から、ジルが邪悪な魔法使いにさらわれてしまうという事件が起こり、彼女を救出する際、同行した少年に、タナトスは危ういところを二度、救われた。
その少年は、結界を解くため持参したアイテム“王の杖”にはめ込まれた宝石、“
助ける際、条件としてダイアデムが出したのが、『もう一度イナンナに会いたい、魔界に連れて来て欲しい』というものだった。
特殊な立場にある彼は、よほど特別な場合を除き、魔界を出ることは許されていなかったのだ。
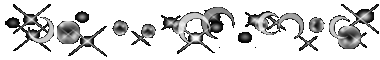
人界から魔界へ行くには、サマエルの屋敷の地下から魔法陣に乗るしかない。
一応、弟に断りを入れ、二人は地下室へと下りた。
複雑な心境のまま、イナンナはタナトスに次いで、輝きを発する魔法陣に乗った。
ふわりと体が浮き上がるような移動感が彼らを包み、それが収まったとき、二人はタナトスの城である
出迎えた召し使いは、うやうやしく
「お帰りなさいませ、タナトス殿下。ベルゼブル陛下よりご伝言がございます。
お戻りになられましたら、すぐに、汎魔殿の執務室へお越しになるように、との
「ちっ、またか。ふん、どうせ、大した用でもあるまいに!」
しかめっ面をした王子は、少女に視線を移した。
「そうだ。イナンナ、キミも一緒に行くか?」
「えっ、よろしいのですか? お仕事のお邪魔になるのでは……」
「無論、重要な会議には連れて行けんが、そんなものはほとんどない。
ここで待っていても退屈だろうし、汎魔殿も結界で囲まれているしな。
用が終われば、城の中を案内してやってもいいぞ」
それは優しさからというわけではなく、単なる彼の気まぐれだった。
本当なら、黔龍城で待たせておいて、ダイアデムを呼べば済むことだったのだから。
「はい! そう仰って頂けるなら、喜んで、ついて参りますわ!」
もちろん、イナンナに異論はなかった。
「よし、急ごう。親父は気が短いからな。
こっちだ、イナンナ」
自分のことは棚に上げて、タナトスは言い、二人は、魔界の宮殿へと通じる魔法陣に乗り替えた。
再び浮き上がるような感覚があり、それが終わると、周囲は完全に闇に包まれていた。