3.猫眼の公爵(2)
当初は面食らったプロケルも、日が経つにつれジルに好意を持っていき、彼女にとっての幸福は、ここにいること、つまり、サマエルのそばで暮らすことなのではないか、と思う気持ちが強くなっていく。
そんな折、タナトスが人界へやって来た。
「どうだ、プロケル。あれから二月経ったが、ジルは無事なのだろうな」
「無論でございますとも。
……ご覧になられて、お分かりになりませんでしょうかな、タナトス様」
魔界公は、心外だと言う態度を隠そうともしなかった。
「そうむくれるな、念のため聞いたのだ。あと三日、俺は人界にいる。
親父が、貴様の報告を聞きたいと言っていたから、帰れ」
タナトスは、彼を追い払うように手を振る。
「──は」
プロケルは一礼し、その場を去った。
サマエルに帰還する旨を告げ、魔法陣で魔界に戻ると、公爵は、さっそく主君の許へと向かった。
「只今、戻りましてございます、陛下」
うやうやしく御前に片膝をつき、礼をする。
ベルゼブルは
「左様な儀礼は、この際は抜きじゃ。
どうなのじゃ、プロケル。そなたが見たジルと申す娘は?
まこと、魔界の王妃にふさわしき者か?」
「……は。まず、魔力につきましては、安定せず、いまだ研磨途中の宝石の原石かと。
ですが、時折垣間見せる輝きの片鱗はすばらしく、かなりの潜在力を秘めておると思われます」
「ふむ。サタナエルの眼に、狂いはないと?」
「魔力につきましては。しかしながら……」
「何じゃ、申してみよ」
「はい……あの娘の力は、純粋無垢に過ぎるように見受けられ、それゆえ……いや、これは、それがしの私見でございますゆえ……」
プロケルが口ごもると、魔界の王は立ち上がって公爵の手を取った。
「この際じゃ、思うことをすべて、
ありのままを、余は知りたいのじゃ、プロケル公よ」
氷剣公は、胸に手を当て、深々と礼をした。
「……それでは、ありていに申し上げます。
ジルなる娘は、魔族の王妃にはそぐわぬと存じます。
娘は、天界の女神に近しい力を有しており……神族の子孫である可能性も考えられます」
「何と、天界の血筋やもしれぬと申すか。たしかにそれでは、魔界にはそぐわぬな……」
「ご存知でもございましょうが、単なる人の子にとりましても、馴染みない魔界の気候風土、習慣はなかなか受け入れがたいもの。
ましてや、天界の血を引くともなれば、苦しむだけのように思われてなりませぬ。
第一、娘自身が拒むことでしょうな、魔界に参ることを。
タナトス殿下を嫌うからではなく、師であらせられるサマエル殿下を、
いずれにせよ、このまま人界で過ごさせた方がよいと、それがしは心得ますが」
「なに、慕っておるじゃと? あのルキフェルめを、か?
まさか、あやつ、夢魔の力で、娘を操っておるのではなかろうな、
左様なことがあれば、今度こそ極刑は免れまいぞ!」
魔界王は、
「いやいや、夢で操っておるご様子など、一切ございませぬ」
氷剣公は、即座に否定した。
「それはまことであろうな」
ベルゼブルは、重々しく念を押した。
「無論でございますとも。
サマエル殿下は、
また、殿下は、娘のそばにいると心が和み、狂気が遠のくと
察するに、ジルは、浄化の力を持っておるのでございますな。
殿下の中に
それゆえ、お二人が結ばれても、よろしいのではございませぬか。
よしんば、天界が、娘の魔力に眼をつけ、女神に召し上げようと画策致しましても手出しが出来ず、一石二鳥と申せましょうぞ」
「……ふむ。敵とするより、取り込んで味方にするが得策。それゆえ、人族との交わりもやむを得ぬか。
なれど、その場合、問題となるのはサタナエル……じゃな」
「左様でございますな。タナトス殿下が、それでご納得なさるとは……到底……」
雪のように白い髪をした、魔界の王族達は眼を合わせた。
瞳の色こそ違え、容貌の相似は、彼らが血縁関係にあることを 明確に示している。
魔界の王は、顔をしかめ、純白のヒゲをなでつけた。
「……まことに困ったものよ、魔界の王子ともあろう者が、おなごなどに、うつつを抜かしおって!
我ら夢魔にとり、女はあくまでも食事。
または、子を産ませるための道具に過ぎぬ、愛情など二の次でよいと言うに。弟のみならず、兄までとは、まったくもって情けない……」
無言のまま、プロケルは軽く頭を下げた。
彼の考えは、主君とはまったく違っていたが、身分制度の厳格な魔界のこと、求められてもいない意見を口にすることは、はばかられたのだ。
「しからば、陛下、今後は、いかが致せばよろしいのでしょうかな」
「ううむ……」
どっかりと腰を下ろしたベルゼブルは、豪華な椅子の背もたれに寄りかかり、ひじ掛けをコツコツ指でたたきながら、しばし思索にふけった。
「……そうじゃな。
やはり今少し、様子を見ることと致そう。これ以上、もめ事の種は増やしたくはない。
サタナエルは、三年待つと申しておるゆえ、そなたはその間、息子達を監視するのじゃ」
「しかと承りました。このプロケル、最後のお勤めと致しまして、誠心誠意、務めさせていただきます、陛下」
「引退間際と申すに、無理を申して相済まぬな。かようなことを頼めるのは、
手数をかけるが、よしなに頼むぞ」
「……もったいなきお言葉」
魔界公爵は、胸に手を当て、うやうやしくお辞儀をした。
「よー、ベルゼブル、話、終わったかぁ?」
そのとき、いきなり扉が開いて、一人の少年が、ひょっこり顔を出した。
少女と
鮮やかな紅色の髪を背で束ね、眼もまた、髪同様に紅い。
驚くことには、その少年の瞳には
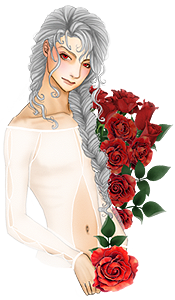
「これは“
プロケルは、ていねいに礼をし、ベルゼブルは美貌の少年に尋ねた。
「
大きく伸びをし、ダイアデムと呼ばれた少年は答えた。
「んー、次元が震えてうるせーと思ったら、次元回廊を使ってたんだな、そのせいで眼が覚めちまったぜ。
けど、タナトスのヤロー、今度は人界の女に入れ揚げてんのかよ、しよーがねーな」
王に対するには、あまりに
「まったく、サタナエルにも困ったものよ。
今、このプロケルに、監視を頼んだところじゃ……ルキフェルとも関わりあることじゃでな」
「ふーん。でもいーよな、魔界の外に行けてさ。
なあ、ベルゼブル、オレもたまにゃ、どっか行きてーよぉ」
「何を申しておる、魔界の象徴たるそなたが、気安く人界へ参ることなど、許されると思うてか」
今度は、さすがにベルゼブルも、たしなめるような口調になった。
「ちぇっ、つまんねーの」
少年は、可愛らしく口をとがらせた。
「考えてもみよ、“
「……ちぇっ、分かったよ。
じゃ、その三角関係が進展したら教えろ。それまで、また寝てっからさ。
あーあ、退屈だなーっと」
ダイアデムは、頭の後ろで指を組み、ぶらぶらと部屋を出て行った。
魔界公爵は、溜めていた息をようやく吐き出すことが出来た。
紅毛の少年の美しくも特殊な瞳は、否応なく魔族を
さすがに、魔界王や王子達は、その限りではなかったが。
ベルゼブルもまた、大きなため息をついた。
「サタナエルも、あれくらい聞き分けがよいと、助かるのじゃがな……」
その後、三日間、休暇をもらい、気分も新たにプロケルが人界へ戻ってみると、魔界王家の兄弟王子の間には、いつにも増して、険悪な空気が流れていた。
「……一体、いかがなされたのですかな、ジル」
プロケルは、こっそりと栗毛の少女に尋ねた。
ジルも小声で答えた。
「あのね、あたしが焼いたケーキを、三人で食べようとしたの。
そしたら、タナトスが、お師匠様のが大きいって言い出して、それで……」
「はぁ? ケーキの大きさ……ですと?」
魔界公は、思わずあきれ声を出してしまい、タナトス王子の鋭い視線を浴びて、急いで口をつぐんだ。
「子供みたいでしょ? でも、いくら突っかかって行っても、いつもタナトスが負けちゃうんだけどね。
お師匠様が、ひと
それは、サマエルの“
鮮紅色の瞳や魔眼自体は、魔族には珍しくもないが、“カオスの貴公子”のものは、一味違っていた。
日頃は物静かな彼の瞳に、暗い闇の炎が灯り、それが燃え広がってゆく。
“紅い死神”と異名を取る、魔界王家の第二王子の、死をもたらす
たとえ死ななくとも、見据えられた者の心に、決して消えない
氷剣公プロケルも、直に眼にするのは初めてだった。
魔族の自分でさえ、身震いを抑えかねているのに、ジルは平然としている。
タナトスが、彼女を魔界の王妃にと考え、夢中になるのも無理はない、改めて彼は思った。
だがそれは叶わぬ夢に終わりそうだな、というのが、公爵の正直な感想だった。