3.猫眼の公爵(1)
第一王子の行動を、快く思わない人物がいた。
現在、魔界の王位に
久しぶりに魔界に戻った息子を、魔界王は呼び出し、説教を始めた。
「よいか、サタナエル。人族の娘になぞ、うつつを抜かしておる場合ではないぞ。
そなたは、次期魔界王として、魔界にて学ばねばならぬことが多々あるのじゃ、それを……」
「うるさい、口出しするな! 俺は俺のやりたいようにやると決めている!」
タナトスは、いつも通り、そんな父親に反抗した。
サタナエルとは、タナトスの真の名であり、父王は、常に彼をそう呼んでいた。
「う、うるさいとは何事だ、親に向かって!」
ベルゼブルは、紅い眼を燃え上がらせた。
さすがは親子、頭頂部の二本の角を振り立て、そうやって怒っている様は、タナトスとよく似ていて、相違点といえば、髪の色くらいなものだった。
年齢を重ねれば、タナトスが、父親そっくりになることには疑いがなかった。
「ふん、今さら血のつながりを持ち出すか!
親父だとて、七面倒なことなど、どうせ、大臣あたりに押し付けて済ませているのだろうが!」
黒髪のタナトスは、銀髪の父王に指を突きつけた。
ベルゼブルも、負けじと言い返す。
「たわけ者!
そなたが、余をよく思っておらぬことはさて置き、世継ぎの王子が左様な心構えでおって、魔界の未来はいかがするのじゃ!」
怒りのあまり、タナトスは
「だから、今、魔界の王妃にふさわしい女を、妻にしようとしているところだ!
黙って成果を見ていろ! 邪魔をするのは、サマエルだけでいい!」
息子の言葉に、ベルゼブルは顔色を変えた。
「何、女じゃと……まさか、そなたまで……」
「たわけ、俺を、あの生まれぞこないと一緒にするな!
天界に対抗するためには、強大な力を持つ女に、ガキを産ませねばならんのだろうが!」
父親似の角を振り立て、タナトスは
この二人は、顔を合わせると、いつもこの調子だった。
激しくののしり、互いの主張をぶつけ合って、譲ることがない。
そのことに思い至った魔界の王は、まずは、自分が冷静になろうと、雪白のあごひげをなで付けた。
「……妃のことなど、王位に就いてからでも遅くはあるまいに、まったく仕様のない……。
なれど……魔界の王妃にふさわしい女……ルキフェルが邪魔を? よもや……」
ベルゼブルはつぶやく。
ルキフェルとは、サマエルの真の名である。
父親が静まったことで、タナトスも少し落ち着き、呼吸を整えて答えた。
「いいや、サマエルの女ではない。
単なる弟子だと言うのに、保護者面をしおって、あと三年待てだの何だのと、うるさいのだ」
「ほう、ルキフェルが弟子にしているとは。その娘、歳はいくつになる」
興味を引かれて、ベルゼブルは尋ねた。
「ああっと、たしか……十五になったばかりのはずだが」
王は顔をしかめた。
「……人族の十五とは、たしかに若いな。
歳ばかりではない。どれほどの力の持ち主か知らぬが、人族の者が魔界で生き抜くのは、今までの例を引くまでもなく、かなり厳しいのじゃぞ」
「それくらい、俺だとて分かっている。
そこで、ヤツの言うことにも一理あると、三年待ってやることにしたのだが……。
問題は、あやつ自身だ。サマエルは、死と破壊の衝動を常に抱えている“紅龍”。
おまけに、天界の女神さえもモノにするような、特上級の夢魔なのだぞ!
俺が見張っていなければ、ジルが成人する前に、ヤツの毒牙にかけられてしまうわ!」
タナトスは、またもや興奮し始め、声が大きくなっていく。
「……左様に大声を出すでないわ、頭に響く。
しばし待っておれ。少々、考えをまとめたい……」
ベルゼブルは、そう言って黙り込み、タナトスはじりじりしながらも、父親が断を下すのを待った。
やがて、魔界の君主は心を決め、口を開いた。
「いかに、その娘が王妃にふさわしくとも、いまだ年若く、魔界に連れて参るは早計……。
それは、ルキフェルの申す通りじゃ」
「親父……!」
口を挟みかける息子を、ベルゼブルは手を振って黙らせた。
「最後まで聞くがよい、サタナエル。
分かっておる。余とて、保護するにはやぶさかでない。氷剣公を
そなたは、魔界で、せねばならぬことがあるのじゃからな」
その言葉に、タナトスは、父親似の紅い眼を、くわっと見開いた。
「プロケルだとぉ!?
あんな老いぼれ、サマエルにかかっては
「何を申すか、プロケルとて公爵、
サマエルも、親しみを持っておるようじゃ、あれ以上に適任の者はおらぬであろう」
「し、しかし……」
「気に掛かるのであれば、時折人界に参るのは構わぬ。されど、今まで同様、入り浸るのは許さぬぞ!
その上で、娘にはまだ手を出してはならぬ、人界で平穏に過ごさせ、成人してより連れて参るのじゃ!
これは、父親としてだけではなく、魔界の王としての命令ぞ! 破れば、そなたに王位は譲らぬ!
分かったか、サタナエル!」
魔界の王は、毅然とした態度で言ってのけ、息子に指を突きつけた。
てこでも動かぬ父王の様子に、さしものタナトスも渋々折れた。
「……ちっ、仕方がない。時々なら、行っても構わんのだな?
それなら、プロケルは、あいつの屋敷に住まわせて、見張らせた方がいいぞ」
「では、左様に申し渡そう。
そなた、プロケル公を呼んで参れ」
ベルゼブルは小姓に命じた。
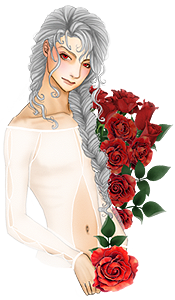
「かようなわけでございまして……。
父君、魔界王ベルゼブル陛下直々のご命により、こうして参上
翌日、任命を受けた氷剣公爵プロケルは、人界へと
「そうか、手数を掛けるね、プロケル」
サマエルは、悲しげに微笑んだ。
「お気に
自分の責任でもあるかのように、恐縮して公爵は頭を下げた。
「別に構わないよ、かえって助かる。渡りに船と言ってもいいな。
彼らが気をもむのも、無理はない。
私自身、いつ、自制が効かなくなってしまうかと、気が気ではないのだからね……」
サマエルは、魔族によく見られる緋ひ色の眼を伏せ、わずかにうつむいた。
その仕草に連れて、これまた魔族によくある白銀の髪が、さらりと頬にかかる。
「左様なことを、殿下……」
「事実なのだから、しようがないさ」
サマエルは首を振り、銀の絹糸のような髪をかき上げた。
彼に同情を寄せながらも、この魔界の王子は、試練に遭うたびに美しくなっていくなと、プロケルは思った。
「それと、“殿下”はやめてくれ、私には、もう王子の資格はないし、そう呼ばれたくもない。
……陛下も、私のことなど、息子などとは思っておいでにならないだろう」
「いえ、陛下は……」
言いかけたプロケルは、彼の表情を見て、それ以上を言葉にするのを控えた。
「分かり申した、お名前でお呼び致せばよろしいのですな」
「ああ、そうしてくれ。何はともあれ、ジルのためにも、お前を歓迎するよ。
さっそく彼女を呼ぼう」
“ジル、私の部屋へ来ておくれ”
サマエルは、心の声で弟子を呼んだ。
“はーい、お師匠様!”
元気な足音が近づいてくるのを、プロケル公爵は鋭敏な魔物の聴覚で聞き取り、魔界の王妃にと
その足音が部屋の手前で止まったかと思うと、何の前触れもなくドアが音を立てて大きく開き、少女が顔を出した。
「お師匠様、ご用?」
「これ、入室の前にはノックをしなさい、ドアの開閉は静かにと、いつも言っているだろう」
「あ、お客様が来てたの、ごめんなさーい」
ジルはちょろっと舌を出し、それから頭を下げた。
プロケルの眼に映ったのは、はつらつとした少女だった。
二つのお下げに結った栗色の巻き毛、表情は、まだあどけない。
およそ美人とは言いがたく、女王と言うよりも、下働きの娘と呼んだ方が、ぴったりくる感じだが、大きな栗色の眼は澄み切って、一種、不思議な魅力を放っている。
(何ゆえであろう、この瞳の前では、魔界の貴族たる自分が、ひどく汚れているように感じられる。
この、純真
プロケルはつぶやいた。
「ジル、こちらはプロケルだ。人界に少し用があってね。しばらくこの屋敷に住むことになった」
「あ……よ、よろしくお願い致します、ジル殿」
衝撃から覚めやらぬまま、魔界の公爵は手を差し出した。
「よろしくね。あたしのことは、ジルって呼んで下さいな」
彼の手を握り返す少女の手は小さくて、力も弱く、言われているほど強大な魔力を秘めているとは、とても思われない。
「まあ、キレイな眼……ネコメオジサンって呼んでもいい?」
ジルはさらに、無邪気に言った。
プロケルの眼は琥珀色をしており、光が当たる角度で黄金の輝きを放つ。
そして、明るいところでは、猫の眼そっくりに、
「は? はあ……それは構いませぬが……」
「あたしね、昔、あなたみたいに真っ白な毛並みの猫を飼ってたの、可愛かったのよ。
……あ、ご免なさい。あなたは猫じゃないのよね」
「ふふ、魔界の公爵も、ジルにかかっては形無しだね」
魔族の貴公子は、くすくす笑った。
この王子がこんな風に笑うのを、プロケルは、初めて見た気がしていた。
かつて魔界でも、サマエルは常に微笑を絶やさなかったが、その眼は、決して笑ってはいなかったのだ。
「え? 公爵様だったの? ご、ご免なさい、あたし……」
「これは
氷剣公プロケルは、雪白の頭を
「何しろ、ジルは、私の悪口を言ったタナトスの頬を、思い切り張り飛ばしたくらいだからね」
「な、何と……!?」
驚いたプロケルの虹彩が、興奮したときの猫めいて、ぱあっと広がる。
「わ、そんなこと教えないで、お師匠様ってば!」
「その威勢のよさに、タナトスは
「は……はあ、左様で……」
意外な話の連続に、魔界公は、眼を白黒させるばかりだった。